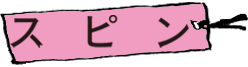『自閉症のぼくは小説家』 第3回「そして言葉は飛び出した」
内田博仁(うちだ・はくと)
2025.09.01

連載第3回 そして言葉は飛び出した
一筋の光
僕の中にある言葉に最初に気づいてくれたのは母だった。
僕が2歳の時のことだ。僕はお医者さんがいうような「物事を理解してない状態」ではないと伝えたくて、日々機会を窺っていた。
母と祖母の家に行ったある日、リビングのソファの横に置かれていた知育教材が目に入った。救急車やパトカー、消防車のサイレン音が流れて「これは何の音かな?」と聞かれ、ボタンを押して答える教材だ。
祖母は僕が何も分からないと思っているから
「音が鳴るね」
「面白いね」
と僕に話しかける。
僕は今こそチャンスだ!と思った。
僕は母の手をがしっと掴み、ピーポーというサイレンの音の後に、パトカーのボタンを母の指を使って押した。正解!と音が鳴り響いた。
母と祖母がびっくりしたのか呆然とした後、
「待ってこの子わかってる!」と興奮して叫んだ。
「じゃあこれは?」
サイレン音を出す。僕は母の指を使い次々と当てる。(今では自身の指で打てる僕だが、この頃の僕は自分の指さえもコントロールできなかったので、母の指を使い答えを示していた。)
「この子は話せないだけで色々分かってる!」
そう言いながら母は僕の中に一筋の光を見出したのか、何か決意したかのような強い目で僕を泣きながら見つめていた。
言葉のシャワー
それから母は、僕が本当に理解しているのか確認する作業に夢中になって、毎日のように僕に問題を出し続けた。
冷蔵庫は飛ぶ? ○か×か
自転車より飛行機が速い? ○か×か
など。僕は母の手を使い次々と当てる。周りからは知的障害だと、何も理解してないと言われ続けていたのだから、母の驚き、興奮は相当なものだった。そして僕の子育てに希望を見いだした母は、僕に毎日勉強を教え始めた。
言葉のカードをたくさん見せたり、数字を何度もなぞらせたり。僕は目線をその文字に合わせたりじっと集中したり反応することができなかったので、ちゃんと本当に聞いているかどうか母は分からなかったと思う。それでも母は僕を信じ続け、僕の中にある可能性、目には見えないけれど光る何か希望を疑いなく信じ、とにかく僕を毎日机に座らせ、日々教材を増やしていき、熱心にひたむきに僕の教育に励んだ。
表面的には変な声を出したり、パニックや奇声を発したりしていた僕だったが、母は僕が理解していることを前提として日々接してくれた。おかげで僕は幼少期にたくさんの言葉や知識のシャワーを浴び、僕の内面は真っすぐにすくすくと成長していった。
僕は勉強しなくてもいいの?
僕が小学校に入学して不思議に思ったことがある。教科書がないのだ。僕は本が大好きだし理科や社会や新しいことを知れること、勉強を教えてもらえることにわくわくし、期待していた。
でも支援学級では、先生が僕に合わせた教材を用意していた。幼稚園児が遊びで使うような絵カードやおもちゃや、まるで何も理解してない赤ちゃんと接するようなものばかりだった。
僕はショックだった。僕が話せないから? 目線も行動も、言われたことに無反応だから?
百人いれば百人とも違うのに、どうして一つの検査だけで全てを判断できる? もし重い知的障害があると判断された子が、本当は色々分かっていたら? 実際僕はIQが低いが、小さい頃から毎日訓練を続け、こうやって文章を綴っている。もちろん全ての子を見誤っているとは言わない。でも中には僕のように実際は色々理解していたら?
僕達がテストができないのは、理解できないからではない。思ったことを出力する手段がないからだ。脳と体の指令が上手く伝達しないだけで、適切な訓練をすればきちんと教育できるのだ。
教育は、勉強は、どんな子供にも必要だ。多くの物語や文学に触れることで自分の考えや価値観を育てられる。この世界には歴史があり、多くの方の努力と戦いで今の豊かな社会が作られたこと、僕らの周りに存在する自然や物質の存在や価値を知ること、国語や社会や理科で学べる素晴らしい知識だ。
他の子供達が当たり前に受けているこのような教育を、何故僕は受けることができないのだろうか。このような知識の積み重ねが、少しずつ僕らの内面を育て成長させてくれるのではないだろうか。そうして育った知性が大きな武器となり、僕が自身の衝動を制することができたという成功体験を、僕は何度も重ねてきた。だからこそどんな子どもにも、たとえ障がいがあろうとも、教育が大事なのだと僕は今でも思っている。
気づいてくれた人
僕が六歳の時、大きな変化が起こった。
きっかけは何も話せない僕に「この子はすべて理解はしている」と言ってくださった、ある大学の先生の一言だった。この頃の僕は、文字を本当は理解しているのにそれを伝える機会も術もなくて、もどかしく悔しい気持ちで日々を過ごしていた。だからこの時先生が僕の内面の強い思いを、「分かって」という思いをすぐに理解してくれたことが本当に嬉しかった。僕は先生のこの言葉を浴びた瞬間、まるで暗闇から光が差し込んできたような、救われたような気持ちになったのだ。
先生は僕に電子手帳を差し出し、「名前を打ってごらん」と言ってくださった。
僕は差し出された電子手帳のアルファベットをじっと見つめた。その瞬間、「あっこれ知ってる」と思った。何故ならその頃、母がパソコンで文章を打つたび横に行って「「A」と打つと「あ」になるんだ」とか「このアルファベットの並びで文字を打てるんだ」とか考えながらいつも見ていたからだ。そして毎日見ていることで、文字の打ちかたも覚えてしまっていたのだ。
文字を打つ方法をすでに知っていることで勇気が出た僕は、人差し指をそっと差し出し、ゆっくりと打ち始めた。「意外と力がいるんだな」と思った。「う」はここだなとか、「ち」はこれだなとか確認しながら必死だったのでゆっくりではあったけれど、だからこそとても正確に名前を打ち込むことができた。「僕は文字を分かってるんだ!」と伝えたい気持ちもあったので本当に必死だった。そして僕は生まれて初めて言葉を発した。「UCHIDAHAKUTO」と。
打っている最中は集中していて、言葉を打っているという感覚はなかった。でも横にいる母がとても驚いていて感激しているのを見て、「ああこれは凄いことなんだ」と、「僕は生まれて初めて自分の名前を発することができたんだ」と実感した。僕は興奮しすぎたのか、何故か混乱する気持ちと、何よりあまりの嬉しさで思わず研究室の中を走りまわった。
母は感激して「凄い!凄い!」と歓喜で叫んでいた。
この日の出来事をきっかけに、僕の人生は変わった。僕は毎日欠かさず打つ練習をして、何年もかけ、単語から二語文へ、そして長い文章へと徐々に打てるようになっていったのだ。
「言葉」とは、僕にとってこの世界へと繋げてくれた扉だ。僕の中に溜まっていた、ずっと降り積もっていた思いたちは解放され、光が差し込む扉から待ってたとばかりにどんどん飛び出していった。心の中で静かに眠っていた思いが外に飛び出したその瞬間、生きた言葉となり文章となって人に伝わり始めたのだ。言葉がなかったら、僕の思いはずっと心に溜まったままで行き場を失い彷徨っていただろう。言葉のおかげで僕は僕自身を解放でき、世界と繋がりはじめることができたのだ。