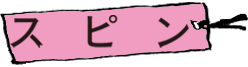『自閉症のぼくは小説家』 第4回「お疲れさまのスープ」
内田博仁(うちだ・はくと)
2025.09.19

連載第4回 お疲れさまのスープ
僕の朝
僕の朝は灰色の世界から始まる。夢と現実の区別が曖昧でぼんやりしている灰色の世界。そんな曖昧な世界をいきなり打ち破るように父が電気を付け、カーテンを開ける。僕は眩しさに顔をしかめ寝返りを打つ。こんな風に僕の朝は始まる。
僕は学校に行くのにとてもエネルギーがいる。なのでまず朝なかなか起きない。
父が「はくと起きるよー!」と何度も声をかける。僕は起きなければと思うのだが、なかなか身体が動かない。
起きたい、起きなきゃとは強く思っているのだ。でも身体が本当に動かないのだ。
指令が伝わってないというか、動線が切れている感覚というか。
父の声はだんだん強く大きくなる。
「はくと遅れるよー!」
分かってる。僕だって起きたいんだ。でも動けないんだ。僕は朝からイライラする。
父はとうとう僕の身体を力ずくで起こそうとする。母が「自分で起き上がらせて。力ずくは止めて」と言う。僕は母と父に申し訳ないと毎朝思う。二人とも朝からぐったりしてしまうからだ。
そこから着替えまで、一つ一つ嘘みたいに時間がかかるのだ。
まず朝食の席に座るのが大変だ。父がソファに行こうとする僕を制して、母が僕を落ち着かせるためにまず水を飲ませる。僕はそこでやっと切り替わって、朝食の席に座り食べることができるのだ。
一番時間がかかるのが、最後玄関へ行くまで。
「はくと時間だよ! 行くよ!」
と言われて腰が上がるまで最低でも5回、いや時には10回は母に叫ばせてしまうのだ。
最大の難関
僕は毎日スクールバスで通学している。自宅の近くにバスポイントがあり、8時36分が到着時間だ。いつもギリギリになるので、母は「これは、走らなきゃ」と言って二人でバス停まで走る。
しかし最大の難関はそこからバスに乗るまでだ。バスが来た瞬間、僕の身体はまた固まりはじめる。脂汗も出てくる。手や足がガタガタ震える。
乗れない…どうしても動かない…乗れない。
時間が決まっているので、バスはいつまでも待ってはくれない。
僕は焦る。
さらに震える。
もう乗れないかもしれない。
介助の方や母が「いいよゆっくりでいいよ」と言う。
僕には効果的な言葉だ。ここでもし「早く!」なんて言われたら僕の身体は彫刻のように固まってしまうだろう。
動け動け!
僕は身体にお願いする。少しずつじりじりと足が動く。一度足を乗せてまた後ずさりする。ふざけているわけではないのだ。
僕は乗りたい。学校まで歩くのは嫌だし。
「少し乗れたね! あともう少し!」
と皆が声をかけてくれる。僕は最後のエネルギーをふり絞ってエイッと足を動かした。
いけた! 動いた!
僕は自分の席まで勢いよく歩いてやっと席に座った。
これが毎朝だ。本当に毎朝。普通の人から見たら信じがたい行動だろう。
でも重度の自閉症の人は思ったこと、したいと思ったこと、行動がどうしても出来ないのだ。
僕は本当に真剣に動こうと精一杯努力している。できないのは誰より自分が辛いのだ。
僕に必要なのは訓練だろう。動けるように毎日訓練すること。止めてしまったらそこで終わりだから。
それを分かって、先生も周りの支援の人もバス通学を勧めてくれるのだ。訓練で身体が少しずつ動かし方を覚えてきた気がする。
バスの中は低学年の子がおしゃべりをしたり、時に叫んだりと騒がしい。そんな中、僕はハンカチをこねこねといじりったり、時に車窓から見える桜の木を見たりしながら緊張感と不安を紛らわしている。学校に着いたらまた身体が固まってしまって降りるのに時間がかかるんだろうな、と思いながら憂鬱な気持ちで到着までの10分間を過ごすのだ。
僕の一番好きな時間
その反面、一日の中で一番好きな時間は食事の時間だ。特に時間の制限のない夕食の時間は、僕にとって幸せで安らぐ最高の時間だ。
僕は学校でたくさんの苦い経験をして帰ってくる。先生は一生懸命指導してくれるけれど、どうしても現実はできないことが多い。正直自信がなくなる時もあるし、そんな日は疲弊して心が冷えきってしまう。
自閉症の人は食べ方にこだわりがある人が多い。ちなみに僕は一つのものを集中して食べるのが好きだ。例えばカレーライスならまずルーを食べてからライスを食べる。お寿司ならまず上にあるネタを食べてから下の握りを食べる。
「一緒に食べたほうが美味しいのに」と母が匙にカレーとライスをのっけてよく一緒に食べるようにと提案してくれるが、やっぱりダメだった。どうしても別々に食べたいのだ。
だから母はまるでコース料理のように次はこれ、次はこれと一品ずつおかずやご飯を出してくれる。
この夕飯コースのトリが、具沢山の野菜スープだ。僕が一番この野菜スープが大好きなのを知っているからだ。
まず僕はスープから出汁の昆布を取り出し、左手に持つ(左手に何かを持つと安心するからだ)。そしてもの凄い集中力で、まず何度も何度もスープをすくう。
このスープが身体に入っていく感覚、野菜の旨味が喉に広がる心地よさ、スープの脂がキラキラしているのを見るのも楽しくて、次第に心が無になり集中しリラックスしていく。
スープが疲れた身体に、心に沁みわたる。冷たくなった心にじんわりと灯りがともっていくようなこの感覚。その感覚と幸福感に浸る時間の恍惚感。スープをすくう強さの調節や、位置の調節が上手くできないのでスープが四方にこぼれるけれど、母はこの夕食の時間こそが僕にとって自由で解放される時間なのだと分かっているからか、あまりとがめない。僕は調子に乗り、残った具を手づかみし始める。さすがに母は怒り「手はダメ。スプーンで」と注意する。
でも僕は隠れてまた具を手でぐちゃぐちゃさせ感触を楽しむ。この行為がいけないのはよく分かっている。でもこの感触、感覚遊びは、手をひらひらさせたりジャンプしたりするのと同じ、スティム(自己刺激行動)の一種で、興奮した心を落ち着かせてくれるのだ。
母はさすがにこの行動については毎回注意する。でも僕が本当に疲れている日は仕方なく黙認してくれる。この夕食の時間は色々と許される時間なのだ。
そして僕はこのスープを必ずおかわりする。お椀を指さしして「もう一杯」という合図をする。
「よく食べるね~」と驚きながらも嬉しそうな母。「偉いね!お代わりしてくれて嬉しいよ」と何回も褒めてくれる。僕はますます機嫌がよくなって横にいる母の顔を覗き込み笑う。「そんなにおいしい?」と母も笑いかえす。
僕が人と笑いあい共感しあうなんてなかなかできないことだ。僕だって人とこうやって共感することができるのだ。だいたいいつも三杯は飲むだろうか。このスープには、一日外の世界で頑張ってきた僕に対しての母の「お疲れさま」という愛情や労わりが込められているのだと思う。そして言葉はなくとも、母とのこの夕食時のやり取りは優しく温かい時間を作ってくれる。僕の心にたくさんの栄養を与えてくれるのだ。
僕の毎日はいい事ばかりではない。むしろ成長するための訓練に向き合う困難さ、大変さを実感、経験する日々だ。でもこのような幸福な時間がひと時でもあれば、日々を乗り切っていける。少なくとも僕はそのひと時のために日々の訓練ややるべきことに力一杯取り組んでいるのだ。