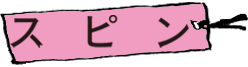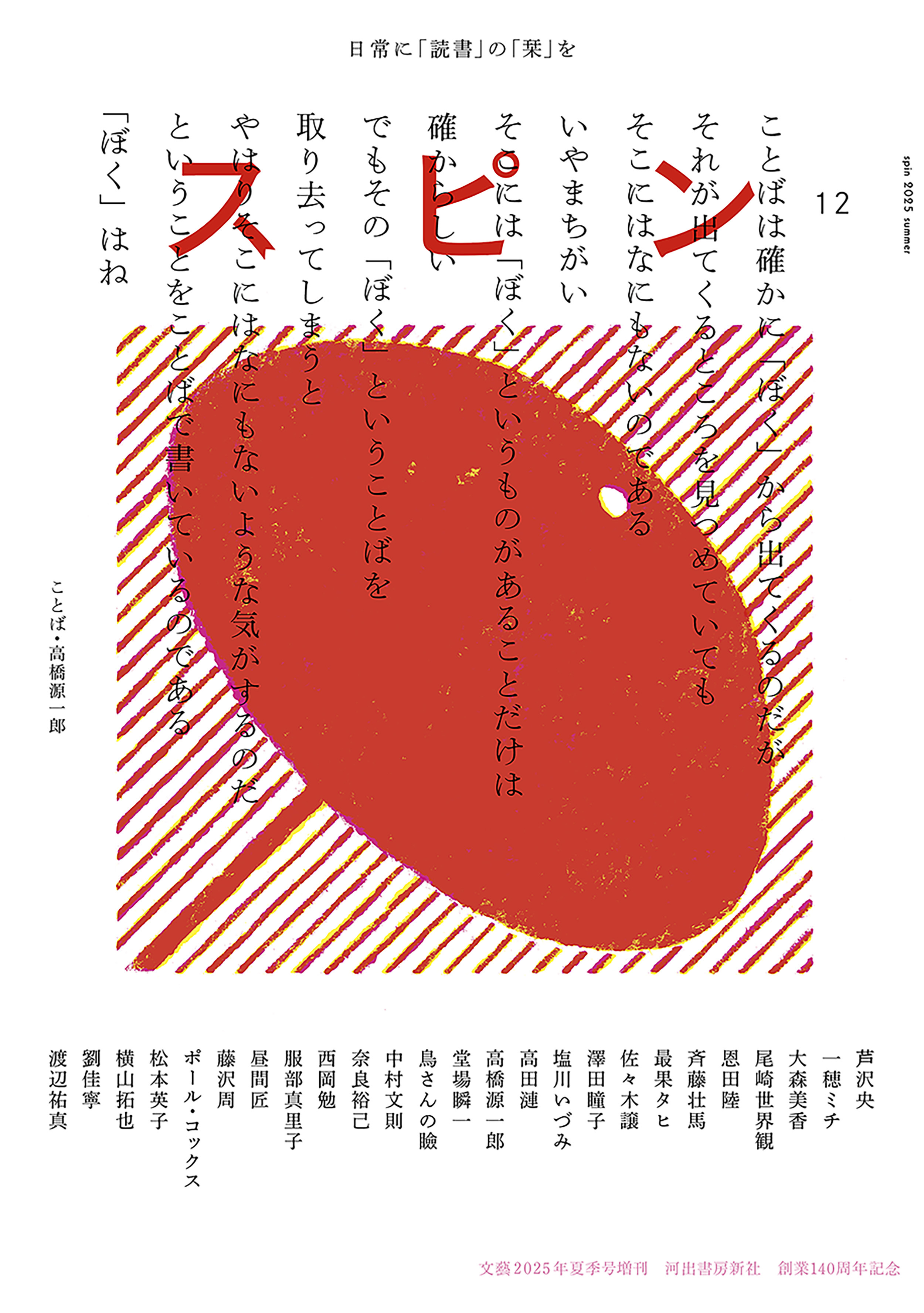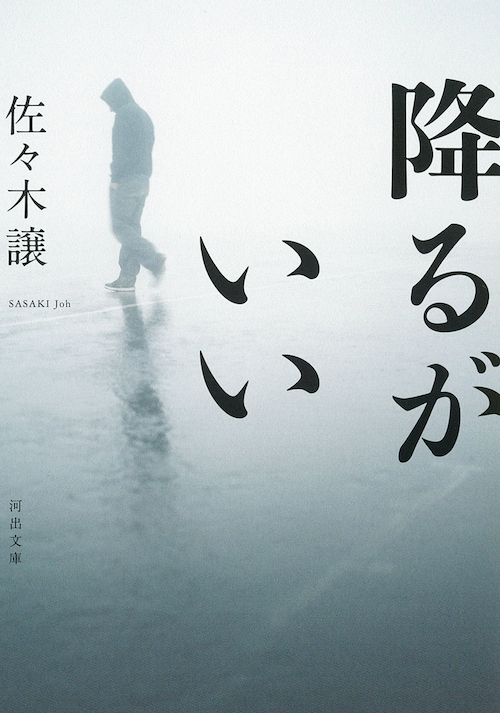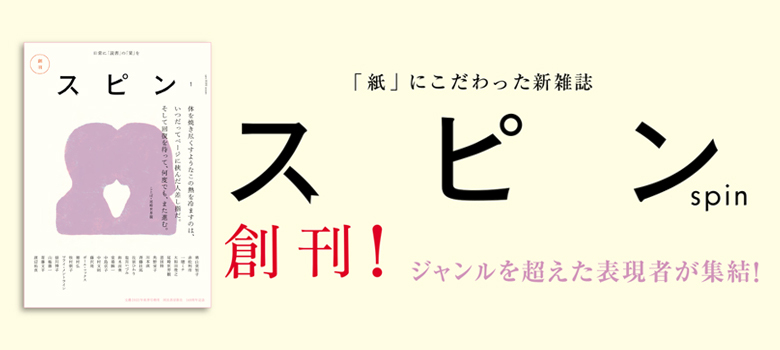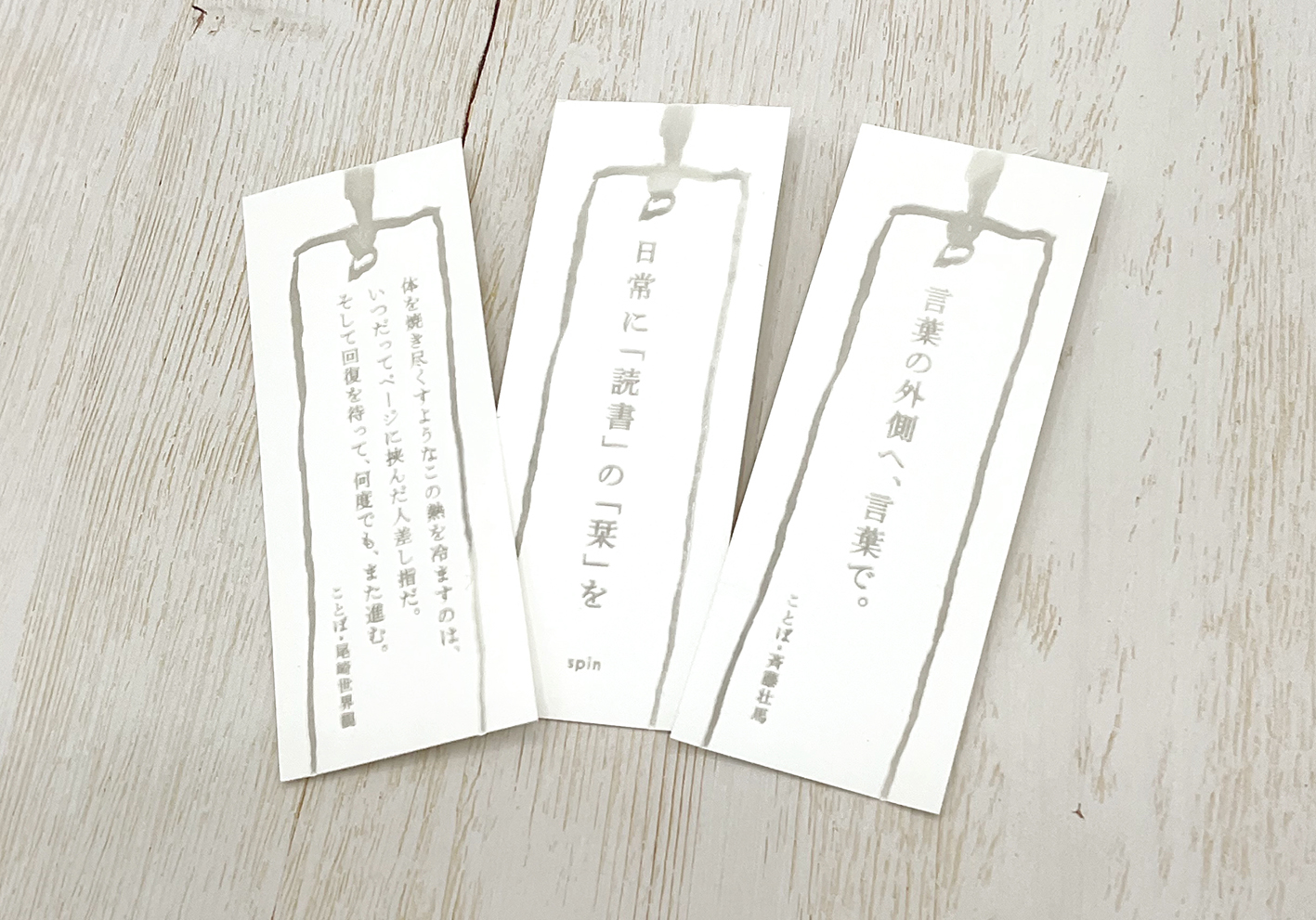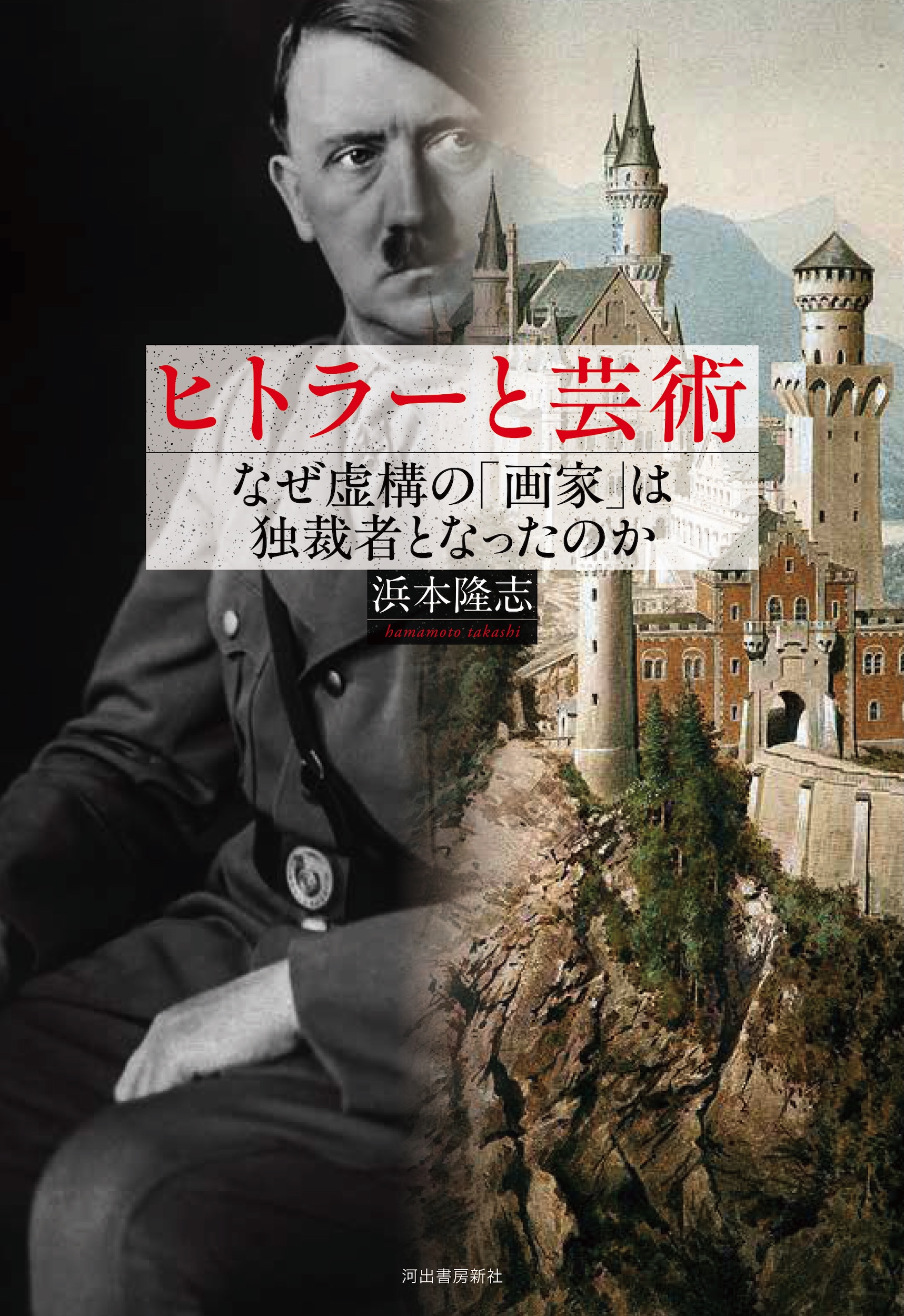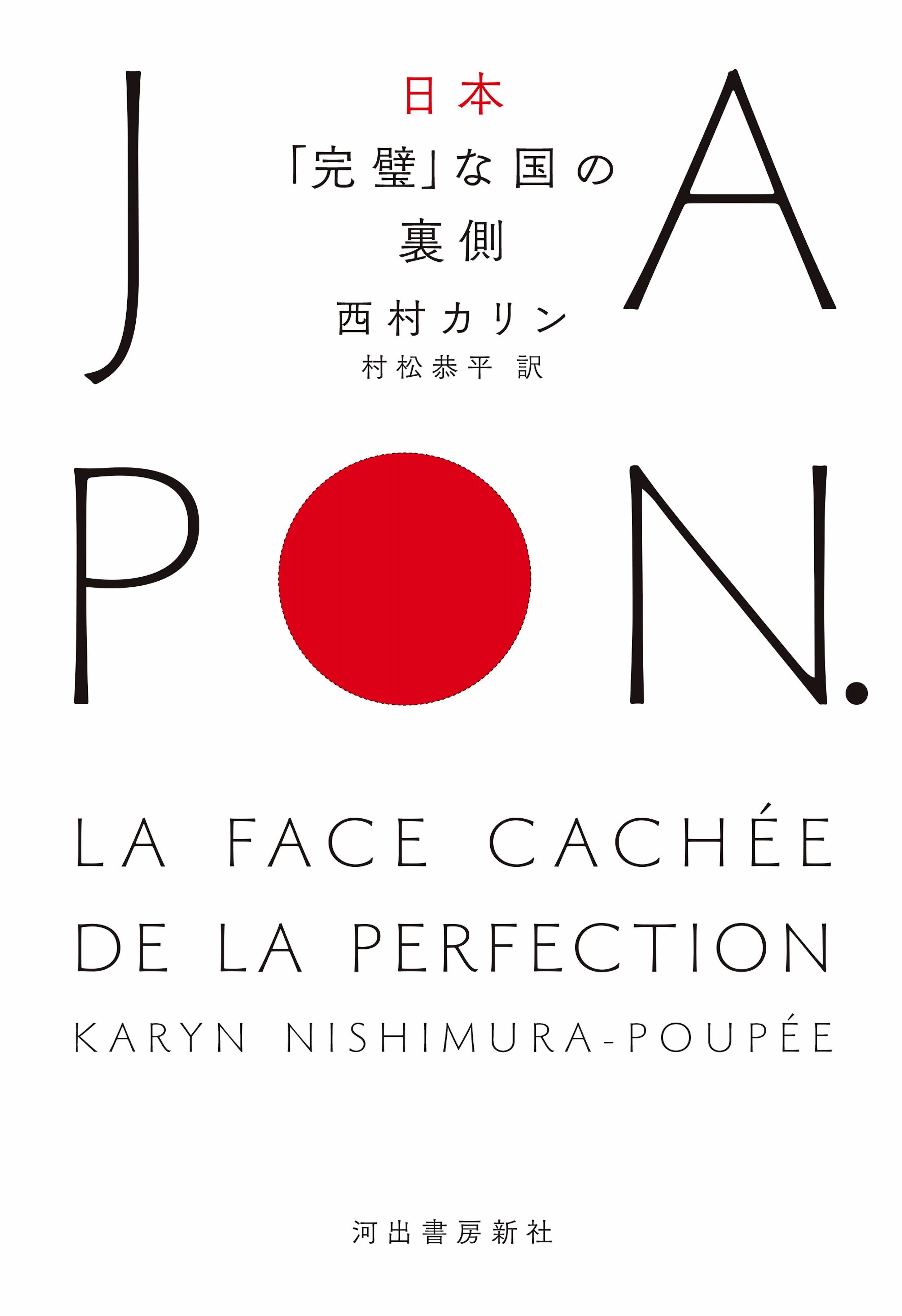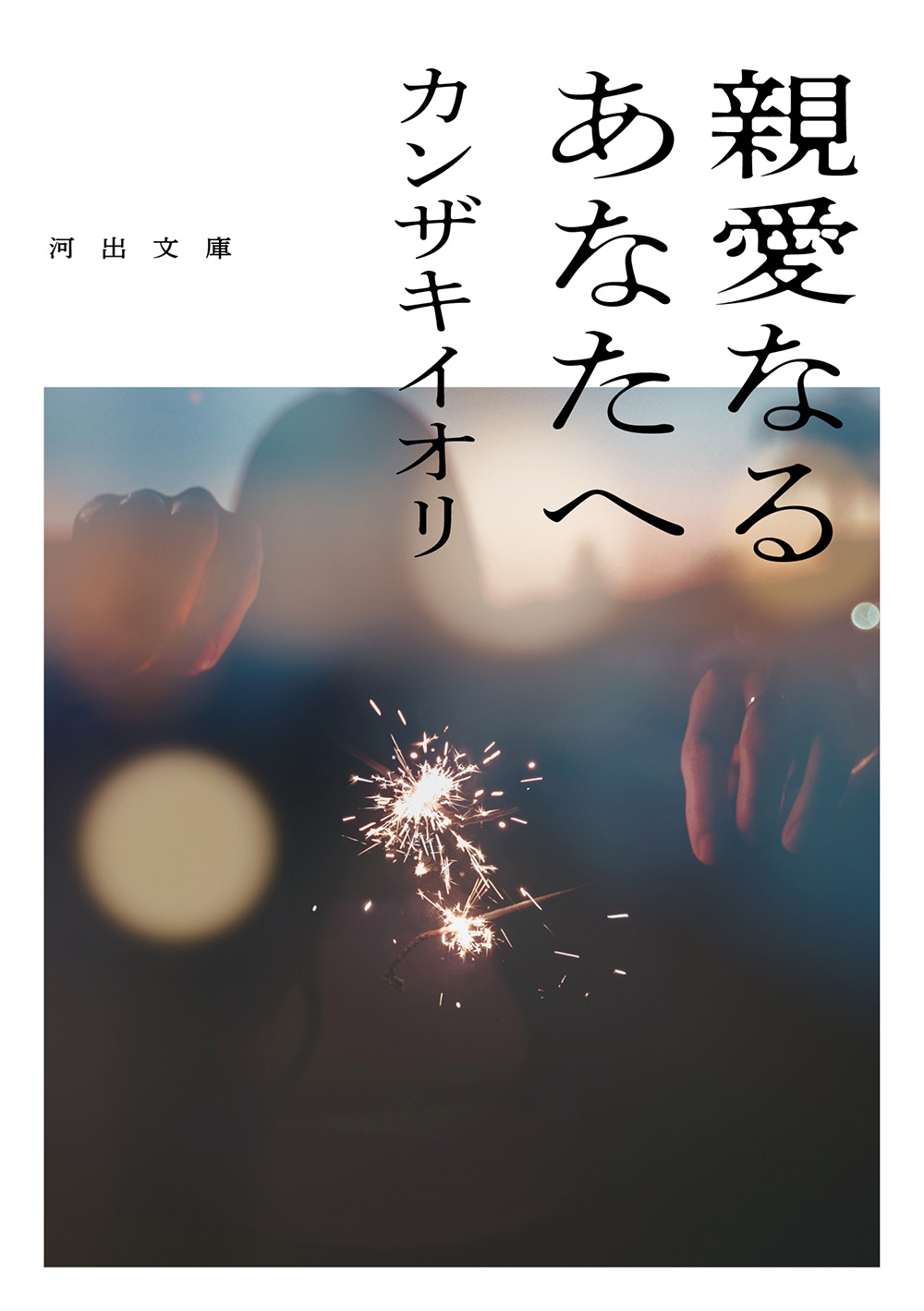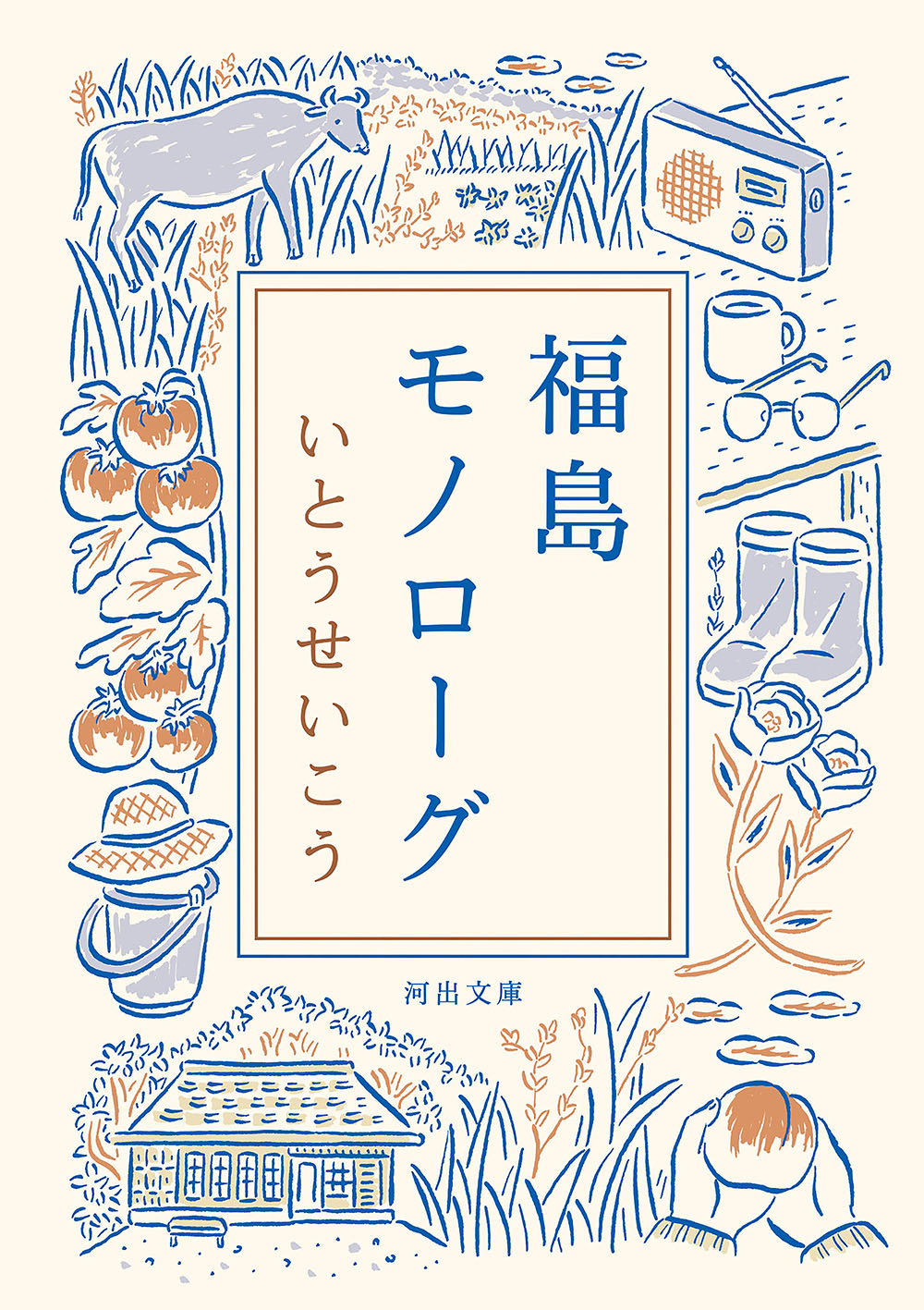路上の輝き 第3回
佐々木譲
2025.10.21

天気はいい。
気温も静岡県は最高が一八度との予報だった。寒いというほどの気温ではない。もっとも浜松の海岸に出れば、少し風はあるだろうが、小一時間砂浜を歩くことは苦にはならないだろう。
冬樹は、この日も黒っぽい身支度で部屋から出てきた。細身の黒いパンツ、黒いシャツに黒いジャケット。帽子は、彼のこの三十年ばかりのトレードマークとも言えるソフト・ハット。
昨日もそうであったが、旅行着というよりは、カジュアルすぎない街着だ。冬樹自身が持つ雰囲気のせいもあって、少しあらたまった席に出ても場違いには見えない服装とも言える。きょうは黒いハーフコートを手にしていた。大きめのナイロンタフタのショルダーバッグを肩にかけている。
冬樹が修平に言った。
「修さんとふたりで旅行をするのって、何年ぶりだろうかって考えてたよ」
修平は言った。
「奈津美ちゃんが広島でライブハウスを始めたときは、ふたりで行った。日帰りの遠出を別にすれば、あれが最初で最後だ」
「旅行は、ほとんどが三人だったのか」
「冬樹さんに会うために、ぼくと奈津美ちゃんとふたりで旅行したことは何度かあった」
「ニューヨークと、京都と、福岡もそうかな」
「福岡?」
冬樹は福岡にいた時期もある。でも修平は冬樹を福岡に訪ねたことはなかった。
「違うな」と、冬樹はとくに慌てた様子も見せずに言い直した。「福岡には、ミミがひとりで来てくれたんだ」
修平はすでに上野駅で買っておいた新幹線のチケットを冬樹に渡した。
東海道新幹線のひかり、グリーン車に並んで指定席を取ったのだ。富士山が見える側だ。冬樹には、窓側の席に掛けてもらうことになるだろう。自分は通路側だ。
「グリーン車」と冬樹が驚いた。
「身体に負担をかけないで行くよ」
「昨日も、あの小さな小屋の硬い椅子に耐えられたよ」
「二日続きでは、つらくなるんじゃないかと思って」
東京駅へと移動して、午後一時過ぎのひかりに乗った。
席に着いてから、冬樹が言った。
「昨日、その喫茶店を探してみた。見つからなかった」
「ぼくも探した」修平は確かめた。「店の名前は、風紋、で間違いなかったろうか」
「うん。砂丘に風が作る風紋」
「喫茶店なら、いまもあるなら見つからないはずはないな」
「さすがに五十年も経つと、なくなっていてもおかしくはないか。街も変わる」
「あいだにバブルの時代が挟まっているし」
「ぼくはあのあと、もう一回行っているんだ。バブルがはじける直前だ。最初に行ったときから十三年後だった」
修平は計算してみた。それはつまり、三十六年前のことになるのか?
「それは、朗読会だったっけ?」
「うん。そのときお客さんに、自分は十三年前は聴く側でこの店に来たことがあるんですと言ったら、お客さんが驚いていたな」
三十六年前というと、冬樹が演劇の世界から少し離れ始めた時期になるだろうか。
彼が自分の劇団を休止したのは、とある助成金を受けてニューヨークに派遣される直前だったけれど、それはむしろ演出家、劇作家として何か期するところがあっての「遊学」でありニューヨーク生活だったはずだ。じっさい帰国後に、劇団を再出発させた。
しかしその後は次々と冬樹にごたごたが降りかかり、演劇の世界では活動がしにくくなっていたようだった。より正確に言えば、演出家としての活動が少なくなっていた。
でも冬樹は三十代なかばから戯曲のほかに詩も書くようになっていた。傍から見るとなんとも消耗なトラブルが次々と出現しては彼を邪魔していたけれど、冬樹本人はさほど意に介している様子も見せずに、演劇以外のところでも表現活動を続けていた。三十六年前といえばそんな時期だ。
修平は言った。
「あった場所まで行ってみて、近所のひとにどうなったかを訊いてみるかい?」
「歩くだけでいい。その近辺にいい喫茶店があったら、入って休もう。追憶に耽る時間はあるだろう?」
「十分に。店のほうは見つからなかったけど、砂丘はある」
「そりゃあそうだろう。なくなるものじゃない」
「それが、あの大震災のあとに、防潮堤が作られたんだ。高さ十三メートル。それに砂をかぶせている。画像で見ると、風景は少し変わっていた」
「高さ十三メートルって、堤というよりは、それって城壁だね」
「それに、砂がずいぶん少なくなって、砂が飛び散らないように対策もしているんだそうだ。少しがっかりする風景になっているかもしれない」
「あの砂丘がなくなっている?」
「防潮堤の外側、海側の砂が減っている、という段階のようだけど」
「地球も、半世紀経てばそこそこ変わってしまうのか」
「川の流れとか、海岸線はそうなりやすいんだろうな」修平は昨夜のうちに調べておいたことをつけ加えた。「浜松の日没時刻は十六時四十二分。少し早めに浜松に着く。駅で時間を調節して、日没にちょうどいいバスに乗ろう。水平線に沈む夕陽を見て、浜松市内に戻る」
冬樹が笑ったので、修平は訊いた。
「おかしかった?」
「ミミを思い出した。あのときも、ミミは同じように言った」
たしかだ。あのときの奈津美の役割を、いま自分が引き受けた。
それは冬樹がまだ戯曲を書き出してはいないころだ。七十六年だったろう。修平は広告プロダクションに就職して、グラフィック・デザイナーとして働きだして二年目だったか。奈津美はアパレル企業の企画部にいて、専門学校時代からの希望どおりテキスタイル・デザイナーとして働いていた。
三人が会う機会は、修平や奈津美がまだ学生のときよりもさすがに減ってはいたが、修平自身は、待ち合わせなくても月蝕洞にひとりで寄る機会は増えていた。高田馬場は帰り道の途中だったし、約束はしていなくても顔を出して奈津美か冬樹がいれば儲けものだと、行くようになっていたのだ。週に一回は顔を出していたろう。もちろん月に一度は確実に、約束しあうこともなく店に集まった。
二月のある夜、約束して月蝕洞に行ったとき、冬樹も奈津美もすでに先に着いていた。
冬樹が言った。
「修さんは、『砂の女』って読んだ?」
その文庫本を手にしていた。
「うん」と、修平は応えた。「映画も観た」
「あの砂って、何だと思う?」
質問が唐突だったので、いくらか面食らった。
「映画を観ても、よくわからなかった。理不尽に自分を閉じ込めるものなんだから、現実の社会制度のことかとも思ったけど」
「ぼくはあの流動性とか不安定さを、時間の暗喩なのかと思った」
「主人公は、時間に閉じ込められた?」
「でも、主人公はあの砂丘で、現実から逃れられた。脱出もできるようになったのに、いつのまにか脱出する気持ちもなくなったんだ。だから、彼は閉じ込められたのでもない。砂が現実の社会に戻らない理由にはなった」
「じゃあ、あの砂は自由の暗喩だったのかな。ただ、豪雪地帯の生活だって似たようなものだから、盛岡出身者としては、そう言い切るのは無理があるかなとも思う」
冬樹が奈津美に訊いた。
「ミミは、読んだ?」
奈津美は首を振った。
「ううん。映画は、岸田今日子が出たんでしたっけ?」
「岸田今日子と岡田英次。ミミは、砂丘って観たことはあるの?」
「ない。鳥取の砂丘にも行ったことはない」
「ぼくもないんだ。砂丘とか砂漠を知っていたら、あれはわかるのかな。安部公房は、秋田の酒田の砂丘にインスピレーションをもらったらしい」
修平は言った。
「小説では、人食い砂のシーンが、短いシーンなのにけっこう衝撃だったな。『アラビアのロレンス』では、流砂の中に少年が埋もれていくところが怖かった。たぶん同じもののことだよね」
「ロレンスのほうはどうか知らないけど、『砂の女』の人食い砂のほうはフィクションだと思うな」
奈津美が修平に訊いた。
「修さんは、砂丘は?」
修平は答えた。
「小学校の修学旅行まで、海も砂浜も観たことがなかった」
冬樹が言った。
「鳥取も酒田も遠いな。だけど、砂丘を知らない人間には、あの作品は理解不能なのかもしれないと思うと、ちょっと癪だ」
「知りたいですか?」と奈津美が冬樹が訊いた。
「もっと手近にあるなら」
修平は不思議に思って訊いた。
「どうして急に『砂の女』が気になった?」
冬樹は、それまでにも親しいと言っていた舞台演出家の名を出した。
「彼が、『砂の女』みたいな芝居を書けないかと言ってきたんだ」
「みたいな、ってなんだい。『砂の女』を上演したいなら、あれを原作に脚本を書けばいい」
「だけど、ピンターの戯曲をこっそり訳して上演してしまうのとはわけが違う。安部公房に了解をもらい、原作料も支払わなきゃならない。そのたいへんさを考えると、砂に閉じ込められた男女、という設定の芝居をオリジナルで誰かに書いてもらいたいんだそうだ」
奈津美が言った。
「そのひと、自分で書くのがいいと思う」
冬樹は微笑して奈津美に言った。
「演出家と脚本家は、まったく別のタイプの人間だ。兼ねているひともいるけど、彼は戯曲は書けないんだ。苦手だ、と自分でも承知している」
「それで冬樹さんが、同じような設定で、オリジナルを書くって約束したんですか」
「約束はしていない。だけどとりあえず原作を読み返して、あらためてあの砂って何だろうと考えたんだ。で、思い至る。自分は砂も砂丘も知らないって」
「浜松の南に中田島砂丘っていうのもあるじゃないですか。浜松なら、見に行くのにも近いですよ」
「浜松に砂丘があるの?」
「アカウミガメの産卵でも有名なところ」
「ミミのように広島としょっちゅう行ったり来たりしていれば、浜松は東京圏か」
「東京から二時間かかりません」
「行ったことはあるの?」
「ううん。でも話に聞く。秋から春にかけては、太陽は水平線に沈むんだそうです」
修平は言った。
「砂丘はなくても、砂の海岸が続いているってだけで、見たいという気分になるな」
冬樹が言った。
「キャンバスに、水平線を一本引いただけのような風景じゃないの」
「砂。風紋。砂が崩れない程度のゆるやかな起伏。寄せては返す波。犬を散歩させているひと。絵になるものはありそうに思う」
「捕虫網を持った旅人もひとりいて。砂丘の始まるところにいる老人が、捕虫網を持った男に言う。行くな。すべてを捨てられる者だけが、この砂丘の先に進んでいい」
修平は感嘆して言った。
「砂丘を想像するだけで、そこまで場面ができてしまうんだ」
「いまのはどちらかと言えば、砂丘ではなく砂漠のイメージだな」
奈津美が言った。
「中田島砂丘に、三人で行きましょうか。わたしも行きたくなってきた」
冬樹が奈津美に確かめた。
「浜松に、ただその砂丘を見るためだけに行く?」
「砂丘から水平線に落ちる夕陽を観に行く。冬樹さんは、その文庫本だけを持って行く。余計な観光はしない、っていうのはどうです?」
「そんなに簡単な旅行になるかな」
「土曜日の昼過ぎに出れば、日の入りには間に合うでしょう。浜松の街でご飯を食べて、日曜日に帰ってくる」
冬樹は苦笑しながら言った。
「ミミは、そういうオーガナイズが得意だな。行きたくなってきている」
修平は言った。
「ぼくは予算次第だ。あまりおカネがない」
奈津美はもう決めたという口調で言った。
「浜松市内で、晩御飯を食べて、一泊するのでいいんですね」
冬樹が同意した。
「ぼくらが行けるような酒場とか、喫茶店も探してみよう。学生街もあるんだろうな。宿はどうする?」
「節約しましょう。民宿みたいなところがあれば、ひと部屋に三人。変なことをしないのであれば、わたし、一緒でいいです」
「変なことなんてしない。いままで何かあったか?」
「念のためです。約束」
「約束する」と、冬樹と修平は同時に言った。
奈津美は冬樹と修平の目をそれぞれ、本気ですねと言うように覗き込んでから言った。
「二月なんだから、潮風が冷たいと思う。しっかり防寒着を着て行きましょう」
それまでに、三人で一度、一泊の旅行をしていた。奈津美が就職したその年の夏で、尾瀬へのトレッキングだった。バス・ツアーを申込み、夜は尾瀬沼の山小屋の庭で語り合った。月蝕洞で集まることとは違った非日常感を、三人が楽しんだ。山小屋は混んでいたから、三人は奈津美をあいだに寝袋をくっつけて眠った。
新宿駅西口で待ち合わせたときのことを思い出した。バス・ツアーの申込みもすべて奈津美がやってくれたけれど、集合したときに彼女は修平と冬樹に言ったのだ。
「メンバーのみなさん。わたしに千円ずつ預けてください。二日間、共通にかかる費用はわたしがそこからまとめて支払います。足りなくなったらまた出してください」
冬樹が感嘆して言った。
「ミミは、こういうことに慣れているの?」
奈津美が得意そうに鼻をうごめかせた。
「合唱部で、マネージャーでした」
「ぼくに一番欠けてる能力が、そういうことだよ」
修平は言った。
「ひとり旅もしているのに」
「そのたびにどれだけ苦労して、どれだけ失敗してきたか」
奈津美が笑った。
浜松駅前発のバスを、中田島砂丘前の停留所で降りた。
砂丘への入口の前に大きな石が置かれ「中田島砂丘」と彫られている。前に来たとき、この石があったかどうか、修平には記憶がなかった。目に入らなかったのかもしれない。石の裏手に二十段ほどの石段がある。これも記憶があやふやだ。記憶では、バス停を降りて国道を渡るともう海岸林で、砂浜方向に遊歩道が延び、林を抜けるとそこはもういきなり、不規則な起伏を繰り返す砂丘ではなかったろうか。
いまは、前面には一見砂丘の斜面と見えるものが左右に広がっている。稜線は横に一直線だ。これが防潮堤なのだろう。石段の上からの目測でも、防潮堤の高さはやはり十二、三メートルぐらいある。
一級河川の陸地側から土堤を見ているようだ。堤全体を砂で埋めたというから、稜線と見える水平線は堤の天辺で、たぶんそこには歩道ができているのだろう。
石段の上から正面に向けて通路が延びていて、途中から上りの勾配の斜面となっていた。堤のてっぺんまで上れば、その向こう側に砂丘が残り、海があるのだろう。
防潮堤へ向けて、一直線の通路が伸びていた。砂丘へ向かういわばメイン・ストリートがそれなのだろう。左右に垣があって、その外と通路とを分けている。
通路は舗装されたり固められているわけではない。砂の道だ。防潮堤の上まで三百メートルくらいはあるだろうか。
この道以外にも、陸側の防風林のあいだを抜けて砂丘に出ることのできる遊歩道はいくつもあるのではないか。前に来たとき、案内図でそれを覚えた。
冬樹が言った。
「あのときとは、やっぱり違うな」
落胆したというよりは、困惑しているような表情だ。
修平は訊いた。
「砂の斜面を上るの、きついかな」
「ゆっくり休みながらでいいかな」
「必要になったら、手を引っ張る」
「前は、こんな道を歩いたっけ?」
「防潮堤を作ってから、整備したんじゃないのかな」
通路の左右の斜面には、少し植物が映えている。砂地でも生育できる海浜植物なのだろう。完全に砂だけの斜面ではない。かつてはほとんど砂しか目に入らない丘が広がっていたと思い込んでいたが、これは記憶が修正されたものかもしれない。砂浜はあまり広くなく、波打ち際へそこそこの勾配で砂丘が落ちていたのだ。
ありがたいことに、風はあまりなかった。でも、稜線の海側、砂浜ではそこそこ吹いているかもしれない。真冬だからこの太平洋側の海岸は快晴だ。わずかに水平線近くに雲が伸びているだけだ。吹きさらしの中に長い時間立たずにすむように、日没時間に合わせてここまでやってきたのだ。きれいな日没を見ることができそうだった。
冬樹は、修平に助けを求めることもなくゆっくりと砂の斜面を上り、防潮堤の上に立った。修平も並んだ。たしかに砂丘はやせているように見えた。あのときは、砂丘はもっと柔らかく豊かな砂の丘で、風と浸食とが作り出したその丘は、女性的と言ってもいいくらいになまめかしくも感じられたのだ。
砂浜も広くなっている。砂が消えている、というのはこの様子を言うのだろう。
ただ、ほぼ真横からの陽光だから、風紋も斜面の影も、けっしてひどく失望するようなものではなかった。
冬樹がゆっくりと周囲を見渡してから言った。
「あのとき来ておいて、よかったんだな」
修平はうなずいた。
「こういう海岸まで、ここまで変わってしまうんだものなあ」
「思い出を思い切り美化してやろうって気になっている。ぼくたちが見たのは、これじゃない」
「でも、けっきょく『砂の女』は書かなかったね」
「砂丘を見た体験は十分に生きた。あのとき浜松に来たことも、ひょんなことからあとのことにつながったし」冬樹は正面に顔を向けて言った。「波打ち際まで歩こう」
斜面を下るときに、冬樹は一瞬よろめいた。修平はすぐ手を出して支えた。上りの斜面がけっこうきつかったろうかと反省した。
「サンキュー」と冬樹が言った。「人食い砂だった」
波打ち際を歩き、また砂丘の中を歩いて防潮堤の上へと戻った。夕陽が西の水平線近くに落ちてきている。
初めて来たときは二月だったから、さすがに寒く、砂丘にいるあいだはみなあまり喋らなかった。
冬樹は、砂丘の景観や、砂と風が作り出す大地の形状に、修平以上に魅入られていたようだった。風紋に目を細め、その上を歩き、稜線や斜面をじっくりと眺めていた。砂丘の風下側にできているくぼみに入ってしゃがみこんだり、背伸びして周囲を見渡したりした。
やがて太陽が水平線に近づいていった。冬樹と奈津美は砂の上に座りこみ、無言で夕陽と向かい合った。修平は立ったまま携帯用透明水彩のパレットで、その日没の色を再現しようと懸命になった。
さすがに風と寒気のせいで、陽が完全に没するまで見ていることが厳しくなってきた。
奈津美がまず立ち上がり、ついで冬樹が腰を上げた。三人は何度も振り返りながら砂丘を出て、またバスで駅前まで戻ったのだった。三人とも、ずっと無言だった。
それからほぼ半世紀経ってのこの日も、修平と冬樹は太陽の下端が水平線にかかったところで、砂丘を後にした。
次は、あの喫茶店の面影を、浜松市街地で探すのだ。おおよその場所はわかっているから、そこに行ってみる。冬樹の気持ち次第で、もう少し歩くか、食事ができる店を探すことになる。たぶん駅の北口の飲食街で。
バス停まで戻ったところで、修平は冬樹に訊いた。
「疲れていないかな。砂浜は、思っていた以上に歩きにくかった」
冬樹が答えた。
「大丈夫。靴の中に砂がずいぶん入ってしまったけど」
けど。
まだ冬樹の言葉が続きそうな気がした。修平は冬樹を見つめた。
景観が変わってしまったという以上の問題は、ここにはいま奈津美がいないことだ。砂丘は、彼女の不在を強く意識させた。冬樹も同じことを思っただろうか。
冬樹は首を振った。
「いや。なんでもない」
あの日、三人は浜松駅に着くと、まず駅の観光案内所で市内の音楽喫茶とその場所を教えてもらった。係の女性が、浜松市街地の地図に青いサインペンで印をつけてくれた。地図に名の入っていない喫茶店については、名前も書き込んでくれた。
案内所のおすすめの喫茶店のうちから、バスやタクシーで行かねばならない店は除外した。浜松駅から歩いて行ける範囲で、店を絞りこんだ。
泊まる旅館は、浜松駅の南口にあった。商人宿と言ってよい造りと設備の旅館だ。一室に男女三人が泊まることも可能で、朝食がついてもビジネスホテルに泊まるよりはずっと安かった。修平たちはチェックインして八畳の和室にとりあえず荷物を置いてから、あらためて浜松駅の北口に出た。
駅前のバス・ターミナルから、中田島砂丘行きのバスに乗るのだ。砂丘から戻ってきた後、音楽を聴かせてくれる店に行く。
案内所の係の女性の話では、駅北口の左手に歓楽街というか、酒場の多いエリアがあるとのことだった。その中にも、案内所の女性がおすすめの、音楽を聞かせる店が一軒あった。ピアノ・バーふうの店で、でも歓談しながらお酒を飲めるという。
冬樹が目をつけたのは、広小路という駅前の目抜き通りから中通りに折れた場所にある店だ。よくライブがある店とのことだ。
中田島の砂丘から駅前に戻ってきて、地図を頼りに、その店を探した。もう日没から三十分以上経っていた。六時過ぎの、薄暮の時間帯だった。
広小路を歩いて、ここだろうと目星をつけた中通りに折れると、通りの雰囲気は半分は住宅街のような印象となった。夕暮れだったから、通りの照明が少ないせいで、余計にそう感じたのかもしれない。医院と、ピアノ教室の看板を出した建物があった。そのピアノ教室の外観は、リゾート地のレストランであってもおかしくはないような建物だ。
そのピアノ教室の隣にその店はあった。建物は、その通りの中ではやや無骨だ。かつては何かの事務所だったのかもしれない。
木製の扉の横に看板が出ている。
「珈琲と音楽 風紋」
扉の脇にはチラシが貼られていた。
「佐野久雄朗読会 十九時から」
入場料は三百円。それにワンドリンク三百円。
冬樹が店のドアの前で、奈津美に訊いた。「佐野久雄って、知っている?」
「ううん」と奈津美は答えた。
「朗読って、どういうことだ? 自分の詩を読むのかな。それとも他人の作品を朗読するのか」
冬樹は修平に目を向けたが、修平も佐野久雄という名前は知らない。
「誰かの作品の朗読会なら、たぶんその作家の名前を出すよね。中原中也作品朗読会とか。このひとは自分の作品を読むってことじゃないんだろうか」
「それが詩なのか、小説なのか。それとも戯曲を読むのかな」
その疑問を言い終えたところで、冬樹は店のドアを開けた。
「こんにちは」と彼は中に入りながら言った。
修平と奈津美も続いた。
店構えから想像していたよりも中は広かった。間口は三間くらい、奥行きは四間ほどあるだろうか。奥が小さなステージとなっていて、いくらか小ぶりのグランド・ピアノが置いてある。奥の壁には大型のスピーカー。
そのステージに向けて、テーブルと椅子が並べてあった。朗読会があるからその配置なのかもしれない。十人ほどの客がいた。
入ってすぐ右手がカウンタだ。カウンターの奥にいる中年男が店長で、カウンターの外にいる若い女性はウェイトレスなのだろう。
冬樹がカウンターに近づいて、ウェイトレスと見える女性に訊いた。
「旅行者なんですが、きょうはここでどんな朗読があるんですか?」
ウェイトレスらしき女性が店長らしき男に目を向けた。冬樹の言葉が聞こえていたらしき店長がカウンターの中を移動してきて、冬樹に答えた。
「佐野久雄さんの朗読会なんです。佐野久雄さんをご存じですか」
「すみません。存じ上げなくて。俳優さんでしょうか?」
「地元のアナウンサーさんです」
「浜松の?」
「静岡でした。定年してフリーになってからは、出身の浜松にお住みなんです。定期的に朗読会を開いています」
その声が聞こえたのだろう。ステージのすぐ前、左側の席にいた男性が冬樹に会釈した。初老といってよい年の男性だ。あの当時の言葉で言うならば、ロマンス・グレーという年代か。黒いタートルネックのスウェーターを着ていた。髪をていねいに横分けしている。
冬樹が店長に訊いた。
「きょうは何を朗読されるんです?」
店長は脇から小さめの紙を一枚取り出して冬樹に渡した。
修平がのぞきこもうとすると、店長は修平と奈津美にもその紙を渡してくれた。
きょうの朗読会のプログラムだった。
佐野久雄朗読会
Vn 中村由実
プログラム
宮澤賢治『春と修羅』より
屈折率
春と修羅
真空溶媒
永訣の朝
オホーツク挽歌 ほか
奈津美がうれしそうな声を上げた。
「『永訣の朝』が入ってる」
冬樹が店長に言った。
「三人、いいですか?」
「どうぞ。宮澤賢治がお好きなんですね」
奈津美が答えた。
「ええ。朗読で聴けるなんて」
「入場料が三百円。ドリンクをひとつ以上ご注文願います」
修平たちは、前から三列目の左寄りのテーブルに着いた。冬樹と修平はコーヒーを、真ん中の席に着いた奈津美はココアを注文して、朗読会が始まるまでを待った。
修平は小声で冬樹に訊いた。
「朗読会をよく聴きに行くの?」
「何回か」と冬樹が答えた。「詩人の朗読会を聴きに行ったことがある。子供のころの読み聞かせは別として」
奈津美が言った。
「好きなんですね」
「芝居と隣接している表現行為だから」
修平は言った。
「日本じゃ少ないよね。詩人も、詩集を出版して初めて表現と思っているところがある」
「たぶん日本の詩の、というか、文芸の文化が、いつからか肉声から離れてしまったんだ。漢詩を吟じる文化も消えてしまったし」
「演劇は盛んなのに」
「ヨーロッパや中東では、詩はまず詩人によって読まれて発表されるんだと聞くよ」
奈津美が訊いた。
「誰かが他人の作品を朗読することは、どうなんでしょう?」
「歌好きが、誰かの作った曲をカバーする。同じことだ。表現行為だ。ミミがメリー・ホプキンを歌うみたいに」
「あれを表現行為と思ったことはなかった。趣味」
「商業的ではないってだけだ」
注文したドリンクが来た。客も次第に増えてきている。修平がコーヒーを飲み終えたころには、店は三十人ほどの客で埋まった。若い客は少なく、年配客が大半だった。それも半分は女性だ。
やがてステージの上に男女が立った。さっき会釈してきた初老の男性、佐野久雄と、ヴァイオリンを手にした三十代と見える女性だ。彼女がプログラムにある中村由実か。黒いパンツスーツ姿だった。
控えめな拍手があって、佐野久雄があいさつした。
「ようこそ、今宵の朗読会へ。佐野久雄です」
いかにもアナウンサーらしい声と発音だった。
「いつものように、ヴァイオリンは中村由実さん」
拍手があった。
「きょうは」と佐野久雄が続けた。「宮澤賢治の作品からいくつかを読もうと思います。三年前にも宮澤賢治を読みましたが、一部重なる作品があります」
佐野久雄が中村由実に目で合図した。中村由実がヴァイオリンを顎に当てて、弾き始めた。
曲名が何かはわからなかった。クラシックの名曲なのだろう。一分ほど弾いたところで、佐野久雄が朗読を始めた。
「『春と修羅』から、『屈折率』ほか。
七つ森のこつちのひとつが
水の中よりもっと明るく……」
中村由実のヴァイオリンの音が消えていった。
佐野久雄が一連を読むと、中村由実がまたヴァイオリンを弾いた。佐野久雄が一篇を読み終えると、中村由実は少し長めに演奏した。つまりこの朗読会は、中村由実のヴァイオリンの小さなライブでもあったのだった。彼女のヴァイオリンを目当てに来ている客も多いのだろう。
『永訣の朝』は最後に読まれた。全体では四十五分ほどの朗読会だった。
終わると拍手が起こり、佐野久雄と中村由実がていねいに頭を下げた。
奈津美は涙ぐんでいた。ハンカチを目に当てると、冬樹がからかった。
「大好きなんだね」
奈津美は照れ臭そうに乱暴な言葉で応えた。
「いいじゃないか」
その後は、佐野久雄たちと客とのあいだで歓談の時間となった。
佐野久雄が修平たちの席にもやってきた。
彼は冬樹に頭を下げて言った。
「初めての方ですね。どちらから?」
若い冬樹に対して、佐野久雄はじつに丁寧な口調だった。
「東京です」と冬樹が立ち上がって答えた。「店の外の案内を見て、聴かせていただきました」
「もしかして、お芝居をしている方ですか?」
冬樹の印象から、そう思えたのだろう。それも当然という雰囲気が、冬樹にはあった。
「違うんですが、無関係でもありません。戯曲の翻訳をしています」
「ではこういう朗読会も、かなりお聴きになっているんでしょうね。東京なら、朗読会はずいぶんあるでしょう」
「じつを言うと、あまり多くありません。でも佐野さんのこの会は素敵でした。ヴァイオリンとのコラボレーションもよかったですね」
「理解ある方に協力してもらっているので」
佐野久雄は修平と奈津美に会釈して、離れて言った。
それ以上店には長居しなかった。居心地が悪かったわけではないし、退屈だったのでもない。なんとなく三人で語り合いたくなっていたのだ。
店を出るときに、店長が言った。
「連絡先を教えていただければ、ライブのスケジュール、ご案内するようにしますよ」
冬樹は店のノートに自分の名前と住所を書いた。
店を出て、修平たちは駅に近い飲食街へと向かった。案内所で教えられて、見当をつけていた店がある。
その店の名前は覚えていない。英語の名だった。シティライトとか、ライムライトか、そのような名だったような気がする。少しカジュアルな店だと思わせる店名だった。
土曜日の夜ということもあって、けっこう混んでいた。修平たちは入口に近い丸テーブルの席に着いて、それぞれお酒と軽い食事を注文した。ハンバーグとか、ピザを取ったはずだ。そういう種類の店だった。店にはアップライト・ピアノが置いてあったけれど、とくに演奏はなかった。
奈津美が冬樹に訊いた。
「『砂の女』書けそうですか?」
「うん」冬樹はうなずいた。「砂丘を見て、そのあと朗読会を聴いたし」
「それも宮澤賢治を」と奈津美。
「そう、宮澤賢治の詩の朗読を聴いた。ちょっと刺激されているな」
冬樹が修平を見つめてきた。きみは何か感じているか、と訊いている。
修平は率直なところを言った。
「浜松で賢治を聴くのは意外だった」
「土地に合っていなかったかい?」
「そうじゃなくて。逆だな。あの聴き方は初体験で、とてもよかった。いくつかは、あの佐野さんの読み方のせいなんだろうか。これってこんな詩だったのか、と感じたものもあった」
「朗読は、読むひとによる作品の解釈だからな。あの企画はよかった。これまで佐野さんはどんなものを読んできたんだろうな」
奈津美が言った。
「冬樹さんも、詩を書いて自分で朗読したいと思っていないですか」
「けしかけるな。やらなきゃならないことは、ほかにもいろいろある」
注文したお酒が出てきた。奈津美は、ホットワイン。冬樹と修平はビールだった。乾杯して、すぐに二杯目を注文することになった。あの夜、店が賑やかだったこともあって、三人はかなり陽気に、大きな声で歓談したはずだ。
冬樹が途中で、修平に訊いた。
「前から不思議に思っているんだけど、修さんはそんなに絵を描くのが好きなのに、どうして美大はグラフィック・デザイン科を選んだの? 洋画専攻というのか、油絵専攻なのか、そっちじゃなくて」
修平は答えた。
「ぼくは一年浪人している。最初は岩手大学の教育学部、特設美術科を受けたんだ。美大で言えば、油絵科みたいなところを。岩手で、油絵の道に進もうとすれば、事実上岩手大学の特設美術科に入るしかなかった。でもそこは石膏デッサンの実技試験があるんだ」
「学科試験だけじゃなく?」
「美大と同じに」
そのときの体験を、冬樹たちに初めて話した。
「実技試験は、教育学部の体育館でいくつかのグループに別れて、石膏像を木炭デッサンするんだけど、ぼくは盛岡市内の高校じゃなかったから、そういう受験準備なんてまったくしていなかった。もちろん高校の美術部で、やったけども」
奈津美が訊いた。
「石膏像って、ミロのビーナスとかの?」
「ぼくらのグループの課題は、アグリッパだった。石膏像の名前。男性の頭の部分だ。ところがその実技試験で、ぼくの隣にいる受験生が、もう唖然とするくらいにうまい。ああ、このくらいの石膏デッサンを描けないと油絵をやりたいなんて考えてはだめだったんだと、その受験の日に知った。けっこう衝撃だった。案の定不合格。それで親に頼みこんで、東京で美大受験向けの予備校に通うことにした。そこでもう一回ショックを受けた」
冬樹が言った。
「東京の美大志望の連中のはちゃめちゃぶりにとか?」
「いいや。美大受験の予備校には、盛岡でかなわないと思ったレベルの浪人生がゴロゴロいる。自分はなんと世間知らずだったかと、落ち込んだ。でも東京の美大に行くこと自体には魅力を感じた。で、ぎりぎりのところで進路変更。油絵はやめる。美大のグラフィック・デザイン科を受けて、きちんと就職しようと思った」
「美術でも、そのくらいの年齢で技術の差は出るものなのか」
「高校を出るまでには、基礎的な訓練はすませていなきゃあならない。ぼくは遅すぎた。それからの訓練でも、なんとか生きられる場所を見つけるべきだと思った」
「ゴーギャンだったかゴッホだったか、お前は絵がへたくそだと言われて、だっておれはもう海に飛びこんでしまったんだ。いまさら泳ぐのが下手だと言われてもしょうがない、って言わなかったかい」
「さいわい、ぼくは海に飛び込む前に下手だと知った」
奈津美が言った。
「修さん、下手じゃないよ」
「六歳から描いていれば、高校を出るまでにはそういう指と目ができていたかもしれないけど、それが必要だ、という知識もなかった。でも、仕事にはできないけれども描くことは好きなんだ。だから描いている」
冬樹が奈津美を見た。
「ミミは、どうして音楽の道に進まなかった?」
「だって」と奈津美は苦笑しながら言った。「オルガン教室でオルガンを習ったくらいで、どうして音楽の道に行こうなんて思えます?」
「好きだろう?」
「好きなことが、プロとして食べられるレベルにはなれないことは知っている。というか、そんなことは考えたこともない」
「テキスタイル・デザイナーとしてやっていく?」
「うん。でもまだ、そっちでひとり立ちできるかどうかもわからないけど」
奈津美が少しだけ目を遠くに泳がせたように感じた。
「何か?」と冬樹が訊いた。
奈津美は言った。
「さっきのお店、よかったですね。ライブとか、朗読会とか、そういうものができる場所を持つのもいいかも」
「クリエーターに表現の場を提供することか」
「ええ。いままで、全然思ったことはなかったけど」
「あの店は悪くなかったな。企画もよかったのだろうけど」
修平は訊いた。
「冬樹さんは、夢は?」
「英語力をカネに換えること」
「言葉で何かをするんじゃなく?」
「翻訳も言葉だ。正直言うと、まだ自分の夢なんて何かはわからない。手を出していろいろトライアル中だ。だけど」
冬樹が真顔になった。
修平は冬樹を見つめた。奈津美も修平と同様だ。何を言おうとしている?
冬樹は言った。
「断念したものはある」
「それは」と修平が質問しようとしたとき、ウエイターがテーブルの横に立って訊いた。
「ビール、お代わりはいかがですか?」
修平は質問することをやめた。
三人が旅館に戻ったのは、十時をかなり回った時刻だった。布団は客が敷けというシステムの旅館だったから、自分たちで三組の布団を少しずつ空けて敷き、真ん中に奈津美を入れて眠った。
この日も、宿は浜松駅の南口に取っていた。全国チェーンのビジネス・ホテルで、修平は隣り合うシングル・ルームを二室予約していた。
中田島砂丘行きのバスに乗る前に、チェックインはすませてあった。
砂丘からホテルに戻ってきて、修平は冬樹に体調を訊いた。砂の上を歩いて疲れていないかを案じたのだ。
「十五分、休ませてくれないか」と冬樹は言った。「それから街に出よう」
やはり疲れたようだ。
「三十分後にしよう」と冬樹は逆に提案した。
けっきょく六時半にホテルを出て、前回と同様、浜松駅構内を抜けて北口に出るのだ。
駅前から延びる広小路という大通りを北に歩いた。
三百メートルも歩いたところで、冬樹があたりを見渡してから言った。
「風紋は、このあたりの中通りだった」
すでに東京の感覚で言うなら、駅前の繁華街の雰囲気ではなくなっている。市街地には違いないが、商業ビルやオフィスビルは少なく、たぶん集合住宅と見える外観の七、八階建てのビルが目立つ。それよりも低層のビルもあるし、駐車場となっている更地も多く見えた。ビルの密集地ではない。前回来たときはこのあたり、木造の建物も多かったから、街の様子はかなり様変わりしているのは確かだったが。再開発の途上、と表現できるのかもしれない街並みだ。
冬樹が、中通りへと右に折れた。
通りの様子を眺めながら、中通りを奥へと進んでゆくが、顔はいぶかしげだ。
「この道路、まるで面影がないな。建物が全然変わってしまっている」
集合住宅ふうの建物がぽつりぽつりと建つが、空き地や駐車場も目についた。ただし、個人住宅などはもう完全になくなっていると見えた。
記憶では、あのとき入った喫茶店の風紋は、この通りの北側にあったのではなかったか。たしか木造の建物だ。でも、いまそこはやはり駐車場となっている。
冬樹が、その駐車場に向かい合う歩道上で言った。
「たしか、風紋はそこにあった。二度行ったのだから、記憶は間違いじゃないと思う」
修平は言った。
「三人で来たときも、たしかにこのあたりだった。二度目が、三十六年前?」
「だいたいそのくらい前。三人で来たときから、十六年目くらいだと思う。八八年。十二年前にもこの店に来ましたってあいさつした」
「そのときは、戯曲ではなく、詩を読んだ?」
「最初の詩集を」
「『海浜植物』だね」
それはあの日の砂丘散策から発想されたという詩の連作集だった。
冬樹が言った。
「浜松という地名も、中田島砂丘という固有名詞も出てこないのだけと、読めばどこの何がモチーフかはわかる。だから、店長も呼んでくれたのだと思う」
「あのときの店長と一緒のひと?」
「そう、ぼくが芝居に関わるようになって、ずっと何かできないか気にしてくれていたんだそうだ。朗読劇をやらないかと提案してくれたこともあった。やっと実現したのが、ほぼ十二年後だ」
「忙しかったときに、よくやれたな」
八八年と言えば、冬樹がかなり多忙であったころだったろう。もちろん彼は、その当時も世間的に言うところのメジャーな表現者ではなかったし、マス・メディアへの露出もほとんどなかった。しかしそれでも、彼は関係する世界では同世代の中でも活躍が目立っていたひとりだったろう。そのことが同時に、あの中傷というか非難も呼び寄せることになったのだが。
修平は喫茶店・風紋のあった場所の並びに、喫茶店らしき看板が出ていることに気づいた。間口が三間ほどの細長い五階建てのビルの一階だ。ビルはまだ新しい。外壁に化粧タイルを貼った、いくらかお洒落なビルとも言える。
冬樹もその喫茶店が気になったらしく、そのビルの前へと歩き出した。修平も冬樹について、車の通行のない中通りを渡った。
やはり喫茶店だった。軒下に自立型の看板が出ている。
Café Coin de pensée
修平は冬樹に訊いた。
「フランス語だよね。どういう意味だい?」
「喫茶・思索コーナー」と言ってから、すぐに冬樹は言い直した。「ちがうな。オーナーはたぶん、もの思う場所、といったニュアンスでつけたか。思索の一端、というような意味にもなるかな」
「読み方は?」
「コワン・ドゥ・パンセ」
修平はそのフランス語の店名をもう一度見て言った。
「ロゴタイプがいいな。意味に合っている」
「ネーミング・センスもいい。入ろう」
店は、想像外に奥行きがあった。天井までの高さも、二階分ある。奥の壁には、修平が見たこともないスピーカーシステムが鎮座していた。真ん中の北欧デザインのエアコンとも言えるような銀色の曲線のオブジェは、たぶんウーファーの三段重ねだ。その左右では、赤と白のホーン型のスピーカーが大中小のセットで正面を向いていた。その巨大なスピーカーシステムの前は、フロアが一段低くなっていて、ひとり掛けの肘掛け椅子がみなスピーカーのほうを向いている。椅子にはすべてサイド・テーブルがついていいた。手前のフロアには右手にカウンターがあり、四人掛けのテーブル席がいくつかある。空いているテーブル席がふたつあった。左側の壁は造りつけのレコード棚だ。
修平も冬樹も、その内装に一瞬呆気に取られた思いだった。冬樹もたぶんこれほどのオーディオ再生装置を備えた店は初めてなのではないか。
かかっているのは、修平もわりあい耳にするピアノ・トリオの曲だ。ただ、ジャズに詳しいわけではないので、タイトルも演奏者の名もわからなかった。
若いウェイトレスが修平たちに目を向けてきた。
冬樹が言った。
「初めてなんです。ジャズのお店なんですね?」
ウェイトレスはうなずいた。
「ジャズとクラシックですが、平日はだいたいジャズです」
「ふたり、どの席でもいいのかな」
「前のほうは、音楽を聴くためのお席です。お連れの方とお話をしたいのであれば、こちら側の、空いた席にどうぞ」
修平たちは、入口のドアに近いテーブル席に向かい合って腰掛けた。
メニューを見ながら、冬樹が訊いた。
「晩飯はどうする予定なんだろう?」
修平もメニューに目を落としたまま答えた。
「食事の制限があるんじゃないの?」
「病院食みたいな、和風定食を食べておけば間違いはない」
「この店を出たら、ホテルに戻る途中で定食屋を探して食べよう」
「居酒屋みたいなところで、惣菜系のつまみを取るのでもいい」
「アルコールは飲めるんだっけ?」
「止められてはいないけど、全然おいしいとは思わなくなっている」
音楽を聴きにきた客の多くは、ポットでコーヒーを注文するらしい。ふたりとも、コーヒーはカップで頼み、さらに冬樹はシフォンケーキを頼んだ。修平はふだんはスイーツを食べないけれど、きょうは吹きさらしの砂丘を、砂に足を取られながら歩いた疲労感が少しがあった。メニューにバスクチーズケーキがあったのでこれを追加した。
コーヒーとケーキが出てきたときに、冬樹がウェイトレスに訊いた。
「むかしこの通りに風紋というライブハウスというか、喫茶店があったんです。その店はいつごろなくなったか、知っています?」
「お待ちください」とウェイトレスが答え、すぐに店長だという五十がらみの男と一緒に戻ってきた。「店長が知っていました」
店長は、口髭をはやし、白いシャツにチェックのベストを着た男だった。
「風紋のお客さんだったんですか?」
「ええ」と冬樹が答えた。「お客で行って、二度目はあの店で出演者側になった」
店長は冬樹の顔を見つめた。自分の知っている顔かどうか、確かめようとしたのかもしれない。
「音楽関係の方でしたか?」
「いいや。芝居のほうなんだけど、風紋で自作の詩の朗読会をしたことがある」
店長は冬樹に名刺をわたした。
「わたしもあのお店が好きで、よく行っていました」
「わたしは名刺を持っていないんです。堂内と言います。堂内冬樹」
店長は、冬樹の名を知らないようだった。彼はそれ以上冬樹に、仕事や活動分野を訊ねることなく言った。
「この店を作ったのも、風紋の影響です」
「作った?」
「ええ。うちはここでアパートを持っていたんですが、このビルに建て替えるときに、親爺に頼んで一、二階にこの店を造らせてもらった。もう十五年になるんですけどね」
「風紋がなくなったのは、いつごろでしょうか?」
「二十年近く前になるかな。店長さんが引退したあと、娘さんが後を継いだんですけど、何年かでやめてしまいましたね」
「いま駐車場になっているところですよね」
「ええ。建物自体がなくなったのは、十年ぐらい前かな」
「わたしが最初に来たときは四十年以上前ですけど、いいお店でしたね」
「誰かのライブのときでした?」
「朗読会があったときでした。フリーアナウンサーの佐野久雄さんと言ったかな」
「ああ、お名前は聞いています。風紋では長いこと続けられていたそうですね。童話や詩をよく読まれていたとか」
「二回目は、わたし自身が朗読をするために来たんです。自分の詩集から、作品を読んだんですが」
「風紋では、そうした朗読会とか、ライブもよく開かれていましたね」
店長は、四人か五人の名前を挙げた。修平の知らない名前ばかりだった。ミュージシャンなのだろうが、修平にはそれがどんなジャンルの人なのかもわからなかった。風紋でライブをするとなると、フォークとかポップスの人となるのだろうが、ジャズはありうるだろうか。奈津美であれば、全員の名を知っているのかもしれないが。あの店で当時ライブを実施していたほどのミュージシャンなのだから、若すぎて修平たちが知らないというわけでもないだろうが。
店長は、それ以上名を挙げることをやめた。冬樹も修平も反応しないので、ふたりがそうした文化にはまるで疎いのだと判断したようだ。
ウェイトレスが注文のコーヒーを運んできた。そこで店長はカウンターの中に戻っていった。
冬樹がコーヒーを口に運んだ。視線は奥のスピーカー・システムに向けられている。しかし、再生中のジャズを聴いているという様子でもなかった。
修平は自分もコーヒーを少し飲んでから言った。
「さすがに五十年近くも経てば、いろいろ変わるな。砂丘も、街も」
冬樹が修平に目を向けてきた。
「そうだな」
「そろそろ食事にするかい」
「うん。これを飲んだところで」
またしばらく沈黙があってから、冬樹が修平に訊いてきた。
「修さんは、三十代の終わりとか四十歳ぐらいというと、何をしていたんだっけ?」
それはつまり、冬樹がこの店で朗読会を開いた前後の時期ということになる。
「もう広告代理店に移って、ずいぶん経っていた。三十のときに、広告プロダクションを辞めたんだから」
「もうグラフィック・デザイナーではなくなっていたんだよね」
「もうひとまわり仕事の範囲が広がっていた。名刺には、クリエーティブ・ディレクターと肩書が書かれていた」
「結婚して何年目だった?」
「四十で、五年目だな」
修平は三十五歳のときに、会社の同僚の女性と結婚した。四歳年下のグラフィック・デザイナーだった。自分の周りの男たちを見ても、自分の結婚は遅いほうだった。
冬樹が言った。
「修さんの披露宴のあと、ぼくはミミとふたりで二次会をやった。バリ島に行ったのは、その新婚旅行でだった?」
「そう。仕事が忙しい時期だったから、五日間のバリ島。かみさんが、とても行きたがった」
「あの当時は、サラリーマンだと新婚旅行でもそのくらいしか休めなかったか」
「いまだにそうじゃないかな。むしろ外国旅行をする若いひとが少なくなっている印象がある」
「なのによく、ニューヨークまで来てくれたよね。あれはぼくが三十五だから、修さんも同じようなものか」
「ぼくは二歳若い。この歳になると、どうでもいいくらいの差だけれど」
「学年ではひとつだけだ。けっきょく何日いたんだっけ?」
「五泊したね」
「ふたりが来てくれて、毎日、楽しかった。毎日がお祭りだった」
「冬樹さんに、刺激的なものを山ほど見せてもらった」
「休み取るのに、苦労はしなかった?」
「あの時代、広告代理店にいると、ニューヨークに行くと言えば喜んでもらえる雰囲気があったんだ。勉強熱心、と思ってもらえた」
「あのときは、もう奥さんとはつきあっていた?」
「いいや」
再生中のジャズ曲が終わった。冬樹のカップも空いていた。店を出ることにした。
浜松駅へ向かう途中、飲食街で定食の食べられる食堂か居酒屋を探して入ることになるだろう。
居酒屋では、冬樹はあまり食欲がなかった。つまみをいくつか注文したけれど、ほとんど手をつけなかった。
「スイーツを食べたし」と冬樹は言った。「あれできょうのカロリーは足りた」
修平は少しだけ、日本酒を飲んだ。冬樹は、ノンアルコールのビールだ。
ホテルには八時過ぎに戻った。
エレベーターの中で修平は冬樹に訊いた。
「何か、手伝うことはあるかい?」
「いや」と冬樹は答えた。「大丈夫だ。明日は?」
「ゆっくりと、お昼の新幹線。ここの朝食は十時まで」
「薬を飲むのに、朝八時には食堂に行く」
「一緒に行こうか。八時前にノックする」
「ああ」
「何かあったら電話を」それから思いついた。「千春さんにも、電話したほうがいいかもしれない」
「そうだな」
自分の部屋に入ったところで、修平は奈津美に電話をかけた。
「いま浜松。食事をして、ホテルに戻ってきた」
奈津美が訊いた。
「浜松で、冬樹さんがピンポイントで行きたいところって、どこだったんです?」
「三人で行った中田島砂丘と、喫茶店の風紋」
「風紋!」奈津美は驚いた声を出した。「まだありました?」
「いいや。さすがになくなっていた。あった場所の近くで、ジャズをかけている豪華な喫茶店に入ったけど」
「正直に言えばわたし、風紋に行ったことで、ここでライブハウスをやることになったのかもしれない。あの夜に、あんな店を持ちたいと思った」
「冬樹さんは、その後も一度行ってるんだそうだ。詩の朗読で」
「いつごろです?」
「バブルがはじける前だと言っていた」
「ニューヨークから帰ってきてからですね」
「それから三年か四年後ってことになるのかな。芝居だけじゃなくて、やることが広がっていた時期」
「あの風紋でも朗読していたなんて。わたしの店でもやってくれたらよかったのに」奈津美は電話の向こうで笑った。「そのころは、まだこの店を開いていなかった」
「ふたりで店を訪ねたときに、奈津美ちゃんは冬樹さんに頼んでいた。やるってことになっていなかったっけ」
「とうとう実現しなかった。あのころは、冬樹さん、あまり書かなくなっていたでしょう?」
「東京では、大塚の喫茶店を会場にして、年に一度は朗読会を開いていた。ぼくらが一緒に行った時期は」
「だったらうちでもよかったのに」
「ライブハウスとしては立派過ぎるんで、朗読で使わせてもらうには気が引けたんじゃないかな。広島はやや遠いし」
「もしかして、お客も入らないから、って遠慮したとかですか」
「冬樹さんの気持ちは、どうだったかよくはわからないけども」
「ともあれ」と奈津美が話題を変えた。「冬樹さんは体調は大丈夫なんですね」
「元気に行けると思う」
「楽しみに待っています。予定より早く着くのも歓迎ですよ」
「というと?」
「明日広島に着いてもいい。名古屋とか京都に行くのは、帰りでもいいんじゃないですか」
「明日、訊いてみる。一応明日のホテルは予約しているんだけど、冬樹さん次第で変えてもいいよ」
「楽しみに待っています。とても」
「少し早いけれども、おやすみ」
通話を切って、時刻を確かめた。午後八時二十分だ。
自分の通常の就寝時刻は十時半だ。少し間がある。風呂に入った後、ビールを飲もうかと考えた。エレベーターの脇に、飲み物とつまみの自動販売機があった。
買っておくか。
修平はもう一度廊下へと出た。
(つづく)