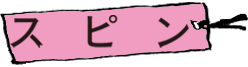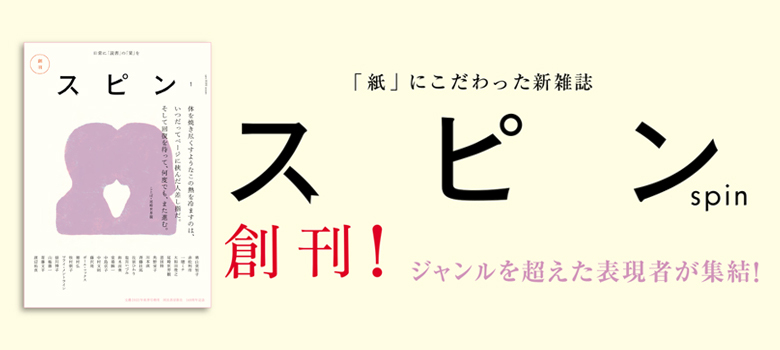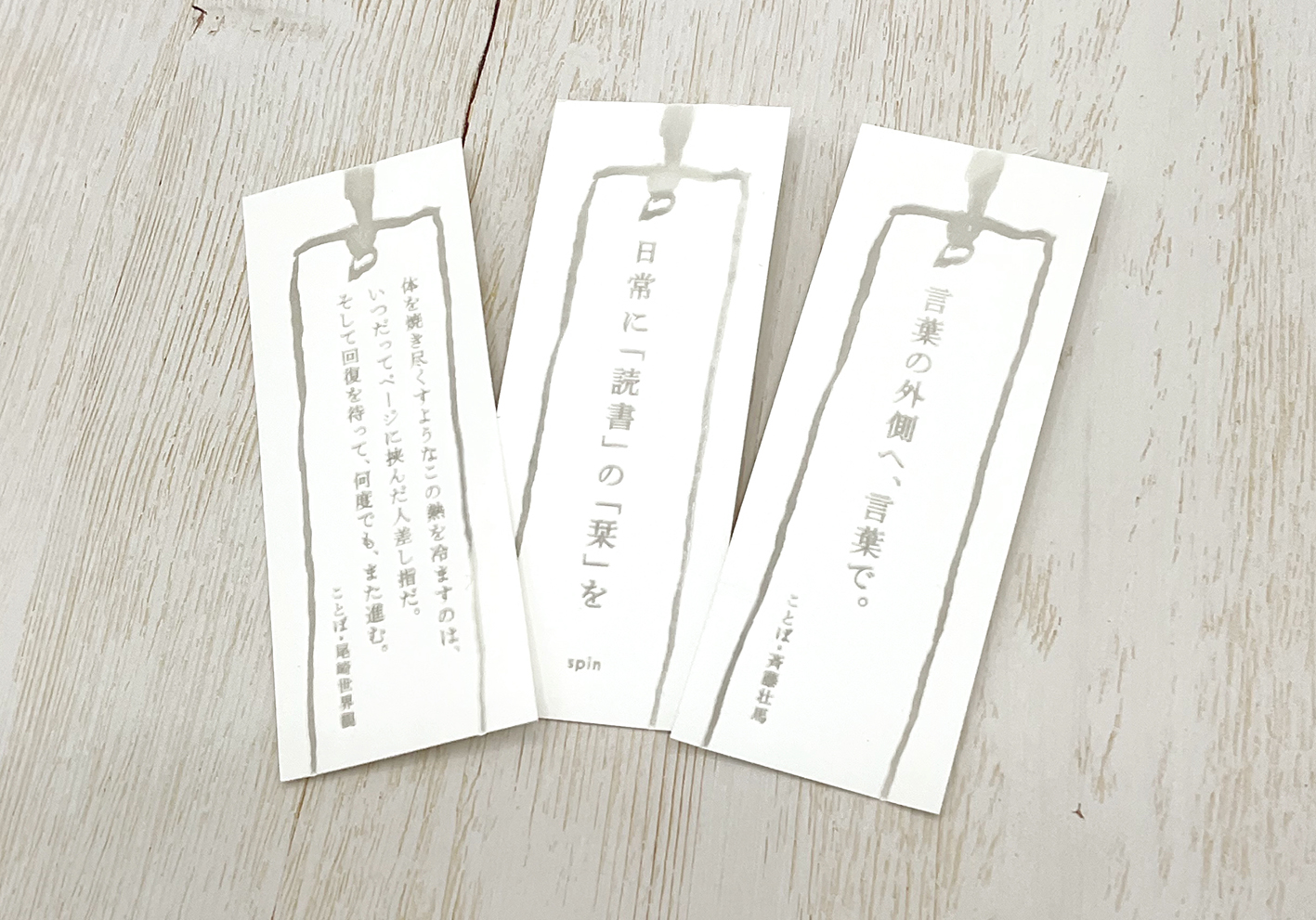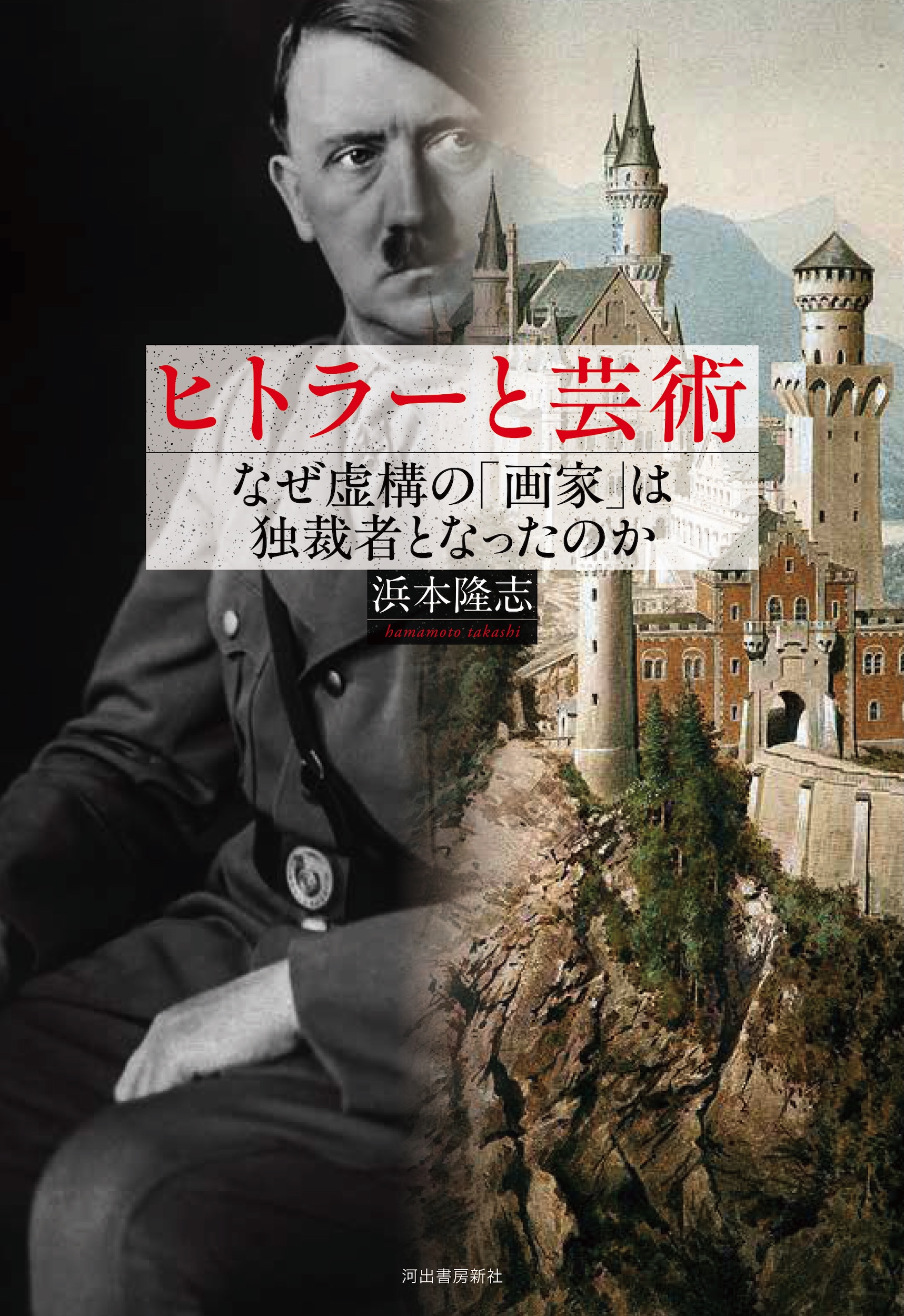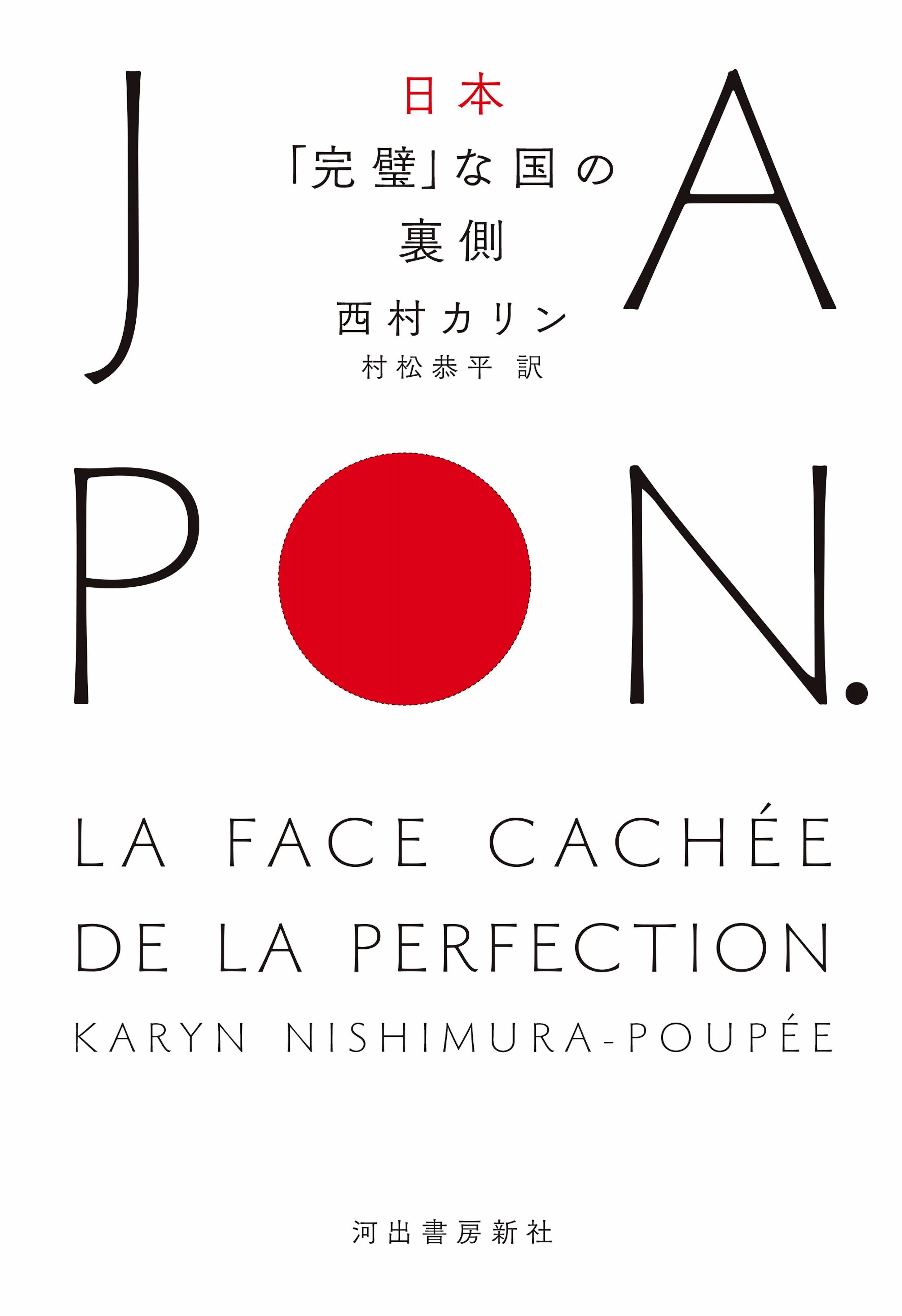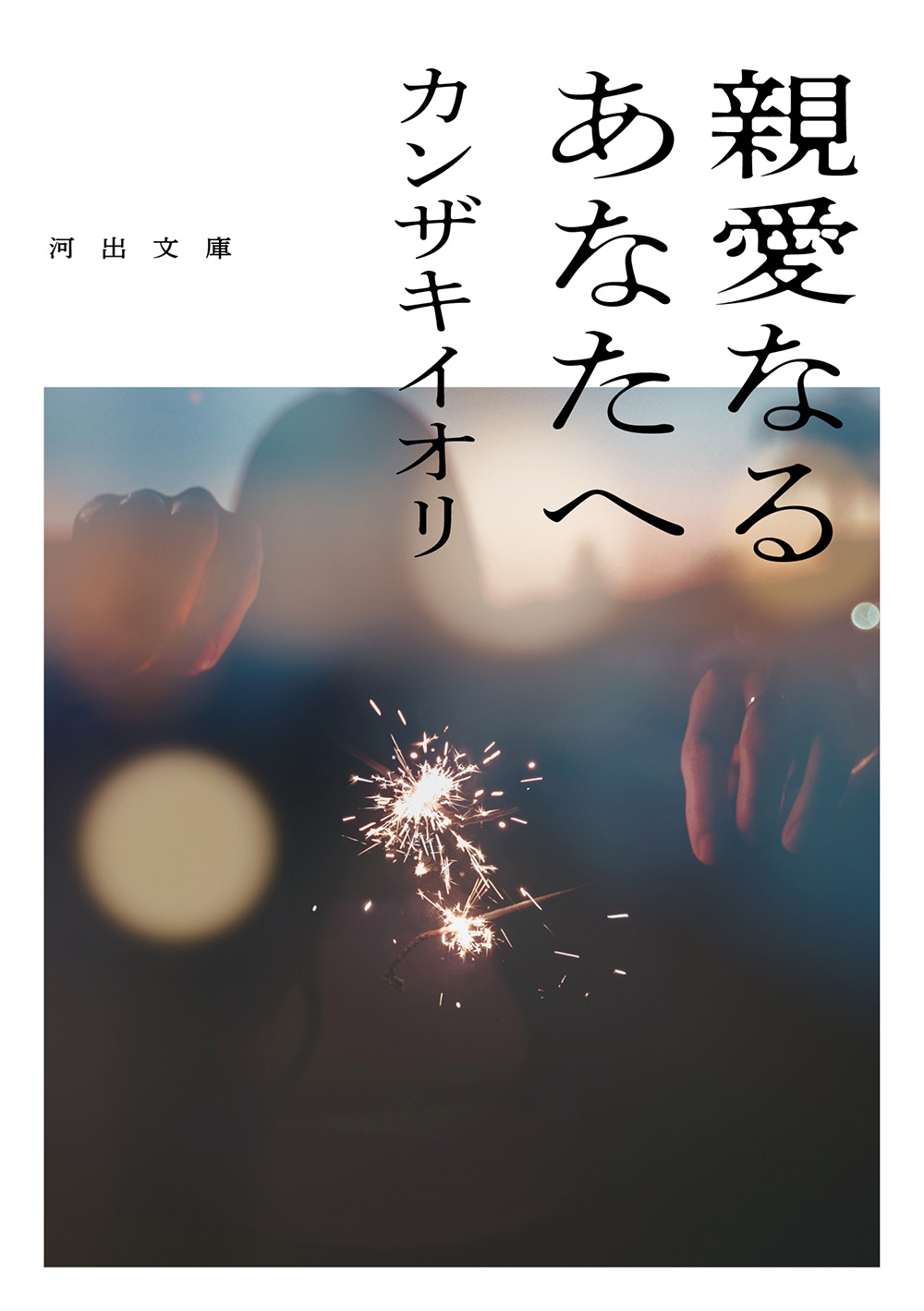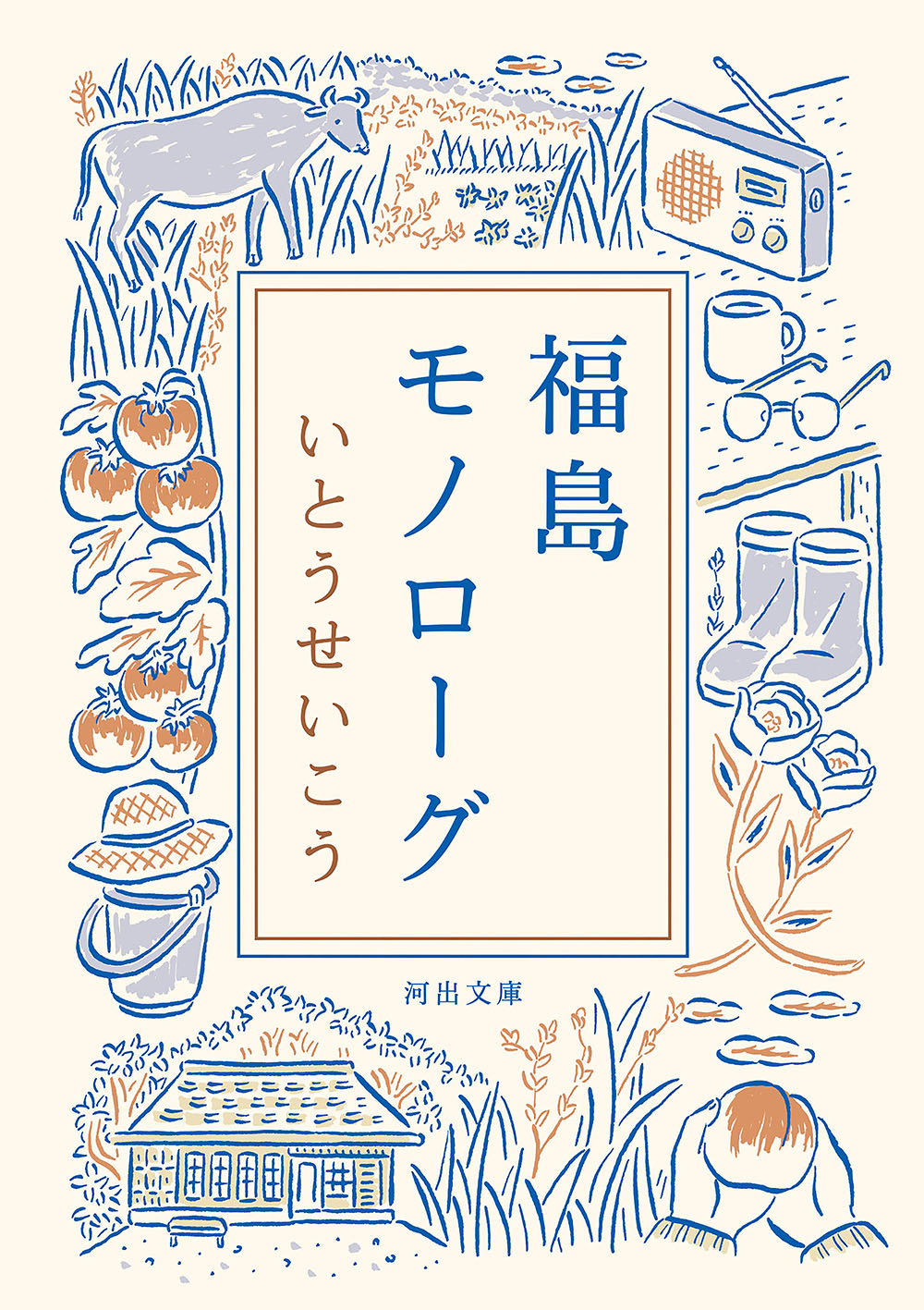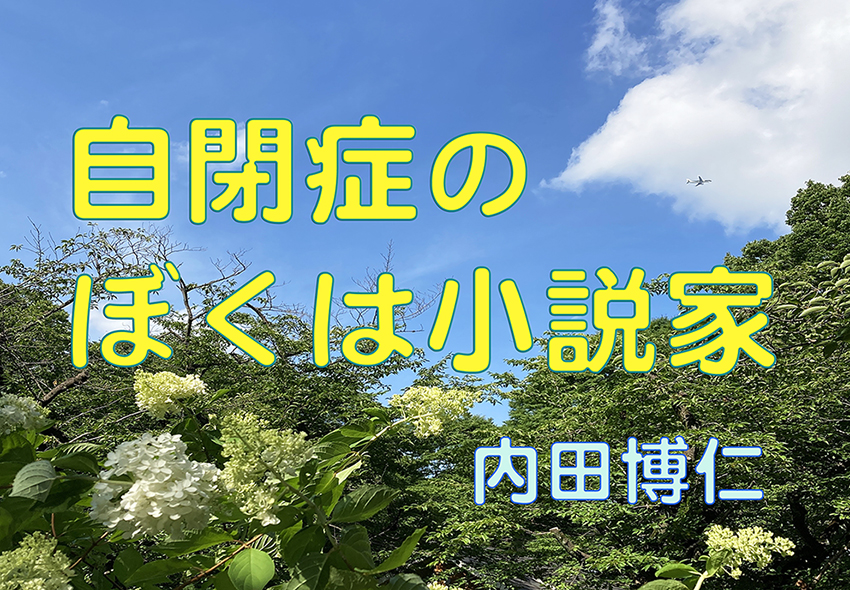
『自閉症のぼくは小説家』 第6回「詩が生まれた日」
内田博仁(うちだ・はくと)
2025.10.31
連載第6回 詩が生まれた日
「なんでこんなことができないの」
と何度言われたことだろう。
なんでと言われてもできないものはできないのだ。言われるたび僕はよく困ってしまったものだった。
「できない」経験は人の何倍もしてきた。お箸を使って食べることができない、積み木を指示どおりに並べることができない、着替えが一人でできない、椅子にずっと座って授業を受けることができない……あげたらキリがない。中でも普通の人にはできて自分にはできないことと言えば「話せない」ことだろう。
それでも幼少期の頃は「この子もいつか話せるようになるのでは」という希望をまだ周囲の人達も持っていたように思う。
そこで、タブレットで打つ訓練と同時に声で話せるようになる訓練も必要だと考えた母は、毎週車で1時間かけ、とある音楽教室に僕を通わせた。
そこでは先生がピアノを弾いて歌を歌い、それを真似して同じように歌うことで、声で言葉を発することを教えていた。
「ブンブンブンはちがとぶ」
と先生が歌う。
「さあはくとくんも歌ってごらん」
と先生が促す。
僕はその「ぶんぶんぶん」の部分を先生の口真似をして発声しようとする。でもできない。
「口の形をよく見て!」
と先生が言った。
僕は必死で先生の口を見た。唇が前に出ている。それと同じようにすればいいのだと思った。僕は唇を先生と同じように前に突き出してみようと頑張った。でもそれもできない。どうしても唇がそのように動かないのだ。
先生が見かねて「こうね。この形」と言いながらいきなり僕の唇を触ってきた。
「これがうーの口だよ」
先生に指でうーの口にされたまま僕はもう一度「ぶんぶんぶん」の部分を歌った。
「うーうーうー(ぶんぶんぶん)」と。
「できたねー!」と先生が大きな声で褒めてくれ、「ぶんぶんぶん」が少し言えるようになったと先生はノートに記録する。
僕は戸惑った。はたしてこの訓練は僕にとって大事なことなのだろうか。そんなに声で話せるようになることは大切なことなのだろうか。
僕は正直納得できなかった。
だいたい毎週必死になってできないことに向き合い、「自分はできない」と毎回心から自覚しなければならないことは、一言でいうと心が疲弊する。凄く落ち込む。そして全然楽しくない。確かに僕は声で話すことが全くできない。でもだからといって無理に話せるようにする必要があるのだろうか。
僕は次第に授業中やる気が起きなくて寝ころぶようになった。
「はくとくん起きなさい!」
と先生が抱きかかえて無理やり椅子に座らせようとしても、僕は全身で抵抗した。
今思えば一生懸命で優しい先生だったのに、悪かったと思う。でもどうしてももうこの訓練はやりたくなかったのだ。
「お母さん今日も授業になりませんでした」と先生が報告すると、母は毎回「申し訳ありませんでした」と平謝りしていた。僕みたいに授業中抵抗する子はその教室には他に誰もいなかったと思う。
「ちゃんとやらないとダメじゃない」
と母に毎回怒られたが、それでも僕は毎週のようにレッスンが始まるや否や、床に寝転がった。
ある日先生が
「はくとくん嫌だと思うならそう打ってくれる?」
と電子手帳のキーボードを僕の前に打つように示した(先生は僕が文字を打てることを知ってからは文字打ちにも取り組んでくれていた)。
僕は
「い、や」
と打った。
先生は悟ったような表情をし「はくとくんしばらく教室を休みましょうか」と母に提案した。
2年は通ったであろうその教室で、僕自身の意志で言えた言葉は、何度も声で言わされた「ぶんぶんぶん」ではなく「い、や」という二文字だった。
しかし何かができないことによって他の何かが、別の何かが生まれるということもある。
僕の場合、話せないことで習慣になったこと、育った能力それは「考える」ことだった。
僕のように重度自閉症で無発語のインド人の作家ティト・ムコパディアイも、ある詩の中で「僕は考える木として生まれた」と表現している。
僕たちは人と会話できない分いつも自問自答したり、物ごとについて考えている。きっと人の何倍も。だからこそ、こうして文章として表現しようという意欲も強くなったのかもしれない。
僕は療育センターにいた6歳くらいの頃、部屋の片隅で窓の外を見ながらいつも頭のなかで言葉遊びのようなものをしていた。
外に出せずに心に溜まっている言葉を自由に並びかえて、繋いでいく遊びだ。この遊びを日々続けていくうちに、気が付いたらそれは一つの詩のようになった。
僕がこうやって詩を作っていることを母や先生は知っていた(確か電子手帳で伝えていたのだと思う)。
ある時「それを完成させて塾主催のコンクールに応募してみない?」と先生が提案してくれた。僕はその提案が嬉しくて、何とか頭の中で完成した詩を文章で表現したいと思った。でも実際にやってみるとなかなか文章として、文字として出てこない。
そこで母が
「最初は何の言葉から始まるの?」
と僕の頭の中の言葉を引き出そうと聞いてきた。
僕は
「あ、い」
と打った。
その頃の僕はもうその日はそれで限界だった。
そして次の日も母は聞いた。
「あいの次は?」
僕は
「ぱ、わ(パワー)」
と打った。
しかしその日もそこで僕の打つエネルギーは限界だった。
そこで次の日は「その言葉を繋げたらどんな文章になるの?」と聞いてきた。
このように日々母がリードしてくれることで、少しずつ頭の中で眠らせていた言葉が日々表出していったのだ。
そして約1カ月かけてそれは出来上がった。僕が生まれて初めて書いた詩。「みんなだいすき」という詩だ。
「みんなだいすき」
あいやおだやかさが
おおきなえをえがく
ぱわーはおおきなやさしさをたすける
おおいうそはきぼうがいやしてくれる
たいようがてらすいえは
おおいあいをいやして
ふぉろーしてくれる
おそとにさがしにいった
うれしいらいおんさんが
たのしくさけんでる
たかいあいがぱわーをだす
おおいあいがさいこうのそらをえがいてくれる
いえをでてもあたたかい
たいようがあった
そとにもあいがあることをしった
この詩をコンクールに応募すると、後日、僕が賞を受賞したとの知らせを受けとった。
僕が人生で初めて賞を取った瞬間だった。話すことのできない、他にもできないことばかりだったその頃の僕にとって、この体験は人生を変えるほどの奇跡のような出来事だった。そしてこの受賞をきっかけに文学賞に毎年チャレンジするという意欲や行動力も生まれたのだ。
何かができないことは決して悪いことではない。このように代わりに違う何かを生まれさせてくれるのだから。
この詩も僕らの考えるという習慣がなかったら決して生まれなかっただろう。
障害のある人は特に、できないことがどうしても多い。でも大人に近づいてきた今、僕は改めて思うのだ。はたしてできないことは悪いことなのだろうか?と。できないことは無理にやらなくてもいいのではないかと。
それよりもむしろ好きだと思うもの、これならばできると思えるものに取り組んだほうが成長を感じられるし、何よりそのほうが幸せで心が日々豊かでいられるのではないだろうか。
僕は話せない代わりに、言葉を心に溜めこんでそれらを大切に温めてきた。出口を失った言葉たちは決して消えはしなかったのだ。
音楽教室では楽しく歌えなかった僕だが、高校生になった今は音楽クラブに入部するくらい歌や音楽が好きだ。あの頃何度も聴いた先生のピアノの音色と歌声だけは、僕の心の中に美しい記憶としてずっと残っていたのかもしれない。