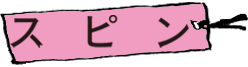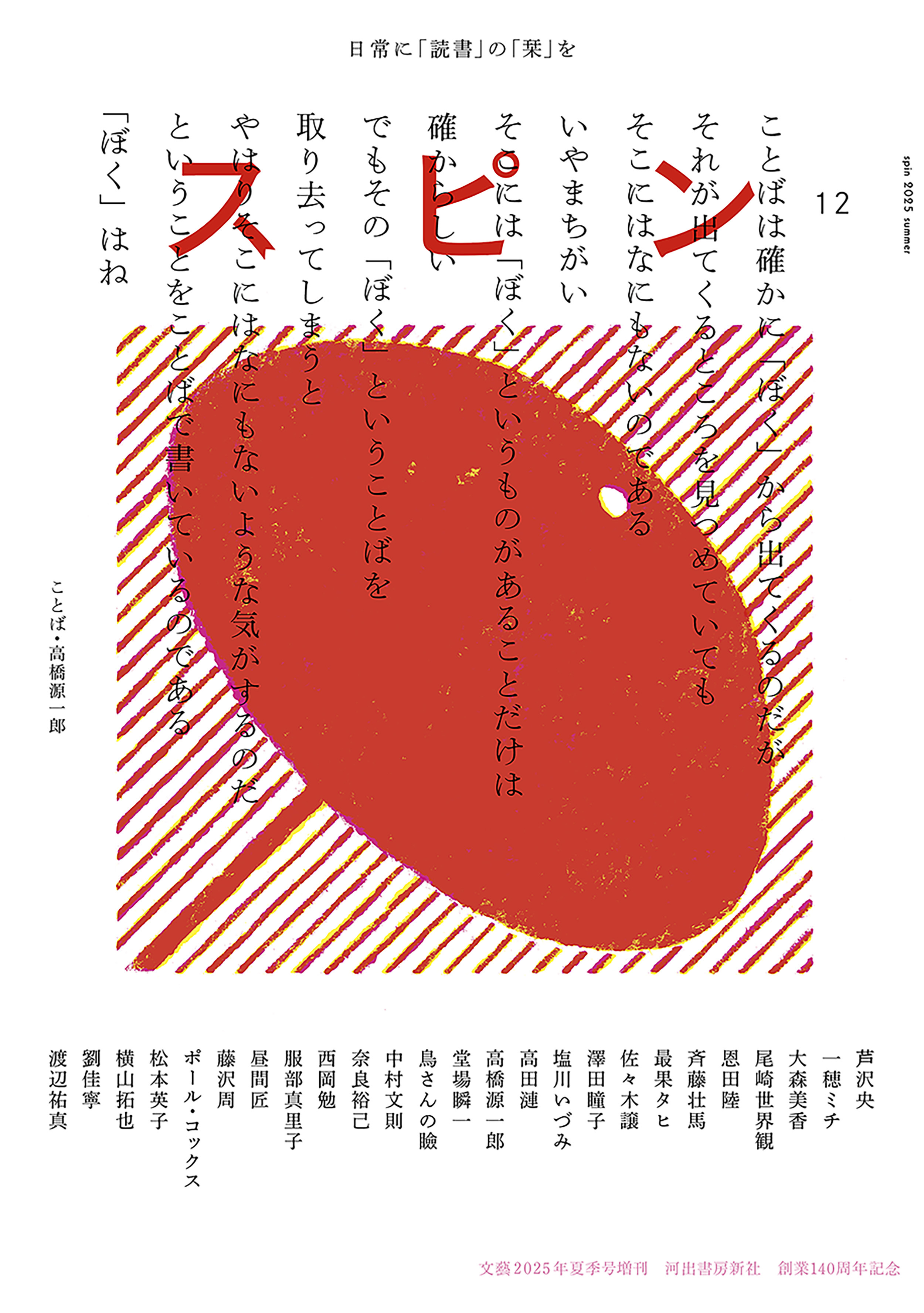路上の輝き 第4回
佐々木譲
2025.12.04

時間帯のせいか、そのビジネス・ホテルの食堂はけっこう混んでいた。サラリーマンふうの客が大半で、観光旅行のカップルとか家族連れなどはいない。
冬樹は修平の向かい側で、ビュッフェ形式の朝食をほとんど食べなかった。少しのサラダとヨーグルトとフルーツだけだ。食べ終わると、黒いポーチを開けて二種類の錠剤のシートを取り出し、水と一緒に飲んだ。
その様子を見つめている修平に、冬樹が言った。
「鎮痛剤と、制吐剤だ」
「せいとざい?」
「吐き気止め。消化酵素剤って説明されたな。鎮痛剤もまだ軽いものだ。旅行ができないような痛みが出ているわけじゃない」
うなずいてから、修平は言った。
「あのあと、奈津美ちゃんに電話した。いっそきょうのうちに広島に来たら、って言っていた。名古屋や京都は、帰りに寄ったらどうかと」
冬樹が微笑した。
「そう?」
「どうする?」
「順に行こう。名古屋は、ホテルも取ってあるんだろう?」
「うん。じゃあ、予定どおりに。きょうは、どんなところに」
「まず七ツ寺共同スタジオ」
冬樹が自作の芝居を上演した小劇場だ。修平も奈津美と一緒に観に行った。
「まだあるのか」
「調べたら、あった。あの小屋をもう一回見てみたい」
冬樹の書いた戯曲が東京以外で上演されるのは、それが最初だった。そこは商店か倉庫を改装したような建物で、客席は八十もあったのだろうか。
当時七ツ寺共同スタジオは、北村想がベースにしていることで東京の小劇場ファンなどには少し知られていた。だからそこでの公演は、俳優たちもスタッフも、うれしいことであったのだろう。冬樹たちは自分の劇団の、というか初演のときの最小限の俳優とスタッフを連れて名古屋に行ったのだった。
名古屋で演劇鑑賞団体の運営委員もやっている男が、劇団を立ち上げてようやく一年ほどの冬樹に、名古屋でも公演してくれないかと持ちかけてきたのだ。鑑賞団体が呼ぶような商業演劇とはべつに、小劇場のいわば「とがった」芝居を名古屋でも観たいのだ、との希望を持っていた。
その人物は名古屋の老舗菓子店の二代目で、東京で学生生活を送っているあいだに芝居好きになったとのことだった。三十代なかばという歳で、山浦、といった。
彼が上演を望んだのは、冬樹が自分の演劇ユニット『劇団・漂流列車』の旗揚げ公演のために書いた作品だ。『蜘蛛の棲む部屋』というタイトルだった。それ以前に、『砂の女』の脚本化の代わりに書いた冬樹自身のオリジナルを発展させたという作品だ。登場人物は男女ふたりだけ。物理的な密室は設定されないけれども、女は男を自分のアパートに誘いこみ、やがてひと月もたったころ、男が女に同棲の継続を望むようになると追い出すという話。女はナイトクラブの歌手で、何年もその生活を繰り返してきた。男は広告代理店の営業マンだ。
修平はもちろん奈津美と一緒に、初演を観に行った。それまでに劇作家としての実績もあったし、冬樹自身の演出によるこの公演は、小劇場関係者のあいだで少し評判にもなった。客数こそ厳しいものではあったにしてもだ。新宿三丁目の小さなフリースペースでの上演だった。
名古屋の山浦も、この上演を観ていたのだった。登場人物がふたりだけだし、舞台もごく簡素なセットでいい。俳優ふたりと、舞台監督、それに照明さんが前日に東京から行けば、さしてカネのかかる上演にはならない。なので声をかけてきたのだ。
「あれはうれしい話だった」と冬樹は言った。「自分の芝居がどの程度に評価されているのか、毎回不安でたまらないときに、名古屋でも上演してくれないかと持ちかけられたんだ。あ、自分の芝居は、身近な友達が面白がってくれてるだけじゃなかったと思えた」
冬樹は、高校時代とか、大学入学から芝居を始めたようなプロパー演劇人ではなかった。自分でも言っていたが、二十七歳で初めて戯曲を書いたような出遅れ気味の演劇人だった。友人の劇団の母屋を借りて自分で演出も手がけるようになったのは、三十歳になったばかりのころだ。
冬樹が『劇団・漂流列車』を結成したのは、その翌年か。自分の劇団といっても、中心メンバーとなる仲間がそう名乗ったというだけで、事務所も稽古場も持ったわけではなかった。もちろん法人組織でもない。メンバーは、主宰で演出家の冬樹のほかに、制作担当と俳優がふたりだった。だから芝居の上演の形態は、劇団の定期公演ではなく、いわゆるプロデュース公演というものだった。
なのに彼は自分で演出も受け持つようになってからすぐに、演劇界ではそこそこ伝統のある戯曲賞の候補となったらしい。
らしい、と思い起こすのは、候補作については事前にも事後にも発表されないからだった。後に冬樹は、選考委員のひとりから候補作であったことを教えられたと言っていた。その時期には冬樹は、新聞や芸能系雑誌の演劇担当記者などには注目されていたということだった。これに続く作品も好評で、最初に候補になったときから二年後には受賞してしまった。
映画や文学の世界とは違って、ごく地味な小さな世界での評価ではあったけれど、贈呈式とは別に芝居仲間が冬樹を盛大に祝ったようだ。
修平と奈津美はいつもの月蝕洞で、冬樹のためにわりあいいいスパークリング・ワインを用意して、受賞に乾杯した。
つまり名古屋での上演は、その受賞前のことだ。山浦は、まだ評価が定まっているとは言えぬ冬樹に声をかけてくれたのだ。
初演のときのチラシのイラストは、修平が描いた。
冬樹が修平に注文した。
「なまめかしくて、ひと目で女性とわかる蜘蛛を描いてもらえるかい。リアリズムで」
修平は応えた。
「作品として描いたものを、気に入ったら使ってくれないか。ただ、細かく注文をつけられて描くのは、冬樹さんの仕事でもいやだ。それでもいいかい?」
「いいよ。作品を、こちらは使わせてもらうだけということで」
そのチラシに使った蜘蛛のイラストレーションが、名古屋公演での告知にも使われたのだった。
七ツ寺共同スタジオでの公演は、金曜日から日曜日までの三日間で、全部で四回のステージだった。修平と奈津美は、土曜日夜のステージを観に一緒に名古屋に向かった。冬樹の芝居を東京以外の場所で観るのは、修平にとっても奈津美にも、楽しい体験になると思えた。
修平は、冬樹に訊いた。
「まずあのスタジオに行くとして、誰かと会う約束でも?」
「何もしていない」
「七ツ寺共同スタジオに行くだけだと、だいぶ時間があるね。その次は?」
冬樹が言った。
「当時のバブリーな夢の跡を見てみたい。劇場建設予定地だった所とか。ぼくが何度かあの実業家にお酒をごちそうされた場所なんか」
「行って、愉快な気持ちになれるかい?」
「苦い思いをかみしめるのでもいいんだ。あれも、ぼくの人生だった」
「無理に思い出すこともない」
「結果はああだったけど、あのひとをぼくは、じつは嫌いでもないんだ。ぼくを騙したわけではないし、ぼくは実害をこうむっていない」
いいや、と修平は思う。冬樹はその実業家、名古屋の不動産会社のオーナーと一時期親しかったことで、十分に害を被った。修平の感覚では、けっして小さくはないだけの被害を。なのに冬樹が、彼を嫌いになれないと言ったことは意外だった。冬樹から聞いた範囲でも、修平にはかなりいかがわしい人物と感じられていたその男に、冬樹を魅了するだけの何があったのだろう。
修平自身は、その男を直接には知らない。冬樹から話を聞いていただけだ。
「金重と言ったかい」
「金重昇。もう亡くなって久しいらしいけど」
冬樹と金重が仕事上の関係を持つようになったのは、修平と奈津美が七ツ寺共同スタジオに冬樹の芝居を観に行ったときから六、七年は後のことだ。冬樹がニューヨークから帰ってきて二年目あたりのときではなかったろうか。
冬樹が時計を見た。
「何時にチェックアウトする?」
「十時ちょうどに。名古屋にはこだまで四十五分前後だ。早めに入るかい。それとも浜松にもう少しいる?」
「十二時くらいのこだまに乗ろう。浜松駅で、少し時間をつぶして」
「ランチは名古屋で?」
「たいして食欲もないけれど」
やはり昨日の砂丘歩きは、冬樹にはけっこうな負荷だったのだろうかと、修平は反省した。
ホテルをチェックアウトすると、浜松駅ビルの喫茶店で少し休んだ。
冬樹はコーヒーカップを前に、ほとんどろくに口をきかなかった。不機嫌という顔ではない。何かを思い出して、それを反芻しているという顔だった。
新幹線の発車時刻までは四十分以上あったから、修平は冬樹が追憶にふけるにまかせた。こちらの話題を持ち出して、せっかくの時間を邪魔してしまうことは避けたほうがいいだろう。
けっきょく修平たちは、発時刻の十二分前に喫茶店を出て、十二時二十三分の浜松発下りのこだまに乗った。
この列車でも、ふたりは並んで席を取ることができた。窓側の席には冬樹が着いた。
出発しても、冬樹はとくに窓の外の景色を見るわけでもなく、物思いにふけっていた。
冬樹が修平に話しかけてきたのは、豊橋を出てからだ。
「さっきの喫茶店でも、ミミのことを思い出していた。フラッシュバックしたみたいに、断片的に次々と。あるとき月蝕洞に行ったら、ミミが涙ぐんでいて、同じテーブルで修さんが当惑顔だったことがあった。覚えているかい?」
「あった」と修平も、たしかにそんなことがあったと思い出した。「奈津美ちゃんが、会社を辞めるかどうか悩んでいた時期。ほかにもいろいろあった時期だ」
「修さんが泣かせたと思ってそう言ったら、修さんはあわてて否定した」
「ぼくが原因じゃなかった。ただ、ぼくが先に行っていて飲んでいて、奈津美ちゃんは遅れてやってきた。約束していた夜じゃなかったと思うけど、冬樹さんも来たんだから、約束していたのかな。奈津美ちゃんが席に着いてビールを一杯飲んだら、泣き出した」
「ミミが就職して五年目だったっけ?」
「六年になっていたんじゃなかったかな。実家には、まだ戻れないって東京暮らしを認めさせていた。その時期は、つきあっていた男のこととか、職場のこととか、悩みが重なっていたはずだ。ぼくはそうした事情を詳しく知っていたわけじゃないし、どうしたらいいものか焦った」
「ぼくが席に着いてふたりに話を聞こうとしたけど、ぼくは修さんがてっきり、何か冷たいことをしたのだと思った」
「だったら一緒の席にはいない」
「でも修さんは、いくらなんでもそれはないだろうということを、ミミに言ったよ」
「何だっけ?」
「これからおいしいものを食べに行こうかって。女性が泣いているときに、何か食べようって提案はないよ」
「悩みがあるとき、満腹感は幸福感の代わりになる。少なくともぼくはそうだから」
「月蝕洞からよそに食べに行くことは妙だよ。ミミは、涙をこらえて月蝕洞までやってきたんだから」
「ぼくはそのあたりの女性の心理には疎い」その夜の具体的な部分が少し思い出されてきた。「冬樹さんが、妙に実際的な提案をしたのがその夜だった」
「ぼくはミミに何を提案した?」
「明日美容院に行くか、旅行に出ろって」
「そんなことを言ったかい?」
「言った。その夜だったと思う」
「ミミはどう反応したんだっけ?」
「涙を拭いて、そうか、とか、それもいいとか。冬樹さんは、パリに行け、とも言わなかったかな」
「言ったな。服飾業界の女性なんだから。ミミは、どういう反応だったっけ?」
「たしか、一緒に行ってくれるんですか、って冬樹さんに訊いた」
「いいよ、とぼくは答えたんだったかな。自分のパターンを考えると、きっとそうだ」
「いいよ、だけど貯金してからでいいかとか、逃げた」
あのときの奈津美の反応を、もっと明瞭に思い出した。彼女は言ったのだ。
「そんな、冬樹さん。パリって言葉にはぐらりと来ますよ。ほんとに一緒に行きます?」
冬樹が答えた。
「本気だ」
「全然そうは聞こえないんですけど」
「何人にも言い過ぎたせいかな」
「明日飛行機に乗りますか?」
「ああ、荷造りが間に合わないな」
修平も奈津美に言った。
「ぼくとパリというのは?」
奈津美が修平に顔を向けた。
「修さんには似合わない。パリじゃないほうがいいと思う」
「ぼくならどこがいい?」
「ぼくと、盛岡のリンゴ園に行かないか、とか」
「そうだよ」と修平はわざといじけて見せた。「ぼくには岩手の田舎が似合ってるのさ」
「盛岡のリンゴ園、悪い意味で言ってませんよ。わたし、本気ですよ」
奈津美はもう涙顔ではなくなっていた。
冬樹が言った。
「あのとき、ミミは、ほんとのところ、どう言ってもらいたかったんだろう」
修平は首を振った。
「わからない。でもぼくらとそういう馬鹿を言ったことで、少し気は晴れたみたいだった。あの夜もふたりで奈津美ちゃんの飲み代はもって、ぼくが地下鉄まで送った」
「ミミが高円寺に引っ越したのはその後?」
「だったと思う。引っ越しの正確な時期は知らない。それから半年しないうちに、勤めも移っていた」
「修さんはそのころはどうだったんだっけ?」
「ぼくも、勤めていた広告プロダクションを辞める気持ちになっていたな。次は広告代理店に移ると決めて、転職雑誌を読んでいた。応募も何回かしていたかもしれない」
「三人とも、人生の転機が来ていたあたりだったか」
冬樹には、翻訳ではなく、オリジナルの戯曲の依頼がぽつりぽつりと来るようになっていた。冬樹が親しくしている演出家たちから、頼まれるようになっていたのだ。
どの作品もそれぞれ好評だったらしく、冬樹は戸惑いつつもその評価を受け入れ始めていた。修平たちには、食べて行けるかどうかわからないことに打ち込むわけにはいかない、と言いながらもだ。
「稽古場に呼ばれて行くこともあるけど」と、冬樹が修平たちに言ったのは、そんな時期のことだ。「現場ってけっこう楽しいんだ。ずっと言葉だけを相手にしてきた身には、生身の人間を相手に仕事をするっていう体験は、刺激的だ」
きっと冬樹は自分でも演出をしたくなっているな、と、このころ修平は思ったのだった。
西へ向かう新幹線の中で、また冬樹が言った。
「それで思い切った。ぼくの五本目のオリジナル戯曲を書いた後だな。その脚本料で電話を引いた。それからは月蝕洞に電話を取り次いでもらわなくなった。まだ誰もが、固定電話と留守番電話で仕事をしていた時代だ」
修平は、冬樹が口にした時期の前後を思い起こして言った。
「ぼくはまだ、飲む約束は事務所に電話をもらって決めていた」
「ミミが電話を引いたのは、ぼくらより早かったな。引っ越してからすぐに引いたんだったか」
「そうだった。教えてくれた番号に、月蝕洞からふたりして電話してみた。そうしたら高円寺のアパートからやってきた」
そういうことがあった。
あの夜、冬樹が修平に訊いたのだ。
「ミミの電話番号、聞いた?」
「このあいだ、教えてもらった」と修平は手帳を見せた。
冬樹が時計を見た。八時半になろうかという時刻だったはずだ。
「誰かがかけてきてくれないかと、膝を抱えて電話の前に座っているかもしれない」
「まさか。友達からひっきりなしにかかっているよ」
「わからないぞ。修さんは番号教えてもらったのに、かけていないんだろう?」
「とくに用事もなければ、かけないよ」
「教えてくれたんだ。用事なんてなくてもかけるべきだよ。声が聞きたい、ってだけでも十分な理由だ。せっかく引いた電話を、使わせてやろう」
月蝕洞のカウンターの端の電話機から、冬樹が奈津美の電話番号を回した。
冬樹はすぐに修平に顔を向けて、口だけの動きで言った。
いた。
冬樹は受話器に言った。
「堂内です。修さんからこの番号教えてもらった。月蝕洞だよ。修さんが隣りにいる。うん代わるよ」
修平が受話器を受け取って言った。
「及川です。かけてみようってことになって」
奈津美は笑い顔が想像できる声で訊いた。
「何度かかけてました?」
「いいや。いまかけたばかり。どうして」
「いま帰ってきたところなんです。玄関入ったら、電話が鳴ってた。何かありました?」
「重大なことじゃないだけど」
横で冬樹が言った。
「出て来ないかって」
修平は奈津美に繰り返した。
「出て来ない?」
「行きます。四十分はかかるけど」
「遅くなっても、待ってる」
奈津美は三十五分でやってきた。
奈津美が言った。
「髪を洗う前でよかった」
その夜は、奈津美も十一時過ぎまで店にいたのだった。
冬樹が窓の外に向けていた視線を修平に向け直して言った。
「仕事のためというよりも、酒を飲むためにも絶対に電話が必要だって思った。ぼくらの会う頻度がいちばん多かったのは、もしかしたらあのころかな。芝居にもよく一緒に行った。『上海バンスキング』も観に行った」
冬樹は、昨日以上にあの時代のことを鮮明に思い出しているようだった。
修平も記憶を探りながら答えた。
「再演だった。初演を観た冬樹さんが強く勧めて、三人で霞町まで観にいった。奈津美ちゃんは、後になっても猛烈に好きだと言っていた。たぶんいまもだ」
「自由劇場の『地下室』も行った」
「吉田日出子が一瞬ヌードになるお芝居」
「そうだ。後ろ姿のヌードがあったやつだ」
「冬樹さんは、観たあと、何度も舌打ちしていた」
「ああ。この手があったか、と思ったんだ。『砂の女』の男女をひっくり返して、俗な犯罪ドラマの設定で、これができるかって」
「冬樹さんは『蜘蛛の棲む部屋』をまだ書いていなかったね」
「あの原型は書いていた。あの日はどうして六本木で飲んだんだっけ?」
「霞町だったから、月蝕洞まで遠かった。だけど三人とも、少しでも早く話したい気分だったんだ」
「そうか。あの原作、翻訳を読んでいたのに、あんなふうに舞台化できるとは考えなかった。そういうことを語り合いたくてたまらなかった」
「高校生で読んだと言っていたよね」
「うん。イギリスの作家だ。ジョン・ファウルズ」
冬樹が窓の外に視線を向けた。列車は、農地の多い、しかし純粋な田園地帯とも言えぬ、住宅地の混在する平坦な風景の中を走っている。
修平は時計を見た。名古屋までは、あと三十分ほどだ。
名古屋駅に着いて、高層ビルの目立つ東口に出た。
七ツ寺共同スタジオまでは、タクシーを使った。中区大須にあるその劇場まで、地下鉄でも行けるが乗り換えがある。ホテルのチェックイン時刻前だったし、旅行荷物を持っての移動は、冬樹にはきついだろうと思えたのだ。直線では二キロメートル弱という距離だから、タクシーもさほどの料金にはならない。
劇場は、大須通りから北に入る中通りにあった。着いてみると、大須通りはもちろん、その中通りも様子はずいぶん違っているように感じた。しかし劇場の建物は記憶にあるものとさほど違っていない。古い商店を改装したと見える、あまり洗練されているとはいえない外観の建物のままだ。
間口は四間ほどだろう。一階の正面のコンクリート部分は赤く、二階の外壁は白い。サイズの不揃いなエアコンの室外機が壁につけられている。
一階には黒っぽい板壁があって、くぐり戸がついている。開演時は板壁の一部が扉として開くのだったろうか。板壁と見えるもの全体が、扉なのかもしれない。修平にはどうであったか記憶がない。
板壁の右手に出窓ふうの掲示板があり、ポスターやチラシが貼られたり置かれたりしている。さらにその隣りには飲み物の自動販売機。
二階のガラス窓には、七ツ寺共同スタジオ、と看板屋の手が入ってはいないシールで作られた文字が貼られていた。
冬樹が外観をざっと眺めてから、くぐり戸の前へと歩いた。
入ろうとしているのか? 修平も後ろについた。
冬樹はくぐり戸の把手に手をかけたが、戸は開かなかった。
冬樹はチラシの貼られた出窓のような作りの掲示板の前に立った。彼はチラシをざっと見ていたが、やがて修平を振り返ってきた。
「きょうは公演はないようだな」
修平は言った。
「やっと一時だ。まだ誰も来ていないのか」
「いや、ないんだろう。名古屋の事情はわからないけど、五十年前よりも芝居小屋は増えているのかもしれない。わざわざここを使わなくても」
「それでも、ここは伝説だ」
「スズナリみたいなものかな」
ふいに冬樹が言った。
「あのとき、アフタートークで、修さんが何を言ったか、覚えているかい?」
あのときとは『蜘蛛の棲む部屋』の公演のときのことだ。おおよそのところは覚えている。正確には、アフタートークで冬樹と、プロデューサーであった山浦とのやりとりのあとのことだ。
観客からの質問に対して冬樹が答えるという時間がもうけられた。東京から招かれた演出家と俳優たちということで、このスタジオの常連客には質問もあるだろう、という予想だったのだろう。少し難解な作品、と山浦は思っていたのかもしれない。
「少しは」と修平は答えた。
あの夜、開演前に山浦に紹介されることもなく、一般客として修平と奈津美は客席に入ったのだ。
たしかふたつ、作品のテーマに関する質問があって、冬樹はかなり真正面から誠実に答えた。ふつうはそこまで解説する必要もないレベルのことまでを明かしたのだ。
三人目の質問者は訊いた。
「これは、『砂の女』でしょうか?」
質問したのは、四十歳ぐらいの、いかにも文学愛好家らしい雰囲気の男だった。彼の言葉にはほんのわずかに意地の悪い調子がこめられている、と修平と感じた。つまりこの質問は、『砂の女』の剽窃もしくは翻案かとの意味だった。冬樹はそれまでも、よその劇団のために書いた脚本も、自分の劇団での公演も、ときどき同業者の一部からはイギリス現代戯曲の剽窃とか模倣と評されることがあった。冬樹が頼まれてイギリスの現代戯曲の無断翻訳をしていたことが、そうした中傷の一因だった。冬樹もそのことを気にしていた。また当時は、オマージュ、という言葉はほとんど使われてはいなかった。
「いいえ、違います」と冬樹は答えた。すでにもう反発の感じられる口調だった。「どこがどうして『砂の女』かと質問されるのかわかりません。テーマも、設定も、まるで違うことは、素直にご覧いただけたならわかることかと思いますが。これのどこが『砂の女』ですか?」
お前は芝居を観る能力がない、と言ったように聞こえても仕方のないような返答だった。
この答えが、あのとき客席にいた地元の芝居好きの一部を刺激してしまったのだろう。
次の質問者は、三十代なかばかと見える男だった。
「この作品は、アメリカ映画の『今宵限りの恋』を東京の話に置き換えたものでしょうか?」
質問ではなかった。それが原典だろうと決めつけている言葉だった。つまりまた、剽窃もしくは翻案だという指摘が出てきたのだ。
冬樹は当惑したように答えた。
「その映画は知りません」
「サンデイ・デニスが女性の役でした」
「そのひとも知りません」
「一カ月ごとに同棲する男を変える女性と、その女性に本気になってしまった男性の話です。ニューヨークが舞台で」
「知りません。いつごろの映画です?」
「十年ぐらい前かと思いますが」
「原題は何と言うのです?」
「『スイート・ノベンバー』です。十一月の男、という意味が含まれています」
「もし似ているとしたら偶然です」
最初に質問した男が、また手を挙げた。
修平も手を挙げた。このままでは、このアフタートークが荒れると感じたのだ。冬樹の表情は、非難してくるなら受けて立つと言っているようだった。彼はふだんは温厚だけれど、いったん誇りを傷つけられたと感じたときは、獰猛になる。修平ももうそれがわかっていた。
プロデューサーの山浦が修平を指名してくれた。
修平は訊いた。
「最初のほうで女性が、観葉植物を示して、この鉢を捨てて、と言いますね。あとのほうでも、お客からもらったと言って花束を持って部屋に帰ってきますが、鉢も花束も、男の暗喩でいいのでしょうか?」
もちろん東京で舞台を観たときに、それはわかっていた。でも、この劇場では観客にはそれが伝わっているのかどうか、微妙な反応だった。なので冬樹に解説させるつもりで、それを質問したのだ。
冬樹が表情をゆるめた。
「そのとおりです。鉢植えは、部屋に根を張ろうとする男の暗喩です。女性はそれを明快に拒絶しています。花束は、根を持たない切り花ですから、女性が次の男を見つけたことを暗示しています」
山浦が、そこでアフタートークの時間を打ち切った。
「時間もオーバーしました。ここまでにしましょう。みなさん、堂内冬樹さんにいま一度盛大な拍手を」
拍手が起こり、冬樹は椅子から立ち上がって一礼した。
上演の後、関係者は共同スタジオ近くの居酒屋で打ち上げをすることになっていた。始まるまで多少時間がある。修平は奈津美と一緒に近くの喫茶店に入った。
奈津美が訊いた。
「修さん、あの質問は、ほんとは訊かなくてもいいことだったのよね?」
「ああ」修平は答えた。「あのままでは、冬樹さんは切れた」
「そうだと思った」
時間になって打ち上げの会場に行くと、山浦は修平を見て、あ、そうか、という顔になった。冬樹との関係を理解したのだ。友人として、あの不穏な質疑応答の場にタオルを投げ入れたのだろうと。
打ち上げが始まって、最初のうちは芝居関係者と、それ以外の客や関係者の友人知人とが分かれて談笑していた。三十分ほどしてから、冬樹が修平たちのそばにやってきた。
冬樹がふたりを見て言った。
「名古屋まで観に来てくれるなんて、感激してるよ」
奈津美が言った。
「やっぱりお客さんの雰囲気が違いますね」
「東京の下北なんかだと、客も芝居を観慣れているのかな。ある意味すれている」それから冬樹は修平に顔を向け、微笑した。「質問、サンキュー」
修平は肩をすぼめた。とくに何もしていないけれど、と。
プロデューサーが横から訊いた。
「打ち合わせていたんじゃなかったのかい?」
「全然ですよ」と冬樹が答えた。
奈津美が冬樹に訊いた。
「最初のときと、演出が変わっていますか?」
「わかるかい」と冬樹。
「きょうのお芝居、なんか女のひとが哀しくて、最初のときと違うように感じた」
「じつは変えたんだ」冬樹は、振り返って、関係者が飲んでいるテーブルから女優を呼んだ。「ハルカ、ちょっと来てくれ」
山岸遥という女優が立ち上がり、修平たちのいる席までやってきた。東京での公演のときも、彼女が同じ役をやっている。いま冬樹が呼び捨てにしたのだから、冬樹と同い年か年下なのだろうか。しかし役柄は、もう少し歳上の設定のはずだ。背が高く、宝塚の男役ふうとも言える顔だちの女優だった。
冬樹が修平と奈津美を、東京から観に来てくれたと紹介してから、山岸遥に言った。
「こっちのミミちゃん、きょうは遥の役が哀しかったって」
山岸遥が微笑して奈津美に言った。
「よかった。わたし、こんどの稽古で冬樹さんに言ったんだけど、この蜘蛛女はほんとは哀しいひとですよねって」
冬樹が苦笑した。
「最初に書いたときは、男の視点で、共感能力の欠如した女に捕まって放り出された、って設定のつもりだった。ところがじっさいに役者さんが芝居にすると、むしろその解釈でも面白いかと思えた。最初の公演のときは、書いたときの設定で通したんだけど、ここに持ってきたのは、新演出なんだ。遥はその複雑な部分を演じられるし」
山岸遥が言った。
「それで、こんどはそれを匂わせたんです。彼女が男には情を移さないよう、かたくなになっているわけ。共感能力が高いことを自分の欠点と思っているために、自己防衛があの生活なんだと」
冬樹が言った。
「ミミが哀しいと言ってくれるんなら、この演出は成功だった」
山岸遥が奈津美に訊いた。
「冬樹さんのお芝居をずっと観てらしてるんですか?」
奈津美が答えた。
「ほかの劇団の舞台も、冬樹さんとは一緒にけっこう観てるんです」
「お芝居をやっているんですか?」
「いいえ。完全に部外者です。観るだけのひと」
山岸遥が、冬樹に訊いた。
「どうしてミミさんを出さないんです?」
冬樹が答えた。
「ミミは堅気なんだ。勤めを持ってる。とても頼めない」
奈津美が言った。
「そもそも無理です。演技なんて、勉強したこともないんですから」
「トレーニングすれば」と山岸遥が言った。「とても雰囲気があるんだから」
「どんな仕事だって、雰囲気だけでは」
「どういうお仕事なんです?」
「服飾関係です」
「なんというお店?」
「メーカーの本社です。企画の仕事をしているんですが」
「メーカーで企画って、面白そう。CMなんかを作るの?」
修平は冬樹に訊いた。
「初演では、何回か暗転するとき、照明が一瞬蜘蛛の巣を部屋の隅に見せたよね。あれがなくなっているのは、何か理由はある?」
冬樹が、その理由を話し始めた。ちょっとくどいと思えるような説明だった。たぶんそれは修平にではなく、山浦に向けた言葉でもあったのだろう。
山岸遥が立ち上がり、ちょっと戻ってきます、とそのテーブルから離れていってしまった。
冬樹が山岸遥の背に目をやってから言った。
「何だい? 何かあったのか」
奈津美が謝った。
「わたしが、生意気なことを言ってしまったみたいです」
冬樹が修平に訊いた。
「そういうことか?」
修平は答えた。
「彼女は、奈津美ちゃんが何者か気になってるんだよ」
「ぼくのマスコットだよ。芝居の同志じゃない。誤解を解いてこなくちゃ」
冬樹が席を離れ、また関係者たちのテーブルに戻っていった。
修平は奈津美を見た。奈津美は修平の視線を避けるようにビールのグラスを口元に持っていった。
舞台は翌日日曜日もあったのだけど、打ち上げは深夜まで続く気配だった。修平は奈津美を誘い、名古屋駅近くに取ったビジネス・ホテルに戻ることにした。
冬樹は機嫌がよく、引き止めたりはしなかった。修平たちは打ち上げ会場の居酒屋を出た。
ホテルまでは歩いて帰ったのだが、途中の話題は芝居のことではなく、名古屋観光のことがほとんどだった。翌日の日曜日を、修平は名古屋の古い建築を観て回り、スケッチするつもりだった。奈津美は、繁華街の服飾店やデパートを覗いて、午後の早い時間に東京に戻るという。最初から彼女はそのような切符にしていたのだ。朝食だけは一緒に食べることにした。
ホテルの部屋はフロアが違った。奈津美の部屋が上の階にある。
エレベーターで先に修平が降りるとき、奈津美が言った。
「修さん、さっきはありがとう」
「ん?」と、何のことを言われているか気づかぬふりで奈津美を見た。
奈津美は微笑した。
「ちょっとわかりやす過ぎた」
修平は苦笑するしかなかった。
「あまりバリエーションを持っていないんだ」
「おやすみ」
エレベーターの扉が、修平の目の前で閉じた。
冬樹が、スタジオの前の中通りで修平に顔を向けた。
「行こう」
次は名古屋では歴史ある部類の高級ホテルだという。そのあと、栄という繁華街に行きたいとのことだった。
修平が地図を確認すると、そのホテルまで一キロメートル以上ある。名古屋のまるで別のエリアにあるというわけではないが、冬樹の様子を見ると、その距離を歩いてもらうのは酷だった。修平はタクシーを使おうと提案し、停めやすい場所まで移動した。
タクシーが走り出してから、冬樹が言った。
「例の金重が名古屋にぼくを呼んで、部屋を取っておいてくれたのが、そのホテルだった。当時は名古屋で一番のホテルだったんじゃないかな。駅に秘書が迎えにきていてホテルに連れてゆかれ、チェックインしたところで、ご本人と会った」
修平は訊いた。
「それが初対面?」
「電話では一回話していた。とにかくお目にかかって、話を聞いてもらえないかと。名古屋に来てもらえれば、いろいろご案内もすると」
「ご案内というのは、建設予定地を?」
「あの段階では、建設希望地と言うほうが正確だったな。錦という繁華街のあたりで、買収を進めている土地があるとのことだった。完了してはいなかったけど、あと少しで終わると聞かされた」
「漠とした話だったんだよね。聞いている限りでも」
「大まかな構想はあったんだ。図面もできていた。ただ金重は、あの景気の崩壊前につまずいた」
「彼は、ほんとうに劇場を持ちたかったんだろうか」
「その気持は本物に思えた。俗物だったけれど、ショービジネスをきちんとやりたかったんだ。劇場と、劇場運営の専門企業と、芸能プロダクションを持ちたいと真剣に願っていた。不動産業は、夢をかなえるための手段だった」
「芝居を、わりあいよく観ていたひとだと言っていたね」
「俗物が観る程度には観ていた。西新宿のテントの小屋で『キャッツ』。ニューヨークにも行っていたんだ。『オー・カルカッタ』と、『コーラスライン』を観たと言っていた」
「『オー・カルカッタ』か」
「ベケットも観ているんだ。話さなかったかな」
「ロンドンで?」
「新宿。紀伊國屋ホール」
「そんなにすごい芝居好きだったのか」
「それが、東京出張のときに漫才でも見たいと、社員にチケットを探させた。社員は星セント・ルイスが出る公演があるのを見つけた。漫才コンビの星セント・ルイスは知っているよね」
「覚えている。好きだったな」
「彼らが『ゴドーを待ちながら』に出たことがあった」
「ああ。評判だったやつだ。チケットがまるで取れなかった公演じゃなかったか。観てはいないけど」
「ぼくは観た。金重さんも、面白かったって言ってた。星ルイスがよかったとも。芝居を観るセンスはあるひとだったんだ」
タクシーはそのホテルに着いた。十八階建てだという、茶色っぽい外観のホテルだった。
車寄せでは、ベルボーイがタクシーのドアに手をかけて、修平たちを迎えてくれた。
修平は訊いた。
「会ったのは最上階かい?」
「夜の食事は。最初に会ったのはラウンジだった。そこでコーヒーを飲もう」
修平たちはラウンジに向かった。
向かい合うソファとソファのあいだが広すぎるラウンジで、修平たちは少し前屈みになり、コーヒーを飲んだ。
冬樹が言った。
「最初に話があったとき、ぼくは彼が声をかけた何人目の演劇関係者なのだろうかと考えた。ぼくの世代で、ぼくよりもすでに有名で、固定客が数万ついている演出家は何人もいた。いや、客が万の数でも、二十人はいたんじゃないだろうか」
「じっさいは何人目だった?」
「それを訊いたことはない。だけど、ぼくが最初から狙いだったはずはないさ。ぼくのアドバンテージは、ニューヨークで芝居を勉強し、あちらのショー・ビジネスにも多少知識があると見えていたってことくらいだった。金重はすでにメジャーな人気の演出家には、何人もに断られていたんだろう。だから、少し乗り気を見せたぼくで決めたんだ。さいわいぼくは、あの時期、それまでとは違う立場で芝居に関われないか、試行錯誤中だった。金重が持ちかけてきた話は、魅力があった」
修平も冬樹から聞かされていた。あの数年前には、冬樹は劇団の主宰にも、自身でプロデュースし演出することにも、熱を失くして、劇団も事実上解散していた。
月蝕洞で、冬樹が芝居仲間と飲んでいるときに遭遇すると、彼はときおり芝居仲間のことをよく愚痴っていた。やつは、あるいは彼女は、基本的な芝居のセンスがない、台詞を理解できない、台詞の意味の多義性を表現できない等々だ。それを同じ芝居関係者に言っていいのかと、修平はよくはらはらしたものだった。
冬樹が金重の計画に乗ることになる二年ほど前のころだったろう。それは冬樹がニューヨークから帰ってきて、自分の劇団での活動を再開してから二年目ぐらいのときでもある。公演の初日、主演男優が急病で劇場に来れなくなるという事故が発生した。冬樹は配役を入れ換え、小さな役は自分が演じることにして、二日休演しただけでなんとか乗り切った。けれど修平は正確なところを教えられた。その俳優は前夜に冬樹と演技をめぐって揉めたことが理由で、急病を理由に劇場に来なかったのだと。俳優は自分の評判が落ちようとも、公演が御破算になることのほうを望んだのだ。
それが、冬樹が主宰していた劇団の最後の公演となった。冬樹は解散を発表しなかったけれども、消滅した。以降、冬樹は演出からは退き、劇作家という立場で芝居に関わるようになった。かたわら、詩作も始めていた。
劇団は解散したけれども、あの時代、東京には映画や演劇関係の教室とか塾とかがずいぶんできていた。冬樹はいっとき、いくつかの教室の講師を掛け持ちでやっていたこともあったし、地方でのワークショップにも招ばれていた。芸能関連の雑誌に劇評も書くようになっていた。修平には、冬樹は自分の劇団を持っていたとき以上に、忙しそうと見えた。
劇団を事実上解散する直前あたりに、冬樹は修平たちにもらしたことがある。
「ひとと一緒に何か作るってことが、ぼくには無理だとわかったよ。面白く思えた時期もあったけど、ストレスのほうがずっと多い。舞台を作る以前の段階で疲れ果ててしまう。ぼくには、ひとりでする仕事のほうが向いている」
奈津美がたしかそのときに言ったはずだ。
「ひとづきあいのうまい下手とか、人間の管理とかって、芸術の才能とは別だから。冬樹さんがそっちが苦手なのは、しかたのないことだと思う」
修平も同意できた。だからその後冬樹が、名古屋の実業家の支援を受けて、名古屋に計画されている劇場建設のためのアドバイザーと、竣工した後はその劇場の芸術監督となると知らされたとき、心配もした。冬樹の資質に向いているかどうか、危ういと思えたのだ。
芸術監督というのは言ってみれば劇場のプロデューサーということであろうし、それは劇団主宰者のすることとは本質的には同じものではないかと思えたのだ。
「違う」と冬樹は修平の懸念を一蹴した。「もつ権力が違う。劇場という劇場が、ぼくの力になるんだ。カネもなく、稽古場も持たない劇団の主宰者とは、まるで違う立場になる」
「でも、その後ろには資本がある。百パーセント自由にそのハコを使えるわけでもないだろう?」
「素人は口を出せない分野だ。十にひとつふたつは、妥協が必要になるにしても」
奈津美が訊いた。
「東京を離れてしまっても、いいの?」
「ああ。東京ローカルの演劇人である必要はないさ。すでにぼくは、一回東京を離れた」
ニューヨーク派遣のことを言ったのだ。
「でも、あれは留学でしょう? 勉強しに行ったので、お芝居を作ってきたわけじゃなかった」
「向こうでも、小さい公演にはいくつも関わった。日本の小劇場の制度の中で活動しなかっただけだ」
あのときは、冬樹は新設される劇場の芸術監督になることに、少し意外にも思えるくらいに積極的だった。
ラウンジでのコーヒーを飲み終えぬうちに、冬樹が促した。
「建設予定地だった場所をちょっと見ておきたい。それからホテルにチェックインしよう」
冬樹は、タクシーを降りてもしばらくはそのままそこに立ったままだった。
感情の読めない顔で、周囲を見渡している。
修平は訊いた。
「ここじゃなかった?」
「所番地なら、このあたりだ」
栄という繁華街の、いくらか外れということになるのだろうか。高層ビルなどないどころか、洒落た商業ビルが密集するエリアでもない。築五十年は経つかと思えるような小さなビルと、隙間に駐車場が目立つ一角だ。そのブロックと周辺は、再開発がまだ始まっていないエリアのように見える。
冬樹はその前まで歩き、周辺をもう一度見渡してから言った。
「このあたりだ。劇場と、テナント・ビルができる予定だったのは」
「繁華街が近いのかな。名古屋には、いまはいい大劇場がいくつもあるはずだけど、このあたりじゃないよね」
「金重は言っていたよ。芝居を観たあとは、酒を飲んで話したくなるだろう、って。東京の国立劇場みたいなところで観て、その後どうするんだよとも。ニューヨークもロンドンも、劇場街は飲み屋街だ。劇場はそういう場所に必要なんだ、っていう持論だった。賛同できたよ」
「ぼくもその点は同意できるな。劇場は、都会の猥雑なエリアの中にあったほうがいい。かける舞台の性格にもよるだろうけど」
「それに彼には、ぼくをアドバイザー、顧問としてくれた時点で、義理もできた。彼は、芸術監督に就く以上、名刺代わりの著作があったほうがいいと、ぼくの戯曲集と、最初の詩集を出してくれたんだ。月々の顧問料とは別にだ」
最初の戯曲集のタイトルは『堂内冬樹戯曲集 夜更けの水位』で、最初の詩集が『海浜植物』だった。どちらもハードカバーで、詩集のほうは印刷にも凝っていた。活版印刷だったのだ。東京の自費出版本をよく手がけている小さな出版社からの刊行だった。修平はエディトリアル・デザインは専門外だったけれど、最小限の知識はあった。詩集の印刷と装幀には少し助言をした。
修平は訊いた。
「金重って実業家とは、計画が流れた後は?」
「会わなかった。秘書から、社長が捕まったのであのプロジェクトはいったん中止になりますと連絡があって、それきりになった。二十年くらい前に亡くなったらしい」
「詐欺で捕まったんだっけ?」
「詳しいことは知らない。会社のカネのやりくりで違法な部分があったらしい。裁判が終わらないうちに、会社は破産した。本人は二年か三年の懲役刑だった。控訴したけど、実刑が確定して、彼の人生は終わったんだ」
逮捕された前後の報道をいくつか覚えている。その金重という実業家は、劇場経営に意欲を持っていたくらいだから、芸能界にも人脈を作ろうとしていたらしい。有名女性アイドルとの会食の写真が写真週刊誌に流出し、実業家というよりは完全な山師と見なされたのではなかったか。
彼が逮捕されるころには、冬樹が某大手企業の支援を受けて、名古屋に新設される劇場の芸術監督になる、という話は関係者のあいだにはそれなりに広まっていた。金重の逮捕後は、冬樹の周囲の一部では、冬樹はその山師のカネにたかろうとした演劇人だ、とレッテルを貼られた。ひとによっては、剽窃や模倣の疑惑よりもそちらを嫌悪したかもしれない。いや、嘲笑したのか。
冬樹が修平に身体を向けて言った。
「チェックインしよう。またタクシーで行ってもらえるかな」
「行こう」
名古屋駅の南口に近いビジネス・ホテルにチェックインしてから、修平は冬樹に訊いた。
「夕食はどうする?」
冬樹は少し考えた様子を見せてから答えた。
「あまり食欲もないな。どっちみち、この近所に出て食べることになるね」
「少しだけでも、食べたほうがいいんじゃないかな。スーパーで、何か買ってくるかい?」
「少し休んでから考える。電話するよ」
エレベーターに乗ると、冬樹が訊いた。
「ミミとニューヨークに来たとき、『オー・カルカッタ』は観た?」
「いや」修平は答えた。「観てないよ。観たのは、冬樹さんが関わったっていう」
「『ノー・ワン・リーヴズ・ザ・ポーチ』、学生たちの卒業公演みたいなものだった」
「着いた翌日にそれを観て、帰る前の晩に『ファンタスティックス』に連れていってもらった。それだけ」
「あのときミミと一緒に来てくれてうれしかった。ぼくがニューヨークで何をしているか、ふたりに知ってもらえた。ニューヨークでただぶらぶらしているんじゃなくて」
「そんなことは夢にも思っていなかった」
「心配していたんだ」
エレベーターを降りて、冬樹の部屋の前まで彼を送った。
(つづく)