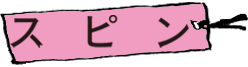『自閉症のぼくは小説家』 第8回「橋になったことば」
内田博仁(うちだ・はくと)
2025.12.12

連載第8回 橋になったことば
「はくとくんて友達とかいるんですか?」
登校班で一緒だったある子から隣にいる母に無邪気に放たれたその質問に、僕の心がチクッと一瞬傷んだ。僕には友達と呼べる人がいなかったからだ。
話せない僕がどうやって友達をつくる? 僕は悩んだ。
小学校の時、僕はよく朝の登校時に「はくとくんおはよう!」と話しかけられた。僕は心の中では「おはよう!」と元気よく答えていた。でもそれを声に出せない。目も合わせられない。悔しい。せっかく話しかけてくれたのに。どうして僕は声にだして「おはよう」と言えないのだろう。そのたった一言も伝えられない悔しさと虚しさ。同級生は戸惑った表情をしている。母が代わりに「おはよう!〇〇くん」と答える。これが僕のできる精一杯の同級生との交流だった。いやこれでは交流とも言い難いだろう。
一番(今でも)憧れること。それは友達とおしゃべりすることだ。
自閉症の人は一人が好きだと思われがちだがそれは間違いだと思う。大勢の人の声が苦手で静かな場所にいたいだけで、別に一人が好きなわけではない。本来僕は人が好きだし友達だって欲しいのだ。
僕は小学校の時、支援学級に在籍していた。そして朝のホームルームだけを普通クラスで皆と一緒に過ごしていた。ここでも皆が「おはよう!」と言ってくれる。僕はまた心の中で「おはよう」と答える。でもそれはやっぱり伝わらない。いつも先生と手を繋いでやってきて、いつも先生の隣にいる僕。いつも守られている子。特別で何を考えているのか分からない子。言い換えれば遠巻きに見られている僕は、別の世界の子のような存在に見えただろう。これでは友達なんてできるわけがない。
思いがけないメッセージ
そんな僕に少しずつ光が見えてきたのは、小学校三年生になった頃だった。やはりこの時も、僕を救ってくれたのは文字だった。
三年生の時、欠席カードというものがあった。欠席者にその日のクラスの様子を伝えるカードだ。そのカードにはその日の授業の内容や、その日あったことなどをクラスメイトが毎日手書きで詳しく書いてくれた。そしてそれをホームルーム以外の授業は別だった僕に、毎日届けてくれたのだ。みんな毎回、その日の授業を振り返って鉛筆で丁寧に手間暇かけて書いてくれた。
【社会 農家のことをしたよ】
【算数 テストしたよ】
【せきがえしたよ!】
【なわとびしたよ!】
僕はワクワクした。丸い文字、角ばった文字、その子らしさが伝わってくる言葉遣い。一人一人の生き生きとした表情が浮かんでくるような個性的で元気いっぱいの文字たち。それを見るたびに心が躍った。まるでクラスで一緒に過ごせたようなそんな満足感と多幸感で心が満たされた。
そのうち〈友達からのメッセージ〉という欄に、クイズを出してくれるようになった。
【〇〇くんは誰の隣でしょう? (1)〇〇くん (2)〇〇くん…】
と三つの中から正解を選ばせたり、
【星がどこかにかくれているよ!】
とカードのどこかに秘かに星を書いて僕に見つけさせたり。僕はさらにワクワクした。
しかしそれに返事をしたくても僕は文字が書けなかった。何とかしてそのクイズに答えたいと思った僕は、電子手帳で打ってそれを鉛筆で手書きして返事をした。毎回母にサポートしてもらいながら書く文字は筆圧が低くてひょろひょろで幽霊のような文字だったけど、僕は毎回思いを込めて丁寧に頑張って書いた。
「答えは(2)です」
「星みつけたよ」
そんなやり取りを続けているうちに、みんなが様々な言葉をその欄に書いてくれるようになった。
【いつも朝きてくれてありがとう】
【毎回3年1組にきてくれてありがとう】
【はくちゃん5、6組(支援級のこと)にいってもがんばってね】
そうやって書いてくれた言葉たちには僕を思う気持ち、僕への愛情が込められているように思えた。それらの文字たちは温かさと優しさを纏っているように僕には見えたのだ。その言葉たちを見るたびに、僕の心にポッと灯りがともるような幸せを感じた。
でも僕はまだその頃、その溢れる感情や思いをお友達にどう伝えたらいいのかが分からなかった。仲間として受け入れてくれてありがとう。本当に嬉しい。そんなはちきれんばかりの思いたちを胸にいっぱい抱えながら僕は書いた。
「ありがとう うちだはくと」と。
友達と遊んだりおしゃべりできなくても言葉のやり取りで心の交流はできる。このやり取りはお互いが純粋に相手の幸せを願って書いていたと思う。この欠席カードは、僕の心と友達の心を繋げる橋のような存在だった。綺麗な便箋に書かれた手紙ではなくて、それは薄っぺらい黄ばんだ用紙のカードだったけど、僕にとっては友達の心と僕の心を形どった唯一無二の橋のような存在だったのだ。
新しい出会い
高学年になり同級生たちも少しずつ成長し変化していった。皆少しずつ自分の世界を持ち始めていた。自然に同級生との交流も少なくなっていった。しかし僕は僕で、この頃感想文やエッセイを打つという習慣ができて自分の世界を持ち始めていた。僕はさらに文章を書くことに夢中になった。
小学校六年生の頃、僕が今まで辿ってきた道のりを書いた作品がある文学賞を受賞した。その時小学生の部で大賞を取ったのはドイツに住む少年だった(ちなみに僕は佳作だった)。その少年(Cくんと呼ぶ)は、自分の父や曾祖父母たちが戦争や東西分断によってどんな苦しみをもたらし、どのような人生を送ってきたかを壮大なドラマのように描ききっていた。
僕はその表現力と文章力に圧倒された。凄い子だと思った。リモートでの授賞式で見たそのC君の表情は利発的で大人っぽくて、とても僕と同じ小学生には見えなかった。僕は受賞は嬉しかったけれど、正直やり切った感があった。いや、正直に言うとCくんの文章に圧倒されてしまったのだ。
結局僕は翌年この文学賞には応募しなかった。翌年の文学賞でも当然のようにCくんは賞をとっていた。母がそのC君の受賞作品を読みながら「あ! 博仁のことが書いてある!」と興奮して言ってきた。えっ? あのCくんが? と僕は驚いた。母がC君の受賞作品を僕に読んでくれた。
思いは海を越えて
その内容を要約するとこうだ。C君はIQが高すぎて飛び級をした。成績はいつも一番でクラスメイトに妬まれていた。そのためなかなか友達ができなかった。ある日従姉妹に成績を自慢され「僕のほうが上だよ。僕のほうがIQも高いし」と思わず言ってしまった。
それを見たC君のお母さんは激怒して「これを読みなさい」とある文章を渡した。それが僕が書いた受賞作品「信じて!重度障がい者の学ぶ力」だった。C君は【この作品を読んでハッとした】という。【博仁君はどうして? しりたいという気持ちが非常に強い】でも【色々なことを学びたいのにその機会を奪われてきた】【そんな彼が今の僕を見たらどう思うだろう】と考えを改めたというのだ。そして作品の最後に【僕に考えを改めるきっかけをくれた内田博仁君、ありがとう】と結んでくれていた。僕は震えた。僕の文章を読んでくれ、それも海を越えて僕の思いが伝わったという奇跡に心が震えた。
僕が書いた文章が距離を越え、国をも越えC君の心へと届いた。僕の心とC君の心に橋がかかったのだ。C君はこのことをきっかけにして苦手だった友達に「君と友達になりたい」と声をかけることができたのだという。
僕はこれを読んだ瞬間、また文学賞に応募する! チャレンジを諦めるものかと思った。C君に「書き続けて」と言われたような気がしたのだ。そしてその翌年、僕は再び文学賞を受賞した。僕は作品の結びにこう書いた。
「僕にまた書く意欲をくれたC君に感謝の思いを伝えたい。C君本当にありがとう」と。
相変わらず僕には友達という友達はいない。でも「友情」という温かくて特別な感情は、様々な場面で綴られた言葉たちの力で知ることができたのだ。