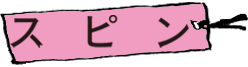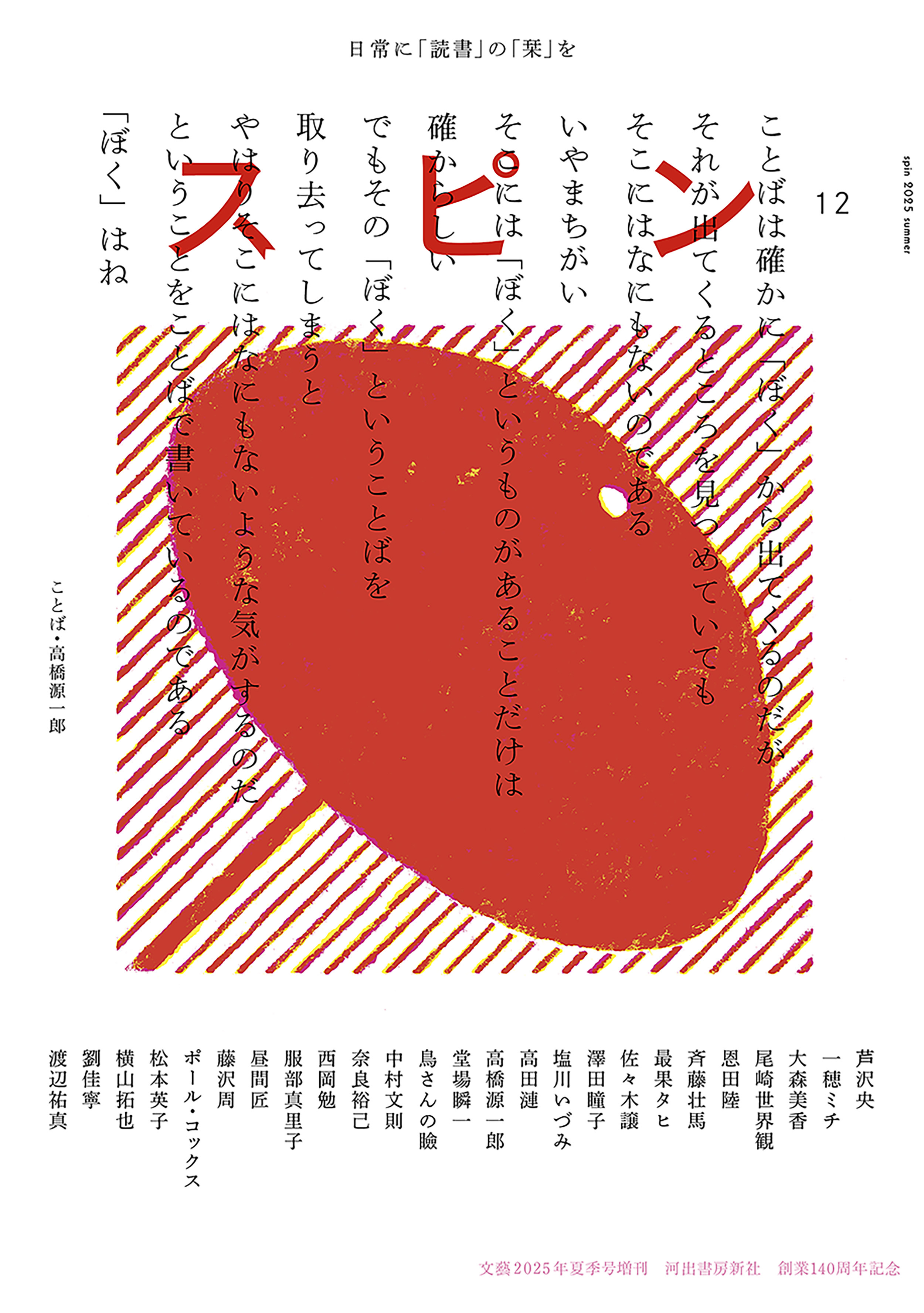路上の輝き 第5回
佐々木譲
2026.01.16

4
四月末の、ゴールデン・ウイーク直前のころだったろう。その前の日に奈津美から電話が来て、明日、月蝕洞で飲みましょうと誘われた。
修平は中堅どころの広告代理店への転職を果たして、ほぼ二年が過ぎていたところだった。同じグラフィック・デザインの仕事だけれども、それまでのような手作業の仕事は減っていて、むしろ打ち合わせや企画会議に出てプランを作ることに、比重が変わっていた。少し待遇もよくなっていたから、経済的にも時間にも、余裕ができていたと感じられていた。
転職先の広告代理店のクライアントには、それなりに大きな企業規模のところが多かった。扱っている商品やサービスも、出稿する媒体も、それまでよりも知名度や格が一ランク上がった。仕事を楽しめるようになっていた。
翌日の夜、月蝕洞に行くと、奈津美が先に来て、テーブル席で白ワインを飲んでいた。
修平が奈津美の向かい側の席でビールを注文して飲み始めると、奈津美が小さめのクラフト紙の封筒を渡してきた。
「お土産です」
言われて思い出した。奈津美は近々香港出張に行くと行っていたのではなかったか。香港の工場で打ち合わせがあるのだとか。上司について行くことになったと。
封筒の中身は、表紙がいかにも香港ふうのスケッチブックだった。サイズはA5くらいだったか。
「ありがとう」礼を言ってそのスケッチブックを押しいただき、奈津美に言った。「楽しい出張だった?」
「ええ。初めての海外で、初めての出張ですからね。まだハイな気分が続いています」
「昨日、帰り?」
「一昨日だった」
「出張なら、観光は全然していないんだね」
「そう。ただ、夜は向こうの取引き先のひとに接待してもらったり、会社のひととお酒を飲みに行った。わたし、今夜も浮かれてますから、目に余るようなら言ってね」
奈津美のその出張旅行の話を聞いているときに、冬樹がやってきた。
冬樹は奈津美の隣りに腰を下ろし、奈津美のグラスを見てから、自分も白ワインを注文した。
冬樹はグラスを持ち上げて言った。
「海外出張帰りのミミと飲める日は、予想よりも遅かった」
「もっと早いと思ってくれていたんですか?」
「それもパリへの出張から帰ってきた、って夜に」
奈津美が冬樹に土産を渡した。ブリキのペンケースだった。中国風の意匠ではなくて、ヨーロッパのアンチークっぽいデザインのものだ。もしかすると、スケッチブックと同じ文具店で買ったものかもしれない。
修平は言った。
「ぼくはまだパスポートも持っていない。そういう日は来るんだろうか」
冬樹が黙っている。修平の言葉に反応しなかった。
奈津美が冬樹のその顔を見て、言った。
「冬樹さん、行くんですね?」
奈津美の言葉に驚いて、修平も冬樹を見つめた。
冬樹がうなずいた。少し照れているような顔だった。
「じつは、決まった」
「どこですか?」
「ニューヨーク」
修平と奈津美は同時に感嘆の声を挙げた。
「わ」と奈津美。
「やった」と修平は言った。
「本決まりになる前に口にしてしまうと、運が逃げそうで言ってなかったんだ」
「いつ?」と修平が訊いた。
「九月から。早めるかもしれない」
奈津美が確かめた。
「から、って言うのは、長くってことですか」
「一年半」
「すごい」
冬樹は、とある公的機関の名を出して言った。
「じつは、大学院のときの指導教授がぼくを、芸術家等海外研修制度に推薦してくれていたんだ。こっちの方面に少し力のある先生だったんで。ぼくも自分がこういう年であることは不利と承知で、申請書を出していた。で、きょう、知らせが来た。一年半、ニューヨークで勉強してくる」
冬樹は以前から、機会があればロンドンか、でなければアメリカの東海岸の都市に長めに滞在してみたいと口にしていた。ほんとうは大学時代にその夢を真剣に追うべきだったのだろうとも言っていたことがある。こういうことを夢見るのが遅すぎたと。ただ、とくに具体的な計画や予定を話したことはなかった。でも。
奈津美が早口で質問した。
「学校に入るんですか?」
「ニューヨーク大学芸術学部の演劇プログラムの聴講生になる。一応向こうで面接試験があるんだけど、ぼくは実績のあるプロだから大丈夫らしい。劇作と演出のコースを聴く。通っているあいだに、実作もやることになるんだと思う」
ニューヨーク大学は、マンハッタンの南、ワシントン広場の周辺にいくつもの校舎を持つ、キャンパスを持たない大学なのだという。芸術学部では映画学科も有名で、ハリウッドの監督の中にもここの映画学科出身者は多いのだ、と冬樹は教えてくれた。
奈津美が訊いた。
「ニューヨークでは、学生寮とかに住むんですか?」
「マンハッタンは住宅事情がひどく悪いらしいんで、部屋をシェアして暮らすとか、ブルックリンに部屋を借りることになるかもしれない。行ってから決める。決まるまでは安ホテル滞在」
「いるあいだは、生活費も出るんですね?」
「無制限にじゃないけど、勉強が続けられるだけのおカネは出る」
「一年半?」
「おカネが出るのはね。だけど、学生ビザは期限が五年。おカネが続くなら、もう少しいてもいいな。せっかくのニューヨークなんだから」
「あたし、冬樹さんがいるあいだに、ニューヨークに行きます。歓迎してくれますか?」
「地元のビールをごちそうするよ。何杯でもいい」
奈津美は修平に顔を向けた。
「修さんも一緒に行きますよね。三人が向こうで会うのって、すごく楽しそう」
「行くよ」
冬樹が言った。
「向こうの小劇場とか、タイムズ・スクエア近辺の芝居関係者の酒場とかを知っておいて、案内しよう」
修平は少し心配になって訊いた。
「劇団はどうなる? せっかく立ち上げたのに」
冬樹は答えた。
「じつはいま、さいわい一時休止状態なんだ。みなの都合が合わなくて、次の公演を延期している。いまなら、行ける。帰ってきたら再開する」
奈津美が訊いた。
「冬樹さん、東京のアパートはどうするんですか。一年半、空けておくの?」
「家賃を払いきれない」と冬樹が答えた。「引き払うしかないよな」
「いないあいだ、あたし、住んであげてもいいですよ。家賃は払います」
「そういうわけにはいかないよ。家具や本は甲府に送って、スーツケースふたつぐらいでニューヨークに向かう」
「そうですか」
冬樹がニューヨークに出発したのは、七月の初めころだ。予定を少し早めたのだった。聴講生になる前に、語学学校に入って耳慣らしが必要だから、と冬樹は言った。
出発が日曜日だったから、成田空港まで、修平は冬樹を見送りに行った。ノースウエスト航空のカウンター近くには、すでに冬樹と奈津美が来ていた。ほかに見送りの友人の姿のないのが意外だった。
「毎晩、壮行会をやってもらっていたから」と冬樹が言った。「アルコール漬けだった」
冬樹はスーツケースをふたつ足元においていた。ひとつは知人からもらったという古い布貼りのもので、もうひとつは新品の、胴のふくらんだ形のものだった。機内持ち込み用の大きめのショルダーバッグを肩にかけていた。
手荷物検査のゲートに入るところで、奈津美が冬樹に言った。
「手紙でなくてもいいけど、絵ハガキはくださいね」
冬樹は笑って応えた。
「自由の女神のを送るよ」
「向こうで居ついてしまわないで」
「それは約束できないぞ」
「いるあいだに絶対に訪ねていきますから」
奈津美が両手を広げた。冬樹も両手を広げ、ふたりはハグした。
「行ってらっしゃい」
「行ってくる」
ふたりが離れてから、修平も冬樹に言った。
「強盗に遭わないように」
「気をつける」
冬樹の姿が手荷物検査場へと消えたあと、修平たちは上野行きの京成線で都内まで帰った。修平は奈津美に、早めにお酒を飲まないかと誘ったけれども、奈津美はやめておきますと断って、ふたりは日暮里駅で別れた。
そのあと修平が奈津美に月蝕洞で会うのは、その年の暮れのことになる。ほぼ五カ月会わなかったのだ。
部屋から奈津美にメールを入れた。
「名古屋で小休止中」
五分ほどで返信があった。
「きょうが最後のライブの初日。もう少しで開演。てんやわんや。冬樹さんの調子は?」
奈津美は、冬樹とは直接やりとりはしていないようだ。
これに返信した。
「快調ではないけど、旅に支障はないよ。冬樹さんはどこでも感慨にひたっている」
「いい旅を。無理をせずに」
末尾に、ハートの絵文字。
時計を見ると、まだ三時十五分だ。冬樹から夕食なり今夜の予定で電話がかかってくるのは、たぶん小一時間は後だろう。部屋で彼は少し眠るかもしれない。朝に服んでいた鎮痛剤にはたぶん、眠気を誘う作用があるはずだ。浜松のホテルをチェックアウトした後、彼はうとうととさえしていなかった。体力の落ちている身ではそろそろ眠くなってきていておかしくはないのだ。
修平も上着を脱いで、その小さな部屋の窓際の、肘掛け椅子に腰かけた。
きょう名古屋に来たが、冬樹とは違い、自分自身はあの七ツ寺共同スタジオで冬樹演出の芝居を観た以外は、たいして思い出はなかった。
あの翌日は、奈津美と別れた後、市の中心部を歩き、描きたくなるような建物や喫茶店などを探した。戦災が大きかった都市だから、期待していたほどにモチーフとなるような建物には遭遇できなかった。そもそも繰り返された空襲で、名古屋駅も名古屋城も焼けているのだ。市の中心部からは、戦前の建物はほとんど失われているという。もちろん犬山市にある明治村まで足を伸ばせば、全国から移築された明治期の建物があったが、このときはせっかくの事実上初めての街なのだから、名古屋市の中心部を歩いてみたかったのだ。
名古屋についての思い出は少ないが、きょう冬樹が口にしたいくつかの言葉から、むしろ修平は奈津美と一緒に冬樹をニューヨーク市に訪ねたときのことを、さまざま思い出していた。
訪ねたのは冬樹がニューヨークに行ってちょうど一年経ったころ、八四年の夏だ。冬樹が行ってから数通エアメールをもらっていたが、四月ころの手紙に彼は書いていた。
「クラスの終了公演が六月にある。ぼくも聴講生なんだけど、制作に参加している。この時期にニューヨークに来ないか。公演を観てもらって、そのあとはニューヨークで遊ぼう」
いつのまにか、冬樹の住所が変わっていた。以前もマンハッタンの南のエリアだったが、引っ越し先もやはりマンハッタンの南のようだった。
同じ中身の手紙が奈津美にも届いた。修平は奈津美と打ち合わせ、有給休暇を取って彼女とふたりでニューヨークに行くことにした。修平も奈津美も、もう仕事や観光で海外には何度か旅行していたが、ニューヨークは初めてだった。
5
修平と奈津美がニューヨーク市のジョン・F・ケネデイ空港に着いたのは六月半ばの木曜日だった。午後の三時過ぎの到着だったろうか。
混雑する到着ロビーでは、冬樹が待っていてくれた。
彼は日本にいたときとあまり印象の変わらない黒っぽい服装だった。ただ、髪は東京にいたときよりもさらに伸ばしていた。
冬樹が修平たちを見つけ、顔を輝かせて両手を広げた。奈津美がスーツケースを押しながら冬樹に向かって駆け、冬樹のすぐ前でスーツケースから手を離して冬樹と抱き合った。少し遅れて修平は冬樹たちに近づき、奈津美のスーツケースに手をかけて、ふたりが離れるのを待った。
冬樹が奈津美の背を軽く叩くと、奈津美が両手を下ろした。
冬樹が近づいてきて修平に言った。
「はるばるようこそ」
修平は訊いた。
「調子は?」
「まあまあだ」
「かなりこっちに慣れたってことだよね」
「とんでもない。いまだに言葉もよく通じないお上りさんだ」
「だって、お芝居を上演するのに」
「クラスの卒業公演だ。ぼくの芝居じゃない。ちょっとアドバイザー的に関わっている」
「演出助手とか?」
「ぼくは一応実績もあるプロってことで、若い学生たちにときどき助言をする程度さ。こんどの公演でも、稽古の途中で教授がぼくに意見を聞いたりもしてきたけど」
奈津美が冬樹に言った。
「きょう、忙しいんじゃないんですか?」
「うん、ふたりをホテルまで送る。それからいったん稽古場に戻る。夜は少し遅くから一緒に食事、ってことでいいかな」冬樹はロビーの出口の方を指さした。「マンハッタンまで、タクシーで行こう」
「マンハッタン、って言い方をするんですね。ニューヨーク・シティじゃなく」
「うん。あの島はマンハッタン区。ここはクイーンズ。ホテルは、ヴィレッジのホテル・アールでよかった? ウェーバリー・プレイス」
修平は、バウチャーを取り出して見ながら答えた。
「ワシントン・スクエアの西側だそうだ」
「場所は悪くない。大学の校舎も、ワシントン・スクエアの西とか南に固まっているんだ。そのホテルには泊まったことはないけど。とにかく向かおう」
空港ビルを出て、タクシー乗り場に並ぶ黄色いタクシーの先頭に歩いた。黒人のドライバーに冬樹がホテルの所在地を告げた。さすがと思える発音だった。黒人ドライバーはうなずき、修平たちのスーツケースをトランクルームに入れてくれた。三人は後部席に並んで乗った。真ん中に奈津美、左側に修平、右側に冬樹だった。
走り出してから、冬樹が言った。
「きょうはたぶんよく眠れないだろうと思う。芝居は明日の午後二時と七時。二回なんだ。どうしても東から来る場合は時差ぼけになる。きょうは早めに、風邪薬でも持ってきたらそれを飲んで眠って」
奈津美が訊いた。
「どうして風邪薬を?」
「睡眠薬になる」
「それは不健康」
「もうひとつ対策。明日は朝から紫外線を浴びる。でも朝から歩き回って疲れないよう気をつけて。それと、きょうは食事のとき、あまりお酒を飲まないほうがいいな。ぼくの体質だとそうだ」
「わたしたちが観るのは、ソワレですか?」
「いいや。マチネを観てほしい。上演時間は三十五分。終わったあとまた会って、ぼくはソワレのほうにも立ち会う。夜にまた合流しよう」
「明後日は?」
「明後日からは、ぼくができるだけニューヨークらしいところに案内する。ただし、自由の女神は行ったことがない。あそこは勘弁して」
「冬樹さんにツアー・コンダクターをしてもらうのは恐縮だ。ぼくら、昼間は勝手に歩いて、夜を三人一緒になるのはどうかと考えてきたんだけど」
「いいな。昼間、ミミは昼間行きたいのはどこなの?」
「MoMAですね。あと、ウエスト・ヴィレッジってところを歩きたい」
「お洒落な街だ」
「そこって、グリニッチ・ヴィレッジと一緒ですか?」
「グリニッジ・ヴィレッジの一部が、ウエスト・ヴィレッジって呼ばれているな。公的な地名じゃないはずだけど。修平さんはどこに行くつもりなの?」
「自然史博物館が楽しみなんだ。美術館もいいな」
「博物館と美術館めぐりだけでニューヨークを終えてしまうのも、つまらなくないかな」
「五泊六日では、絞り込まないと」
「ま、一日歩いてみたら、面白そうな場所がほかに思いつくかもしれない」
「柔軟に考えるよ。夜は、冬樹さんに、よく行くレストランとか、ここで飲んでいる、って店に連れていってもらえるとうれしい」
「そのつもりなんだ。いくつかなじみの店もできた。高級店には無縁だけど、客が面白い月蝕洞みたいなお店もある」
タクシーは空港から高速道路に入った。高速道路の左右に見えるものは、最初は郊外型の住宅地かと見える風景だった。やがてビルが多くなり、アメリカ映画によく出てくる、マンハッタンの高層ビル街ではないニューヨークの風景となった。
奈津美が冬樹に訊いた。
「冬樹さんが住んでいるのは、東五丁目でしたっけ? どういうところなんです?」
「イースト・ヴィレッジだよ。東五で、セカンド・アヴェニューとサード・アヴェニューのあいだ。大学に近くて、歩いて行ける。ミミたちのホテルから、ワシントン広場をはさんで東のほう」
「冬樹さんからそんな地名を聞くだけでくらくらします。あ、ほんとにニューヨークに来たんだって」
「それを意識して言ってるよ、もちろん」
「マンハッタンって、家賃が高いって行く前に言っていましたよね」
「イースト・ヴィレッジは安いほうだ。でも、さすがにシェアして住んでるんだ。三、四カ月前から」
「ああ、それで住所が変わったんですね。シェアは、何人かと?」
「もうひとりと」
奈津美は質問を続けず、冬樹もつけ加えなかった。少しのあいだ、タクシーの中に沈黙があった。
奈津美は質問を変えた。
「ウェスト・ヴィレッジを昼間歩くとして、お勧めのところってあります?」
「あるよ」と、冬樹は答えた。「メモの用意はいいかな」
「あとで教えてください」と、奈津美が言った。わずかに感情が消えたような声だった。
その旅行の手配は、旅行代理店を通じて修平がした。ノースウエスト航空のエコノミー・クラスでの往復で、ホテルはニューヨーク大学の校舎が集中するワシントン広場の近くに取った。ホテル・アールという、三つ星級の小さなホテルだった。旅行代理店が決めてくれた。代理店の女性担当者には、旅行の目的と自分たちの職業は伝えていたので、けっこう面白がってホテル選びをしてくれたようだった。
その担当者は言った。仕事での出張ならミッドタウンのビジネス街のホテル、観光ならブロードウエイ周辺のホテルがいいらしい。でもニューヨーク大学に演劇留学している友人に会うことが主眼であれば、グリニッチ・ヴィレッジの中にあるこのホテルがよいかと思いますと。建物は古いし、ディナーの出るレストランもない規模のホテルだけれど、そのぶん宿泊料金もリーズナブルとのことだった。
その担当者は、部屋をふたつ取ることを奇妙に思ったようだった。一回だけ確認された。ツインのお部屋でなくてもいいのですね?と。
シングルをふたつ、と修平はあらためて言った。奈津美とはそうすると話していた。というか、あの場合はそれ以外の旅行の方法は考えられなかった。
クイーンズからマンハッタン島に入るには、どれかの橋を渡るのだろうと期待していた。たとえばブルックリン・ブリッジとか。でも高速道路はイーストリバーの地下を潜った。トンネルを出るともうマンハッタン島だった。
マンハッタン島の南の街路の様子を食い入るように眺めているうちに、タクシーはホテルの前に停まった。建物は十一階建てと案内を読んでいた。間口が意外に狭い建物だった。
チェックインまで、冬樹が付いてきてくれた。修平と奈津美がバウチャーをそれぞれ出してフロントの係に渡すと、冬樹がもらした。
「別々に部屋を取った?」
「うん」と修平は答えた。
「シェアすればだいぶ安上がりだったのに」
奈津美が笑うように言った。
「そういう問題じゃないですよ」
奈津美が六階の部屋、修平は四階だった。ふたりがキーを受け取ったところで、冬樹が言った。
「じゃあ、とりあえずひと休みして、この周辺の散歩でも。ワシントン・スクエアは、夜になると危ないと言われているんで、暗くなったら入らないほうがいいな」
時計を見ると、まだ四時半だった。
修平は訊いた。
「夏至だから、夜になるのは遅いよね?」
「日の入りは八時過ぎかな」
「ずいぶん遅いんだ」
「サマータイムだし」
「冬樹さんとはここで待ち合わせる?」
「うん。そのほうがわかりやすいだろう。九時には来れる」
冬樹は手を振って、ホテルを出ていった。
修平は奈津美と一緒にエレベーター・ホールへと歩いた。
修平はエレベーターを降りるところで、奈津美に言った。
「じゃあ、後ほど」
奈津美が微笑して手を振った。
九時五分前にロビーに下りてゆくと、すでに奈津美がいた。ソファに腰を下ろしている。夜のお酒の場を意識したと見える服装だった。半袖のブラウスに膝丈のスカート、ジャケットを手にしている。修平は、半袖の麻のシャツに着替えていた。チノパンツは、飛行機に乗ったときのままだ。
奈津美が訊いた。
「どこに行きました?」
修平は答えた。
「この回りを歩いただけ。ワシントン広場と、それから西のほう」
「わたしも同じです。ワシントン広場で、PPMみたいな組み合わせの三人組が路上ライブやっていましたね」
「いたね。若いひとたち」
「ちょっと聴いていました。『トライ・トゥー・リメンバー』を歌っていた」
「ダークダックスの?」
「もともとは、ミュージカルの曲ですね。好きな曲です」
そのとき、エントランスのドアが開いた。
冬樹が入ってきた。女性連れだ。冬樹より少し若いかと見える歳で、背は奈津美ぐらいだろうか。髪はかなり短めだ。快活そうな顔だちで、日本人のように見えるが、ファッションはあまりその年齢の日本人女性っぽくはなかった。細身のブルージーンズに、黒いタンクトップ。ファッションのセンスは、冬樹にどことなく似ている。
冬樹がにこやかに近づいてきて言った。
「四人で行くよ」
冬樹が連れの女性を見ると、彼女は奈津美に一歩近づいて日本語で言った。
「はじめまして。レイコです。礼儀正しい、の礼子です」
微妙に訛りがあった。
奈津美も、礼子と名乗った女性に自己紹介した。
「奈津美です。こんにちは」
「ミミさんですね」
奈津美は戸惑ったような顔となった。その愛称は、冬樹と奈津美とのあいだだけで使われるという思いがあったのかもしれない。
「ええ」と奈津美は言った。「奈津美と呼ばれることのほうがふつうです」
冬樹が修平を礼子に紹介した。
「及川さん。修平」
「はじめまして」と修平も礼子にあいさつした。
礼子が修平と奈津美を交互に見ながら言った。
「おふたりのことは、ドンからよく聞いていました」
「ドン?」と奈津美。
冬樹が言った。
「ぼくの堂内冬樹って名前は、そのままではこちらの友人たちには発音しにくい。いつのまにか名字から、ドニーって呼ばれるようになったんだ」
修平は訊いた。
「ぼくらもそう呼んだほうがいいかな」
冬樹は笑って首を振った。
「いままでどおりで」
奈津美が礼子に訊いた。
「礼子さんは、グリーンカードで滞在中ってことなんですか?」
礼子が答えた。
「こちらで生まれたので、わたしはアメリカ国籍なんです。日本語を話すのは、両親とも日本人だからです」
冬樹が言った。
「礼子はボストン生まれなんだ。フルネームは、イレイン・レイコ・サイトウ」
ということは、両親は戦後早い時期に移民した日系一世ということか。両親がともに二世だと、日本語はあまりうまくはならないだろう。五十年代にボストンに移民とか長期滞在した両親となると、親のどちらかは何かの研究者なのかもしれない。
「日本にも」と礼子が言った。「いたことがありますよ。大学を出たあとに一年」
奈津美は冬樹に顔を向けて訊いた。
「礼子さんは、お芝居の関係の方?」
「いや。映画。いまはドキュメンタリーの仕事をしている」
礼子が言った。
「ドキュメンタリーの仕事がないときは、日本の映像プロダクションで、編集の仕事をしています」
「冬樹さんとは、お芝居を通じて?」
冬樹が答えた。
「イースト・ヴィレッジでなんとなく知り合った。いまはルームメイトなんだ」
礼子が、違う、とでも言ったような表情となり、右手の拳で冬樹の横腹を突いた。
「ま、ルームメイト以上か」
その台詞まで冬樹は用意して、礼子を紹介したように聞こえた。
「ああ」と奈津美が礼子を見て微笑した。「そうなんですね」
冬樹が礼子に言った。
「礼子、忘れないうちに」
礼子がショルダーバッグから、A4サイズの紙を取り出して言った。
「明日のドンのお芝居」
冬樹が説明した。
「芸術学部が持っている小劇場での上演なんだ。場所はワシントン・スクエアの、ツーブロック東。わかりやすいところだ」
「脚本はオリジナル?」
「学生のコンペで、投票で上演作が決まった。ある家族の子供のひとりが、サンクスギビングにゲイであることを告白する話」
「冬樹さんは、出演は?」
「しないよ」
冬樹が時計に目を落としてから言った。
「これから行くところ、軽食しかないけど、雰囲気がいかにもヴィレッジなんだ。軽食でいい?」
「十分」と修平は答え、奈津美もうなずいた。
「ここから五分くらい歩く」
「どんなところ?」
「イタリアンのカフェ。ギンズバーグやケルアックが常連だったそうだ」
「文壇カフェ?」
「そういうのじゃないな。とにかくこのあたりの面白そうなひとたちの溜まり場になっている。カフェって名乗っているけど、ビールもワインも飲める。いまごろ行くと、賑やかで圧倒される」
ホテルを出てから、ワシントン広場の西側の通りを南に向かって歩いた。
歩きながら、奈津美が冬樹に、ワシントン・スクエアで三人組のフォークバンドが『トライ・トゥー・リメンバー』を歌っていたことを話した。
冬樹が言った。
「あそこで聴くには最高の曲だ。『ファンタスティックス』をやっている劇場が近くだ」
「そうなんですか!」
「うん、ずっとロングランなんで、劇場のある小路を、ファンタスティックス・レーンって言うんだ。ぼくも観に行ってる」
「面白いですか?」
「ま、題材は通俗だけど、演出は日本の小劇場にも通じるところがある」
「行きたいな。案内してくれますか」
「あとで予定を整理しよう」
冬樹が連れていってくれた店は、ホテルから遠くはなかった。五ブロックも歩いたところで、その店カフェ・レッジオに着いた。初夏の金曜の夜のせいか、店の前の歩道にもテーブルが出ていて、すべて客で埋まっていた。ビール瓶を手にして立って飲んでいる者も多かった。
店の中に入ると、店のロゴタイプ入りのエプロンをつけた若いウェイトレスが冬樹に近づいてきた。礼子があいさつした。彼女も常連客なのだろう。
冬樹がウェイトレスに言った。
「話したVIPさんたちだ」
奥のテーブルがひとつ、予約席として確保されていた。
ウエイトレスが冬樹に、ちょっと不満そうな顔で何か言って離れていった。
「何か?」と修平は訊いた。
「あと一分遅かったら、予約はキャンセルってことになってたそうだ」
「すごい混みようだね」
テーブルに着いて、修平はビール、ほかの三人は赤ワインで乾杯した。
乾杯した直後には、自分たちと同年代かと思える白人がテーブルまで歩いてきた。長髪で黒いセルフレームの眼鏡、コットン・ジャケットを着ている。修平の勤務先にも、雰囲気の似たコピーライターがいた。彼もたぶんそのような仕事だろうと思える印象があった。その男は修平たちに会釈してから、冬樹とふたことみこと話すと、入り口のほうへと戻っていった。
修平は冬樹に訊いた。
「お芝居関係者?」
「詩人」と冬樹が答えた。「高校でアメリカ文学を教えている。ヴィレッジのカフェで朗読会もやってた。明日の公演には行けないって、謝っていった」
トーストや卵焼きの軽食を食べながら、修平たちはその満席の店の中で話した。一年ぶりの、しかも修平も奈津美も知らない街で暮らしている冬樹との会話は盛り上がった。礼子も、楽しげに聞いている。冬樹が彼女には語っていない事実も知ることになったのだろう。
修平は冬樹のニューヨーク派遣の生活の細部をいろいろと聞いた。どんなことを、どんな学生たちと一緒に、どんな人物から学ぶのか。冬樹には何か新しい発見や学びのある講座なのかどうか。言葉の問題はないのか、日本の演劇論や演出技術と違うところはあるのか?
「言葉には苦労した」と冬樹は苦笑しながら言った。「もう少し聞き取れるつもりでいたのだけど、呆然とするぐらいにわからなかった。最初は講義の三分の一も聞き取れたかどうか。しかもレポートを出せば、講師からきみの英語は十九世紀のものだと笑われたりする。ぼくは聴講生になる前に二カ月、ニューヨーク大学の英語学校に通って耳慣らししたのに」
「いまは?」
「まだ、不自由なく会話ができるレベルには達していない。ただ、発音はいいらしい。少し話しただけだと、初対面のひとはぼくが英語をふつうに話せる男だと勘違いしてくれる」
講義の内容については、冬樹は言った。
「ぼくはそもそも、演劇について学んだことがない。シェイクスピアは戯曲として読んだのであって、芝居の台本として接したわけじゃなかった。演劇論も戯曲の解釈も演出のセオリーも、教えられたのはどれも新鮮なことばかりだ」
話しているあいだにも、何人か冬樹の知り合いがテーブルまで歩いてきてあいさつしていく。礼子の知り合いも何人かいたようで、礼子は十分ばかり修平たちのテーブルを離れていたこともあった。
そのあいだに、奈津美が冬樹に訊いた。
「じゃあ、まだまだ日本には帰れないですよね。あと半年いられるんでしたっけ?」
「滞在費は出るんだ。学生ビザは五年あるから、自分の希望次第ではいられるよ。聴講生を続けるかどうかはともかく」
「決めていないんですか?」
「明日の公演の評価を見て決めようと思っている。指導教授が、公演の後、話をしたいと言っているから、話題はそれだろうな」
修平は、少し羨望を覚えながら言った。
「せっかくこの暮らしを楽しんでいるんだ。事情の許す限りいてもいいな」
奈津美が言った。
「いっそこっちで演出家になってしまうとか」
冬樹は首を振った。
「無理だ。十年前なら、それを考えたかもしれないけれど、ここでは毎回の公演を、世界スタンダードでやらなきゃならない。客の目も肥えている。いまは自分が追いつけるかどうかもわかる。言葉の問題もあるし、東京に残してきたものも惜しい。帰るよ」
修平は言った。
「劇団は事実上解散しているじゃないか」
「人脈はなくなっていない。あれだけのものをもう一回ここで築くには、あと何年かかるかわからないし」
それでも冬樹の口調はどこか、自信と楽観があるようにも聞こえた。ただ、いまこの時点では見極めがついていない、というだけで、このままこの街に残ってもいい、とひそかに思っているようにも感じられたのだった。
「じゃあ、いつかは帰ってくるんですね」と奈津美。
「ああ。それは確実だ」
礼子が戻ってきて言った。
「マイクたちが来てる。こっちに来ないかって言われたけど、どうする?」
冬樹が礼子に訊いた。
「椅子はあるのかな?」
「ちょうど隣りが空いた」
冬樹が修平たちに訊いた。
「知り合いが来ている。せっかくだから合流するかい?」
修平は躊躇した。
「何もしゃべれない」
「礼子が通訳してくれるよ」
奈津美が言った。
「わたし、賛成」
「行こう」と冬樹が立ち上がった。
修平たちも立ち上がって、冬樹や礼子の知り合いらしいそのグループに合流したのだった。
マイクという男は、ジャーナリストで地元紙にもパフォーミング・アート関連の記事を書いているという。彼と一緒に来ていた黒人女性は、ファッション業界紙の編集者とのことだった。
カップルで来ていた白人男女は、男のほうがダンサーで、インストラクターでもあった。女性のほうは舞台俳優だが、パートタイムの仕事はしていると聞いた。ふたりは自分の出演したミュージカルのタイトルを教えてくれたが、ビールのせいもあったか、修平は覚えられなかった。
彼らに、礼子が自分のショルダーバッグから翌日の公演の案内を取り出して渡した。
「よければ来てください」と。
もちろんその場でのやりとりは、礼子と冬樹の通訳に頼ったのだった。
その席には、まだまだ何人もの客があいさつに来てはあいさつし、ときにハグし合ったり、紹介されて握手したりがあった。修平は時差ボケを心配してあまり飲まないつもりだったけれど、それでもビールの小瓶で数えて五本以上は飲んだはずだ。奈津美も、赤ワインをずいぶん飲んでいたように見えた。
十一時を回ったところで、マイクが言った。
「そろそろぼくらは行くが、楽しかった」
修平たちも、そこで引き揚げることにした。
ホテルまで冬樹たちが送ってくれた。 礼子が奈津美をハグして、明日またね、と言い合っていた。
エレベーターに乗ったとき、奈津美を見た。奈津美は、上気しているように見えた。しかし同時に、それに戸惑っているようにも見えた。
奈津美は修平の視線を受け止めて、苦笑したような顔で言った。
「冬樹さん、楽しんでいるね」
修平はうなずいた。
「馴染んでいるね」
エレベーターのドアが開いた。
「おやすみ」と言って、修平はエレベーターを下りた。
翌朝は四時に目が覚めた。二度寝しようと思ったけれども、頭が熱かった。けっきょくそのままシャワーを浴びて、スケッチブックを持ってウエスト・ヴィレッジを歩いた。六時過ぎにホテルに戻ってくると、七時には朝食を取るために食堂に下りた。小さな食堂で、コーヒーとパンとチーズが出るだけだった。隅のテーブルで一時間待ったが、奈津美は下りてこなかった。いや、奈津美もまた修平同様に眠れず、街を歩いているのかもしれなかった。
修平は食堂を出ると、こんどはワシントン・スクエアに向かって歩いた。
スマートフォンに着信があった。
冬樹からだった。彼が言った。
「修さん、いま部屋かい」
「ああ。隣にいるよ」
「ちょっと手伝ってくれないかな。鎮痛剤のテープを貼りたいんだけど、背中なんでうまく貼れない」
「いま行く」
冬樹の部屋の前まで行くと、彼がドアを受けから開けて言った。
「つまらないことですまない」
冬樹は白いアンダーシャツ姿になっていた。ズボンは穿いたままだ。
「痛むのかい?」と修平は冬樹を見つめた。苦しいのをこらえている表情とも見えなかった。
「痛み出す予兆程度なんだ。急性膵炎じゃない。でも、早めに鎮めてしまいたい。まだ二日ある」
冬樹は奥へと歩き、テープの袋を修平に渡してきた。
「うつ伏せになるんで、背中に貼ってもらえるかな」
「どのあたりだろう」
冬樹はアンダーシャツを脱いだ。
一瞬修平は息を飲んだ。冬樹は想像以上に痩せていた。もともと筋肉の少ない細身の体型だったけれど、いまはろくに皮下脂肪もなくなったいる。さすがに肋骨が浮いているほどの痩せ方ではないけれども。しかし修平は驚きをなんとか抑えこみ、顔には出さなかった。出せば冬樹は、自分の体調が自覚している以上に悪いのかと不安になるだろう。
冬樹は後ろ向きとなり、修平に背中を見せ、胃の真後ろだろうかというあたりに右手を持っていった。
「このあたりなんだ。自分でやると、ときどきテープをぐちゃぐちゃにしてしまう」
素早く背中全体を見たが、修平が想像する不健康の証のようなものは見当たらなかった。黄疸も、浮腫も腫瘍もない。少したるみ、乾いているようだという印象がある程度だ。医師の目には見えるものがあるのかもしれないが、少なくとも自分には、明らかに重篤な病気を持っている人物の肌とは感じなかった。
冬樹がベッドにうつぶせになった。
修平は冬樹の裸の背中、いま冬樹が手で示した場所に、強く押したりしないよう注意して沈痛消炎剤であるテープを貼った。
「ありがとう」と冬樹は身体を起こし、アンダーシャツを着直した。
修平は言った。
「お風呂のときは剥がすんだよね。そのあと、また貼るよ」
「いや、明日の朝、シャワーを浴びる。それまでこれでいい」
「ほんとうに、この旅行、大丈夫?」
「耐えがたくなったら、意地は張らない。降参して修さんに助けを求める」
「夕食は、外に行けそう?」
「六時まで休めば十分。せっかくの名古屋だし、きしめんを食べたいな」
「ひつまぶしという手もある」
「麺だ」
「じゃあ、六時にロビーで」
部屋のドアへと向かおうとすると、冬樹が言った。
「名古屋にいるのに、どうしてかニューヨークのことを思い出していた」
修平は笑った。
「ぼくもだ。どういうわけだったんだろう」
「何かキーワードがあったんだな」
修平はうなずいて、あらためてドアへと向かった。
修平は奈津美、礼子と三人でその上演を観たのだった。客席が百ほどのフラットなスペースで、ステージ部分に幕があるわけではなかった。客席はパイプ椅子で、奥の席だけは日本で言う平台の上に設けられていた。
客は八割の入りで、観客は学生がほとんどと見えた。学内公演だからか、無料だった。
登場人物が五人で、ひとり母親役だけは外部からの客演だったけれど、一幕の淡々とした会話劇だった。セットは、アメリカの労働者階級の家の居間で、椅子とソファがあり、隅のテーブルにはサンクスギビングの飾りつけがしてある程度の舞台美術だった。
何度か客席で笑いが起こったことがあったが、修平は台詞がまったく聞き取れず、楽しめたとは言えなかった。終わったときも、スタンディング・オベーションが起こったりはしなかった。観客は礼儀正しく、まあまあだね、という雰囲気で拍手をし、俳優やスタッフたちに声をかけて、そのフリースペースを出ていった。学生が中心の観客たちには、可もなく不可もなくという評価だったのだろう。
冬樹が舞台の袖から出てきて、修平たちに訊いた。
「どうだった?」
礼子が真っ先に答えた。
「最高だった! 素晴らしかった」
修平は苦笑して答えた。
「粗筋を聞いただけだったから、ニュアンスがわからず、チンプンカンプンだった」
「話はわかったろう?」
「流れは」
奈津美が言った。
「最後に何かどんでん返しがあるのかと思っていた」
「どんな?」と冬樹。
「全員が何か家族に秘密を持っていて、それをみんなが告白して、お兄さんのゲイだということがどうでもよいことになるのかなって」
「コメディになってしまうな。そういう脚本ではなかったんだ」
「家族がゲイであるってことは、やっぱりニューヨークでもショックなことなんですか?」
「これの舞台は、ノースカロライナなんだ。ちょっとまだ保守的な土地の話だから」
スタッフや俳優陣たちが次々と冬樹に何か話かけていく。冬樹はいったん修平たちのそばから離れたけれども、すぐに戻ってきて言った。
「今夜もう一回上演がある。その後にみんなと打ち上げがある。九時くらいには、お酒を飲みに行ける。どこかで待っていてもらえるかな」
奈津美が言った。
「わかるところは、昨日のカフェ・レッジオだけ」
「今夜はイースト・ヴィレッジにしよう」冬樹は礼子と話してから言った。「グレート・ジョーンズ・カフェ。九時。いや、もう少し遅くなるかもしれないけど」
礼子も、夜の公演を観てから冬樹と一緒にそのカフェに向かうという。となると、合流までずいぶん時間がある。
奈津美が修平を見て言った。
「修さん、それまでウエスト・ヴィレッジを歩きませんか」
修平はその誘いに戸惑って言った。
「夜だけ一緒に過ごすってことでなくてもいいの?」
「うっとうしくなったら、そこで別行動にしてもいいし」
冬樹が言った。
「そうしてくれ。明日からは、希望なら一緒に過ごせる。案内もできる」
礼子が言った。
「覚えてください。グレート・ジョーンズ・カフェ。グレート・ジョーンズ・ストリートです。バワリーとラファイエット通りのあいだ。赤い壁」
冬樹が言った。
「去年できたばかりの店だけど、とても人気だ。アーチストとか詩人、ロックをやってる連中とか」
礼子がつけ加えた。
「ケイジャン料理の店です。大丈夫ですか?」
奈津美が訊いた。
「ケイジャン料理って?」
「南部の庶民料理ですね。ルイジアナ発祥。お米が主食」
修平が確認した。
「わかりやすいところだよね。もしはぐれたら?」
冬樹が言った。
「ホテルに伝言を残す」
修平たちは九時に再合流することにして、いったん別れた。
ビルの前の歩道をワシントン・スクエアに向かって歩きだすと、奈津美が言った。
「修さん、きょうはどこに行きました?」
「自然史博物館」と修平は答えた。「気がついたらお昼だったので焦った。奈津美ちゃんは?」
「MoMAに行って、わたしもあっと言う間に時間が経っていたのであわてて地下鉄に乗った」
「お昼は食べたの?」
「ううん。九時にケイジャン料理を食べるまで時間がだいぶありますね。何か食べますか」
「ピザは?」
「ニューヨークで最初のピザ。いいな」
「ピザならたぶん、どこにでもあるよね。ウエスト・ヴィレッジで、適当に探そう」
ゆっくりと町並みを眺めたり、ショーウィンドウを覗いたりしながら、ウエストヴィレッジを三十分ほど歩いた。高層ビルは目立たず、四階建てか五階建て程度のビルが並ぶその地区は、たたずまいも落ち着いていて、マンハッタンという言葉から連想できる町並みとは、少し違っていた。レンガ造りの壁の建物が多いので、ヨーロッパの町の景観とも違うのだろう。スーツ姿もさほど多くはない。
途中、それぞれが何かに目に留めて立ち止まったり、方向を変えれば、もうひとりもそれに合わせるという散策となった。奈津美のほうが修平よりもずっと、立ち止まることが多かった。
西方向へ向かっているうちに、タバコの大きな看板が目につく交差点に出た。ガイドブックで確かめると、ウエスト・ヴィレッジの中心部と言っていい場所のようだ。
有名なタバコ店の方へと交差点を渡り、その脇の通りをもう少し歩いて、日本のファストフード店のような造りのピザ屋を見つけた。
通りの見える窓側の席を確保してから、ふたりとも巨大な円形のチーズピザの、八分の一のサイズを注文した。トッピングはそれぞれで、炭酸飲料も合わせて頼んだ。
あまり会話もせずに、日本人にはちょっと量が多すぎるピザを食べ終えた。ニューヨークのこの時点までの感想を言い合ったのはそれからだ。
奈津美が言った。
「全然スケッチをしていないけど、わたしが歩き過ぎかな? 絵になるカフェがいくつもあったのに」
「いいや」と修平は答えた。「ワシントン・スクエアではスケッチをしていても安心だったけど、さすがに歩道でするのは不用心だと思って。意識が自分の持ち物から消える。さんざんニューヨークの危なさを旅行代理店が教えてくれたし」
「飛行機の中で、画材店の話をしていましたよね。あれはどこにあるんでしたっけ?」
「チャイナ・タウン。パール・ペイントという名前だった。たくさん買い込みそうな気がするんで、最後の日に行こうと思っている」
「レモン画翠みたいなお店なんですか?」
「むしろ神保町の文房堂みたいなところじゃないのかな。写真を見ると、赤と白のちょっとポップな建物だった」
「いいですね。わたしも行ってみようかな。そのときついて行ってもいいですか?」
「ああ、そのほうが楽しいだろうな」修平は逆に訊いた。「さっき、歩道で立ち止まって、女性ふたりが話しているのを見ていたけど、あれは何だったの?」
「ああ」奈津美は微笑した。「言葉がわからないから、想像ですけど、向こうから歩いてきたけっこうアバンギャルドな黒いファッションの女性がいたでしょ」
「立ち止まっていたひとりだね」
「あのひとを、べつの女性がすれ違うおうとしたときに呼び止めたんです。まずエクセレント、とかって言うと、相手がにっこりしてサンキューと答えた。知らない同士のようなんですよ。そうしたら、ふたりとも立ち止まって、たぶんファッション談義が始まった。ニューヨークでファッションの情報ってこういうふうに広まるのかって、びっくりして見ていたんです」
その後もウエスト・ヴィレッジを歩いた。途中でピーコック・カフェという喫茶店を見つけて入った。窓から覗くことのできる店内は、日本の純喫茶のような趣きだった。入ってみると、働いているのはかなり高齢の白人女性ひとりだけだった。彼女は店主なのかもしれない。ウエイトレスはたまたま休んでいるのか。
客の数も少なかった。歓談しているグループ客などはなく、四人掛けの席にひとりでついて読書している客が五人ほどいるだけだった。かかっている音楽はバッハだった。無伴奏チェロ組曲の何番かだ。
「気に入ったな」と奈津美がコーヒーを注文してうれしそうに言った。「ニューヨークにもこんな雰囲気の喫茶店があるなんて」
修平は言った。
「冬樹さんに似合いそうな店だ。バッハを聴きながら、アメリカの短編集を読む。外はウエスト・ヴィレッジ」
奈津美は黙ってコーヒーカップを口に運んだ。
けっきょくその日は、午後七時くらいにホテルに戻り、修平はいったんシャワーを浴びた。奈津美もそうだったろう。八時四十分にロビーに下りてきたときは、昼間よりもむしろ逆にカジュアルな服装になっていた。
イースト・ヴィレッジのグレート・ジョーンズ・カフェにはタクシーで向かった。カフェに着いたときに気がついたが、その日は芝居を見終わった後、奈津美はまったくそれを話題にしていなかった。修平もそのことを口にしていない。修平の英語力で、英語の芝居の感想などを語ることは無謀だったと思えたからだが。
グレート・ジョーンズ・カフェに着いて店の中に入ると、冬樹と礼子、それに冬樹たちのふたりの友人らしき若い男女がひと組、ひとかたまりになって酒を飲んでいた。
奥の席で冬樹が立ち上がり、手招きして言った。
「ここだよ」
修平たちは、客の椅子がゲーム盤の障害物のようにふさぐ通路を進んで、冬樹とその仲間たちのテーブルにたどりついた。昨夜と同様、冬樹とはゆっくり話せない様子なのが残念だった。
席に着いてから見渡すと、前夜のカフェ・レッジオの雰囲気をもっとくだけた雰囲気にしたような店だった。客層は明らかにカフェ・レッジオよりも若かった。大半がひと目で何かしらのクリエーティブな仕事に就いているか、その卵かという雰囲気がある。美術か、音楽か、文芸か、演劇か、あるいは映像か。修平は、自分がたぶん完全に浮いているだろうと意識した。言葉も話せない日本人だからではなく、そのファッション、外貌、表情、雰囲気のすべてが、お上りさん観光客以外のものではないだろうと。
奈津美は、昨日よりもずっとすんなり周囲に溶けこんだ。ろくに英語を話せないのは修平と同様なのに、礼子の通訳が巧みなせいか、ほとんどタイムラグなしに笑ったり、感嘆詞を使ったりしていた。
その日は十一時三十分に散会となった。
翌日、日曜日は冬樹がイースト・ヴィレッジを案内してくれるという。
「セント・マークス・プレイスでいくつか、これがイースト・ヴィレッジだってところを案内する」
奈津美が訊いた。
「たとえばどんなところです?」
「詩の朗読会とか、コンテンポラリー・ダンスとか、探してみる。ミミは日本食が恋しくなっていない?」
「まだ三日目ですよ」
「セント・マークス・プレイスには、日本食の店も少しある。寿司や、ラーメン屋とか」
「違うものを食べてみたい」
「ウクライナ料理店もあったな」
「聞くだけでももう満腹してる」
「お腹が?」
「ニューヨークが、ですよ」
「夜六時に会うのでは?」
修平は奈津美の顔を見てから言った。
「いいよ」
奈津美もうなずいた。
セント・マークス・プレイスの西、アスター・プレイスという広場の、立方体のオブジェの前で待ち合わせるということになった。
礼子が店の外でタクシーをつかまえてくれた。
ホテルに着いてロビーに入ったところで、奈津美が訊いた。
「明日の予定は決めています?」
「明日はぼくも近代美術館に行く。二日酔いになっていなければ」
「ずいぶん飲んでいましたね」
「話ができないと、飲むしかないよ」
「昼間は部屋を出ていなければなりませんよね」
「ピーコックで眠ろうかな」
「そうですか」答が期待はずれという顔と見えた。
「奈津美ちゃんは?」
「ひとりで、セントラル・パークを歩いてみます。あとは夕方まで適当に」
エレベーターの扉が開いた。
乗ってから修平は訊いた。
「『ファンタスティックス』いつ観るか決めたの?」
「ううん。冬樹さん、調整するって行ってたけど、ずっと忙しいんだと思う」
四階でエレベーターが止まり、「おやすみなさい」と奈津美は降りていった。
六時に指定された場所に行くと、奈津美が来ていた。金属の四角い立方体が、端っこで立っている広場だった。その立方体のすぐ脇に奈津美がいた。修平が西側の通りを渡って奈津美に近寄ってゆく、正面の側から冬樹も近づいている。礼子と一緒だった。奈津美は修平に気がついて手を振ってきたが、すぐに振り返った。奈津美の向こうで歩きながら冬樹が微笑した。
四人がその場に揃ったところで、冬樹が修平たちに訊いた。
「まずコーヒーかい。それともまだ観光できるか」
奈津美が言った。
「セント・マークス・プレイスの一番お勧めの喫茶店に行って、それから観光がいいな」
「そうしよう」
冬樹が案内してくれたその通りは、一方通行のあまり広くはない街路だった。建物の壁に落書きの目立つ、かなり猥雑な印象がある。東京で言えば、通行人の雰囲気は、下北沢にも似ていた。カフェ、古着屋、中古のレコード店、民族料理店、質屋もあるし、八百屋や惣菜店もあった。ウエスト・ヴィレッジよりもずっと生活感のある通りだった。
冬樹が奈津美に、きょうどこに行ったかを訊いた。奈津美は、セントラル・パークに行き、そのあとデパートをふたつ回ったと答えた。
修平は言った。
「近代美術館」
「そこだけ?」
「起きたのが遅かったんだ。近代美術館を二時間観てから、一度コーヒーを飲みに出て、もう一回行った」
セント・マークス・プレイスをゆっくり歩きながら、冬樹がこの通りの面白さを語ってくれた。
「とにかくイースト・ヴィレッジには、若いアーチストが多い。日本では考えられないくらいに詩人も多くて、詩の朗読会も多い。詩人の交流会もあるな」
「日本で言えば、俳句や短歌の愛好家くらいに?」
「そうだな。無名のうちは、簡易印刷でチャップ・ブックっていう詩集を作る。彼らはこの通りや近辺のカフェでよく詩の朗読会をする。セント・マークス教会では、週に二回、詩の朗読会が開かれている」
「教会で!」驚いて修平は言った。
「詩を作る、読む、聞くっていう文化がある」
奈津美が訊いた。
「ニューヨークは、パフォーミング・アーツもものすごく盛んですよね」
「うん。それも、コンサート・ホールなんかでやるだけじゃなく、カフェだったり公園だったり、こんな街中の道路でやったりする。広場でいきなり街頭演劇が始まったりする」
「冬樹さん、すごく刺激を受けてますね」
「そりゃそうだよ。アーチストやクリエーターにとっては、イースト・ヴィレッジはコロシアムだよ。毎日が真剣勝負なんだと」
冬樹の言葉が妙なところで切れたような気がした。歩きながら、修平は冬樹の顔を見た。反対側で奈津美も冬樹を見た。
冬樹が続けた。
「だと思う。だけどこの街で自分のテーマを持っていない人間は、きついだろうな」
奈津美が言った。
「わたしは住めないな、きっと」
「何言ってる」と冬樹が笑った。
自分もたぶんここでは住めないと修平も思ったが、口にはしなかった。
セント・マークス・プレイスを東端まで歩き、大きな通りを渡って公園に入った。ワシントン・スクエアよりも緑が多く感じられる公園だった。
冬樹が言った。
「そっちのほうに野外ステージがあって、きょうもたぶん誰かのライブがあったはずだ。ハードコア・パンクとか、フリージャズが多いみたいだ。詩の朗読とコンテンポラリー・ダンスのコラボレーションみたいなライブがあったこともある」
礼子が、何人かのひとの名を口にした。
「アレン・ギンズバーグ、サン・ラ、オーネット・コールマン」
ここでパフォーマンスをしたアーチスト、クリエーターの有名どころだったようだ。
冬樹はその野外ステージのほうには向かわずに、遊歩道を北に折れた。
途中、芝生の上に立って、詩を朗読している男がいた。顎鬚の、三十代の白人男だ。その前に十人ほどの男女が立って聴いている。
冬樹が立ち止まった。修平も横で足を止めて朗読を聴こうとしたが、ほとんど聞き取れなかった。語尾に多く韻が踏まれていることだけはなんとなくわかった。
冬樹が歩きだして、その詩人の声がほとんど聞こえない位置まで来てから、冬樹が言った。
「アメリカのいまの詩の思潮ってのが、ちょっと面白いんだ。昨日カフェ・レッジオにも来ていた男も教えてくれたことなんだけど、告白詩とか叙情詩から距離が置かれているんだ」
「というと?」
「詩から内面性を徹底的に排除するんだ。だから即物的で無機的だ。叙情性とか、物語性の排除が、いまのアメリカの詩の潮流なんだそうだ」
「前衛詩ってことかい?」
「聞いたときに、日本のモダニズム詩にもその傾向があったかなと思った。いまの詩の教室では、小型のカメラで撮ったように書け、と教えるらしい。ぼくは、その場合でも物語性は消えないと思うのだけど」
礼子が言った。
「ランゲージ詩人と呼ばれるグループもある」
「そのネーミングは、よくわからない」
公園を出ると、東十一丁目の通りだった。角の横断歩道を渡った。正面に、窓の上に赤い庇をつけた喫茶店がある。
「そこに入ろう。雰囲気は、昨日一昨日に入ったカフェよりも少し落ち着いている。だけど、やっぱり刺激的だ」
中は十一丁目通りに面した側に長い空間で、もっとも奥にステージがあった。キーボードやドラムスのセットもある。音楽ライブもできる喫茶店、というか酒場だった。詩の朗読会もあるのだという。ほぼ満席だ。
客の雰囲気は、これまで入った二軒のカフェとよく似ていた。客の外見も、服装も、歓談する雰囲気もだ。
四人賭けのテーブルに着いて、それぞれがコーヒーを注文した後、冬樹は周囲の客たちを見やりながら言った。
「オペラに『ラ・ボエーム』ってあるだろう。ボヘミアンたちの話」」
「知っている」と修平は言った。
「舞台は十九世紀なかばのパリだけと、あれに出てくるボヘミアンたち、貧しい芸術家たちが、カフェに繰り出す」
礼子がうなずいて言った。
「カフェ・モミュスに行くのよね」
「ヴィレッジのこういったカフェって、あのオペラの雰囲気そのままだって気がする」
修平は冬樹を見つめて言った。
「ここにはミミもいる」
奈津美が引き取った。
「服飾業界で働く、お針子のミミ」
礼子が笑った。
「わたしは何だろう? ムゼッタじゃないのは確かだけど」
冬樹は笑って言った。
「コーヒーを飲んだら、セント・マークス・プレイスに戻ろう。ウクライナ料理を食べて、その後ラ・マーマで面白いパフォーマンスをやっているようなら入る。ライブがいまひとつならヤッファ・カフェでワインだ。そこはちょっと静かだ」
そのときひとりの初老の男性が、ステージに上がった。口髭を生やし、夏物のジャケットを着ている。クリエーターとかアーチストのようではなかった。地元の商店主だろうかと思える雰囲気があった。顔だちはヒスパニックかもしれない。
彼が言った。
「お店のひとから許しをもらって、ここに上がりました」
客はみなその男性を見つめ、話をやめた。
「きょうは、妻の誕生日なんです。一曲だけ、彼女のために歌わせてください」
拍手が起こった。礼子が修平と奈津美のために、そこまでの彼の言葉を素早く小声で通訳してくれたのだった。
男性は続けた。
「歌いたい曲は、ケニー・ロジャースの『レイディ』なんですが、もしここに、これをキーボードで伴奏してやるよという方がいたら、助けてもらえるとありがたい」
男性は客席を見渡した。ほんの一瞬、客席が静まったけれども、ひとりの白人男性が立ち上がった。長髪で、ジーンズにポロシャツというカジュアルな服装の男だった。
その男はキーボードの前に腰掛けると、初老の男性に何か言った。
「楽譜はないよね?」
「すまない」
「たぶん大丈夫だと思う」と、これも礼子が訳してくれた。
長髪の男が初老の男性ともうひとことふたこと話した。打ち合わせたのだろう。やがて長髪の男が控えめに前奏を弾き出し、初老の男性が歌い始めた。出だしのバリトンのワンフレーズで客席がどっと沸いて、拍手が起こった。
歌いながら初老の男性は、客席のある一点から目を離さない。修平が振り返ると、そこに品のいい女性がいる。夫人なのだろう。幸福げな微笑を浮かべて、歌う男性を見つめている。
初老の男性が歌い終えると、客たちは最初よりもずっと盛大な拍手を送った。ありがとう、と初老の男性が小さく言って、伴奏のボランティアを買って出た男性ともうなずき合った。
修平も奈津美も、初老男性が自分の席に戻り、夫人と思える女性にキスするまでを見つめていた。
奈津美が冬樹に訊いた。
「このお店では、いつもこういうことがあるんですか?」
冬樹は首を傾げた。
「初めて見たな。たぶんあのひとは、かなりの常連なんだと思う」
奈津美が言った。
「ここも好きだな」
店の名は、ライフ・カフェ、だった。
(つづく)