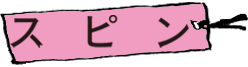『自閉症のぼくは小説家』 第10回 「この思いを何と名づけよう」
内田博仁(うちだ・はくと)
2026.02.06

連載第10回 「この思いを何と名づけよう」
「友達がいない」
先日のエッセイで僕はこう書いた。しかし人生は大きく変化するものだ。
何とこの僕に仲間ができたのだ。僕のように言葉が話せない重度自閉症の子達が、文字でやり取りをしてコミュニケーションを取っている会があると母に聞いたのは昨年末のことだった。
「自閉症の子同士が文字でおしゃべりするんだって」
文字でおしゃべり? 僕はビックリした。先生や家族とは文字でやり取りをしたことがあるが、友達と文字で会話をするなんて考えたこともなかった。なぜなら僕の周りの同級生のほとんどは、お互いが口頭でやり取りをしているからだ。同じ自閉症でも僕みたいに全く言葉のでない子はまれなのだ。だから僕は同級生とほとんど会話をしたことがなかった。しかし聞くとその会のメンバーは、みんな僕のように言葉が全くと言っていいほどでない子達ばかりだというのだ。
そのみんなが会話をする? どのように? 僕は興味津々だった。
「はくと行きたい? 行こうよ!」と母が言った。
僕は「是非参加したいです」と打った。
今回の会場は都内にある施設だった。駐車場に着いて車を降りた途端、元気に動き回っている男の子が目に入ってきた。
「あ、この子知ってる」と思った。小さい頃家に遊びに来たことがあるA君だった(1人知り合いがいるとは聞いていた)。あの頃より背も伸びて表情も大人っぽくなって一瞬分からなかったけど、間違いなくあのA君だ!
知っている子がいたことで僕は少しだけリラックスしてきた。それでも緊張と興奮で身体はカチコチだった。こわばった表情でエレベーターに乗り、部屋に入るともうすでにお友達が来ていた。今回の集まりは僕を含め全部で4人。高校生が3人、社会人が1人、全員男の子だ。
机を並び変え対面式にしてお話をするスタイルを作り上げて、さあいよいよ会が始まる!しかし始まった途端、皆一斉に好きなことをし始めた。お菓子を食べ始める子がいたり、目の前にいるA君はこの後買ってもらう予定のキャラクター人形?の写真をずっと指差して両親におねだりをしている。その様子はまるで学校の自由時間のようだった。いったいおしゃべりは、会話は、どのようにして始まる? 僕はこの手持無沙汰な時間をどう過ごしたらいいのか分からず、紐をずっといじりながら待っていた。
そんなマイペースな雰囲気を打破するように、友達のお母さんが「まずはそれぞれが自己紹介をしましょうか」と切り出してくれた。
まずはこの中で唯一社会人のB君からだ。がっしりとした体格と包み込むような微笑みが年上の貫録を醸し出しているB君は、ボードのようなものに書いてあるアルファベットを指差しながら名前を打った。速いスピードでタッタッと指差すので僕は驚いた。
こうやってボード上のアルファベットを指差して言葉を打つんだ…感激のあまり僕はちらちらと何度もその打つ姿と表情を見てしまった。続いてA君だ。クルクルっとした目でアルファベットを一生懸命指差して名前を打ってくれた。なんて可愛らしい仕草なんだろう。そしてC君。しなやかで優美な雰囲気のC君は、真剣な目で一つ一つの文字を見て指差しながら、落ち着いてゆっくりと名前を打ってくれた。
凄い…傍から見ると文字を打つ姿ってこんな風に見えるのか。身体全体で必死に文字を見つめ表現するその様子が素敵で、僕は惚れ惚れしてしまった。そして次はとうとう僕の番だ。どうしよう、指は動くだろうか。また(身体が)固まりはしないだろうか? 目の前に出されたタブレットにコツコツと音を響かせながら僕は緊張しながらこう打った。
「このような素晴らしい会に呼んでくださり感謝します」。
堅苦しすぎただろうか。それも緊張のあまりもの凄く怖い顔をしていたかもしれない。しかし「よろしくね~」というお母さん達の声が部屋に響いた瞬間、緊張した空気が一気に解きほぐされ、僕の肩にのしかかっていた重い塊も一瞬で消えてしまった。しかし思った以上に魅力的なお友達たちだ。僕は内心大興奮していた。
「はくと話しかけてみる?」と母が言った。僕は勇気をだしてB君に「大人っぽいですね」と話しかけてみた。B君は「ありがとう」と打ってくれた。生まれて初めて文字でお友達とやり取りをしてしまった。
これなんだ!と僕は叫びたい思いだった。自分の言葉で友達に話しかけること。それをずっとしてみたかった。
気持ちが乗ってきた僕は、続いてC君に「フランス語話せるんですか?」と聞いてみた。C君のお母さんがフランス語を話すのを横で聞いていたからだ。それは流れる川のようなまるでパッと花が咲くような上品な言葉で、C君もこの素敵な言葉を話せるのか気になってしまったのだ。C君は「お母さんもお父さんも話すので分かります」と丁寧に答えてくれた。C君は何と二か国語を完璧に理解しているのだという。
聞きたいことを聞いて、それを本人が発した言葉で返してもらえた喜びは想像を超えていた。そしてこの確かな繋がりは今まで経験したことがない感覚だった。
僕はよく大人たちに「ありがとう」とか「嬉しい」とか日々代弁してもらっている(時に自分の考えと違う時もあるけれど)。今まで自分の思いとして、友達に言葉を直接放ったことも放たれたこともなかった。だからこのやり取りはそんな僕にとっては夢のような経験だったのだ。この時、とある映画のワンシーンが僕の頭に浮かんでいた。
それは「僕が飛び跳ねる理由」という映画の中のエピソードだ。自閉症の作家・東田直樹さんのエッセイを原作にしたドキュメンタリー映画で、世界各地の自閉症の子とその家族の姿が描かれている。
エマとベンは6歳の頃からいつも一緒にいた。傍から見たら二人はずっと友達にしか見えなかった。でもそれをお互い言葉にはできない。二人とも重度自閉症で話せなかったからだ。でも心は繋がってただろう二人は常に一緒にいた。ベンは(先に始めていたエマにならって)あるきっかけから、16才の時文字盤をつかって心の内を表現できるようになった。そして文字盤を通じて二人は言葉での交流を始める。
そこでエマはベンを「初めてできた友達」だと表現したのだ。ずっとお互いを友達だと認識していたことが、言葉にして初めて分かったのだ。きっと友情という感情はお互いに持ってはいただろう。でも心の中に閉じ込められてる言葉は、大袈裟に言うと幻のようなもの。言葉として外に出さない限り相手には伝わらないのだ。
曖昧だった感情を確かなもの、形のあるものにしてくれた、それが言葉だった。言葉が二人をより固い絆で結んでくれたのだ。言葉として放たれた瞬間の解き放たれた喜びと、お互いの愛情を確認できた幸福感は、僕たちにしか絶対に分かり得ない感情だろう。僕がこの会で感じた感情はまさにこれだったのだ。
しかし人と接することはなんて学びが多いのだろうか。未知の世界に出会える喜び、刺激、成長…この一日でどれほど僕の心は大きく揺れ動き、感動し、豊かな感情で満たされたことだろう。仲間にいれてもらえたことに心から感謝したい。
最後にこれだけは言いたい。僕らが親に言いたいことを伝えるのにどれだけの努力が必要だったのかということを。僕らだけではない、むしろそれを引き出そうと努力したお母さん達の思いがどれほど切実だったかということを。
どんな方法でもいい、この子の言葉が聞きたい、この切なる願いは当事者でないと決して分かりえない願いだろう。お友達はきっとどんな時も打つのを止めなかったはずだ。どうしても言葉として伝えたかったから。誰よりも大切な人に。
そのためならどんな努力もするのだと決意して歩んできた親子の絆と信頼関係、そのいくつもの困難を乗り越えてきただろう親子の美しい姿を僕は絶対に忘れないだろう。それらを共に乗り越え、心を通じ合わせているからこそ皆こんなに笑顔でいるのだ。僕は彼らと共に学び成長したい。僕がずっと願い言い続けていることだ。
この日僕は夢に一歩近づいた。