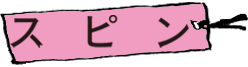読み物 - 読み物
【書き下ろし短編小説】正義の味方
天祢涼
2025.08.21

天祢涼 正義の味方
1
仕事をする気があるのか?
貸し会議室に入ってきた藤峰晴を見た瞬間、一条直は顔をしかめそうになった。
豊満な胸を強調するために選んだとしか思えない、サイズの小さなブラウスとジャケット。長い脚を引き立てることが目的であろう、丈の短すぎるスカート。当人に告げたら「若いのに頭が固い」と一笑に付されるかもしれないが、一条にしてみれば仕事に来る服装ではない。
家族とすごすのを我慢して来てやったのに……。自身の左手薬指に嵌めた指輪に一度視線を落としてから、藤峰と名刺を交換する。
「一条直さんとお読みするんですか」
一条の名刺を見て、藤峰は言った。電話で話したときから漠然と思っていたが、蜜のように甘く蕩けた声だ。
「直です」
一条は素っ気なく訂正した。我ながら、いつも以上に愛想がない。Q県警の名刺には、名前にふりがなやローマ字表記が付されていない。そのため名前を読み間違えられることに慣れているが、この女にそれを伝える気にはなれなかった。
「あら、ごめんなさい。すてきなお名前ですね」
藤峰の声を聞き流しながら、渡された名刺に目を遣る。肩書きは「『週刊パンドラ』ライター」だった。ありふれたフォントでサイズも普通なのに、やけに自己主張して見える。
藤峰に視線を戻す。女性の肌についてはよくわからないが、藤峰のそれはしわが少なく、艶があった。まだ三十路前かもしれない。だとしたら、一条とほぼ同世代だ。
「その若さで『パンドラ』のライターをしていて、一人で取材に来るなんて。すごいですね」
「よく言われます」
半ば社交辞令で言ったのだが、藤峰は謙遜するでもなく答えた。『週刊パンドラ』のライターは、これくらい面の皮が厚くなければ務まらないということか。
『週刊パンドラ』は、飛ぶ鳥を落とす勢いの週刊誌だ。常態化した出版不況に巻き込まれ、ご多分に漏れず発行部数は下落傾向にある。しかし政財界や芸能界のスクープを連発しており、存在感はむしろ増している。
取材が行きすぎるきらいがあり、先月も、不倫した国会議員の家族からコメントを取ろうと外出先まで追い回し、ネットで大炎上したばかりだ。編集長名義で謝罪のコメントを出したものの、炎上は未だ収束していない。
それでも世間の信頼は厚く、リーク情報を持ち込む者が後を絶たないと聞く。
──ふざけた恰好をしているからといって、油断しないようにしないとな。
わざわざ東京からQ県に来た以上、藤峰には明確な狙いがあるはずだ。うまくやりすごさなくてはならない。
そうでなければ、あの男──Q県警の番人の怒りを買う。
一条は奥の、藤峰はドア側の席に腰を下ろした。
「Q県には初めて来ましたけど、意外と暑いんですね。まだ六月とは思えません」
藤峰は左手でブラウスの胸許をつまみ上げると、右手をゆったり振って風を送り込んだ。胸の深い谷間が露わになる。豊満だと改めて思った。一条から向かって右側、ジャケットの胸ポケットに挿したボールペンは、いまにも落ちてしまいそうだ。咄嗟に目を逸らすと、藤峰の笑い声に鼓膜を揺らされた。一条の心情を見透かしているように聞こえた。
名前といい、スタイルといい、泥棒を主人公とした人気アニメに登場するヒロインを思わせる女だ。ヒロインでありながら平気で主人公を裏切ったり、かと思えば味方に戻ったりと、周囲を翻弄するキャラクターである。
──あのキャラクターのように、俺のことを翻弄しているつもりなのかもな。
だとしたら、甘く見るにもほどがある。
まだ配属されて二年にも満たないが、一条は生活安全課で幾度も修羅場をくぐり抜けてきた。半グレ組織の女にハニートラップをしかけられたことだってある。
こんな女の色香ごときに、惑わされはしない。
「本題に入るのは、注文を済ませてからでいいですね」
藤峰の返事を聞かず、一条はブザーを押した。ほどなくして貸し会議室に入ってきたホールスタッフに、一条も藤峰もコーヒーを注文する。ホールスタッフが出ていくと、藤峰はトートバッグを差し出してきた。
「お約束どおり、中を検めてもらって構いません。必要なら、身体検査もします? 私は構いませんよ?」
厚みのある唇の両端をつり上げ、からかうような口振りで、藤峰は言った。トートバッグを受け取った一条は、仏頂面で頷く。
「そうさせてください。後から変なところを触ったと難癖をつけられたらたまりませんから、身体を調べている様子は録画させてもらいます」
「私の方は録音も録画もだめなのに、そちらはするんですか。不公平じゃありません?」
「それが取材を受ける条件だったはずです」
そう言いながら、一条は藤峰のトートバッグを開けた。真っ先に目についたのは、金銀のビーズで派手にデコレーションされたスマホだった。取り出し、電源を切る。
「盗聴アプリを起動しているかもしれませんから」
藤峰が抗議の声を上げる前にぴしゃりと言って、引き続きトートバッグの中を漁る。盗聴や盗撮ができるデバイスは入っていない。隠されている様子もない。
注文したコーヒーが運ばれてきた。ホールスタッフが出ていくと、一条は自分の鞄から棒状のデバイスを取り出した。盗聴器や盗撮カメラの発見器である。それらが発する電磁波を検知する仕組みで、片手で持てる小型タイプだが捜査でも使えるほど精度が高い。
ビデオ撮影モードにしたスマホをテーブルに置いてから、一条は言う。
「その場で立って、両手を上げてください」
藤峰は肩をすくめながらも、指示に従った。一条は発見器を、藤峰の身体の方々に当てていく。
「私の方から身体検査の話を持ち出しておいてなんですが、信用ありませんね。『録音あるいは録画をしていることが判明したら、その場で取材中止』と言われているんですから、余計なことをするはずないのに」
「マスコミは信用できません」
「そんなにはっきり言われると傷ついちゃうなあ」
わざとらしく唇を尖らせる藤峰を無視して、一条は発見器を身体に当て続ける。
この部屋も、マスコミを信用していないからこそ選んだ。
相手が『週刊パンドラ』の記者となれば、隣席や隣室からの盗聴、盗撮にも警戒した方がいい。それを防げる取材場所がないかさがしたものの、一条の住む読川市内では見つからなかった。やむなく隣のQ市でも候補をさがしたところ、手頃な店を見つけた。アストリスカフェという、さびれた地方都市でしかないQ市には不釣り合いな、シンプルながら洒落た雰囲気の店だった。
店のホームページに掲載されたフロアマップによると、二階奥に併設された貸し会議室は両隣に部屋がなかった。しかもドアは、店のカウンターから見える位置にある。これなら盗聴される心配はない。Q市内にあるホテルの一室にすることも検討したが、万が一「ホテルに連れ込まれた」などと騒がれては面倒なことになるので、この店に決めたのだった。
待ち合わせの時間より三十分早く来て、室内に盗聴器やカメラがしかけられていないことも確認してある。テーブルや椅子の下はもちろん、壁際に植えられた観葉植物の葉の裏に至るまでチェックした。
ドアを背にして左側の壁には、部屋を広く見せるためだろう、大きな鏡が設置されている。壁にぴたりとつけられてはいるが、念のためはずして裏を調べられないか店員に交渉した。しかし断られたため、ほかの場所以上に慎重に発見器を当ててなにもしかけられていないことを確認した。
ここまでしたのだ。藤峰はこの部屋になにもしかけていないと断言できる。
「ところで一条さんは、読川市五谷町で起こった殺人事件のことはご存じですか」
発見器を当てられているとは思えないほど和やかな口調で、藤峰は切り出した。
用件は、やはりそれか。藤峰の顔を見ないようにしながら、一条は答える。
「知らないわけがないでしょう、うちの管轄で起こった事件なんだから」
いまからおよそ半月前、六月十四日午後八時二十分。読川市五谷町にあるアパートから、男性が共用部の廊下で血を流し倒れているとの一一〇番通報があった。駆けつけた交番巡査が、その場で男性の死亡を確認。男性の腹部には鋭利な刃物で刺されたと思しき傷が見られ、Q県警読川警察署は殺人事件として捜査を開始した。
被害者は、アパートの二〇四号室に住む高野興一、三十一歳。フリーランスのSEで、週に二度、Q市にあるIT企業に通勤していたが、基本は在宅ワークだった。
容疑者は、捜査本部が立ち上がる前、初動捜査の段階で見つかった。
高野宅の隣、二〇五号室の住人、小久保勝博である。
小久保はQ大学法学部を卒業しており、司法試験に挑むも四年続けて不合格となっていた。そのストレスからか、最近はバイト先の書店でも苛立ちを隠せず、同僚と口論になることが多かった。事件の前日、小久保の部屋の玄関先で、高野が「音楽を聴くなら、イヤホンかヘッドホンをしてください」と強い口調で抗議する姿も目撃されている。
捜査員の聴取に対し、小久保は当初こそ容疑を否認したものの、所有している靴から高野のものと思しき血痕が検出されると一転して犯行を認めた。
通っている予備校で司法試験の模擬試験を受けた小久保だったが、結果は芳しくなかった。このままでは今年も不合格は確実だ。七月の試験本番が迫る中、「文句を言ってくる隣人のせいで勉強に集中できない」と責任転嫁した小久保は、買い物から戻った高野に襲いかかり、出刃包丁で腹部を二度刺した。返り血を浴びないようにレインコートを着てはいたが、靴にまで気が回らなかった。そのせいで、血痕が残ってしまったという。
杜撰としか言いようがないが、現実の殺人犯とは得てしてそういうものだ。
かくして事件は、早期に解決を見た。被害者の高野には気の毒だが、ご近所トラブルに端を発したありふれた殺人事件として、さほど世間の注目を浴びることもなかった──。
一条が無言で発見器を持つ手を動かしていると、藤峰が不意に言った。
「被害者の高野さんは、事前に警察に相談していなかったんですか」
一瞬手がとまりかけたものの、素知らぬ口調で否定する。
「そんな話は聞いていません」
「でも高野さんは、小久保に直接抗議するほど迷惑していたんですよ。アパートの管理会社は頼りにならなかったと聞いてますから、警察に相談していたとしても不思議はないんじゃありませんかね」
「そう言われても、少なくとも私はなにも知らない」
藤峰の顔を見ないようにしながら、一条は噓をついた。
高野から警察に相談があった事実は把握している。
なにしろ対応したのは、一条自身なのだから。
*
六月十三日。一条は、当直勤務だった。
Q県警読川署の当直勤務は、原則、午後五時十五分から翌日の午前八時半まで。合間に四時間の仮眠が認められている。
体力には自信のある一条だが、完徹は少々きつい。三十路が近づいてから、それがより顕著になった。
この日も夜が深まるにつれ、睡魔が襲ってきた。それを必死に追い払っていると、机上の電話が鳴った。課内には、一条と、上司の杉山和彦係長しかいない。当然の流れで、一条が受話器を取った。
「読川警察署です」
〈も……もしもし〉
聞こえてきたのは、たどたどしい男性の声だった。明らかに緊張している。警察相手の電話では珍しいことではないが、一一〇番ではなく署に直接電話をかけてきたのだから、そこまで緊急性はないはず。
「どうしました?」
一条が問うと、相手は〈夜分遅くにすみません……でも……ええと……〉と、ますますしどろもどろになった。一条が無愛想なので、威嚇しているように聞こえたのだろう。
「落ち着いてお話しください」
意識して、やわらかい声を出す。その効果か、男性の口調が少し滑らかになった。
〈実は……相談がありまして。隣の人が、こんな時間に大音量で音楽を流しているんです〉
言われて、電話の向こうから音楽が聴こえてくることに気づいた。一条は興味がないので曲名はわからないが、クラシック音楽のようだ。電話でもこれだけ聴こえるとなると、かなりのボリュームと言える。
〈本当にうるさくて、迷惑してまして……警察から注意してもらえないでしょうか。夜中にこんなの、非常識すぎるでしょう!〉
話しているうちに興奮してきたのか、男性の声は徐々に大きくなっていった。壁にかけられた丸時計に目を遣る。時刻は午後十一時半すぎ。確かに夜中といっていい時間だ。
しかし一条としては、こう返すしかない。
「そういうことは、まず管理会社に相談してください」
民事不介入。それが警察の原則だ。批判されることも多いが、民間の争いに警察がいちいち口出ししていたら切りがないし、どちらか一方の肩を持つべきでもない。
〈管理会社は頼りにならないから、相談するだけ無駄ですよ。少し前、上の階に住んでいる人の歩く音がうるさくて、『注意してほしい』とお願いしたことがあります。でも、アパート全員の郵便受けに注意喚起の紙を入れただけでおしまいでした〉
「それでも、まずは相談してみてください。現時点では、そうとしか言いようがありません」
自分がすごした独身寮に較べたらたいしたことない、という思いもあった。
警察学校を卒業してから入った独身寮では隣室の先輩がうわばみで、一条が当直明けであろうとなかろうと関係なく、酒盛りのため部屋にやってきた。断ろうとしても、「先輩の言うことが聞けないってのか」と一蹴された。気が短く、ちょっとしたことで怒鳴ったり、説教したりしてくることにも辟易した。一条は早々に結婚して退寮したからよかったものの、あのままでは精神を病むか、上司にパワハラを訴えていたかもしれない。
当時のことを思い出すと、いまも胃に鈍痛が走る。
男性は黙ったものの、電話を切らなかった。不満が伝わってくる沈黙だ。やむなく、一条は言った。
「音楽が気になるようになったのは、いつからですか」
〈一週間くらい前ですけど〉
「眠れないほどの音量だったんですか」
〈そこまでは……気になる大きさではありましたけど〉
「それなら、もう少し様子を見てください。実害がないなら、警察は動けません」
〈うわ、警察って、本当にそういうことを言うんですね。でも隣の人は、相当ヤバい奴なんですよ。今日の夕方、イヤホンかヘッドホンをつけてくれと頼みにいったんです。でも無視された挙げ句、今夜はいつもより大きなボリュームで音楽を流しているんですから〉
わずかながら、一条の胸はざわめいた。そういう状況なら、男性が警察に相談したくなる気持ちもわからなくはない。少し真剣に話を聞いた方がいいかもしれない、と思った矢先だった。
〈あ、消えた〉
クラシック音楽がやんだことが、電話越しにもわかった。緊張しかけただけに、拍子抜けしてしまう。
「でしたら、今夜はもう問題なさそうですね」
〈そうですけど、明日も同じことが繰り返されるかと思うと……〉
「音楽は、毎日聞こえてくるんですか」
〈毎日というわけではありませんけど……〉
「でしたら、この先も同じことが繰り返されるなら、改めてお電話ください」
〈いますぐ、なんとかしてもらうわけにはいかないんですか〉
「それは無理です」
気の毒ではあるが、一条は返した。男性は電話を切らぬまま、再び黙りこくる。
──まあ、不満はわかる。
「私は生活安全課の一条と申します。あなたのお名前は?」
〈……タカノです。タカノコウイチ〉
「どういう漢字を書くか教えてください。それと、お住まいも」
男性──高野興一の説明をメモしてから、一条は言った。
「なにかあったら、私宛に電話をかけてください。署にいないこともありますが、できるだけ対応するようにしますから」
〈……なにかあってからでは遅いと思うんですけどね。まあ、お願いしますよ〉
高野は、不服そうにしながらも電話を切った。受話器を置いた一条は、大きく息をつく。
「名前まで教えたのか。向こうから訊かれたわけではなさそうなのに」
右斜め前に座る杉山が、あきれ顔で言った。訊ねられないかぎり、警察官が自分から名乗ることは稀だ。
「相手が不安そうだったので、それくらいはするべきと判断しました」
「真面目なこった」
実害がないので動くことは難しいが、せめて名前を伝えて「味方がいる」と安心感を与える、それが自分にできる精一杯の務めと判断しました──そう説明したところで鼻で笑われるに決まっているので、一条は黙って頭を下げた。
その後は特筆すべきことなく、当直が終わった。高野のことは日報に書きはしたものの、被害届を出されたわけではないので、帰宅後、泥のように眠ったら忘れた。
高野が刺殺されたのは、その日の夜だった。
2
事件の第一報を聞いた一条の頭にまず浮かんだのは、「まさか、あの高野興一じゃないだろうな」だった。しかしフルネームは一致する。現場の住所も、電話で聞かされたものと同じだ。
被害者は電話をかけてきた、あの高野で間違いない。
まさか犯人は隣人なのでは……呆然としているうちに隣人の小久保が逮捕され、動機は騒音を巡るトラブルであることが判明した。
あの電話から一日も経たず殺されたのか……猛烈な後悔に胸を塞がれ、息をすることすら苦しくなった。「どうすれば救えたのか」と何度も自問した。しかし、あの電話だけで緊急性が高いと判断することは不可能だ。どうしようもなかった、と結論づけるしかなかった。
──どうしようもなかったことを含めて、上に報告するべきか? 余計な情報を伝えたら、却って迷惑か?
悶々として一睡もできないまま出勤した六月十五日の朝、生活安全課の本田潤課長に告げられた。
「第二会議室に行け。県警本部から鏡監察官がいらしている」
自分の血の気が引く音を聞いた。「わかりました」とだけ返し、指定された部屋に向かう。生活安全課は署の二階、第二会議室は三階にある。大きな建物ではないので、普通に歩けば二分もかからず着く。
しかし一条には、その二分が果てしなく長く感じられた。
このタイミングで監察官に呼び出される理由は、高野の件以外考えられない。果たしてなにを言われるのか。それも、あの鏡真人に。
第二会議室に着いた。指先が冷たくなるのを感じながら、ドアをノックする。
「入れ」
ぶっきらぼうな声が聞こえてきた。「失礼します」の一言を挟み、一条はドアを開ける。
「生活安全課の一条です。本田課長から──」
「御託はいいから、さっさと入れよ」
鏡は一条を睨みつけ、圧の強い声で遮った。日ごろ暴力団や半グレ集団を相手にしている一条ですら、身が竦むほどの迫力だ。痩躯と青白い肌のせいで、いまにもヒステリックに喚かれそうな恐怖を感じもする。
震えを抑えてドアを閉めた一条は一礼してから、白い机を挟んで鏡の向かいに座った。
──噂は本当だったか。
こんな状況にもかかわらず、胸に失望が兆す。
鏡真人警視は、極めて特殊な監察官だ。
かつてQ県警は、証拠紛失、署内不倫、裏金づくりなどの不祥事が横行し、世間から大きな批判を浴びていた。警察庁から、重大な不祥事が続発した場合に行われる特別監察を受けたこともある。
しかし十数年前、鏡が三十代前半の若さで監察官に就任してから悪徳警察官は階級に関係なく処断された。あわせて、検挙率が一気に上昇。地に落ちていたQ県警の評判は急回復した。この功績を認められたのか、警察庁の意向なのか定かではないが、鏡は任期の三年を終えて別の部署に異動した後も一年経ったら監察官に戻るという人事サイクルを繰り返している。大抵の監察官は異動後、刑事部長になるなど出世コースを歩んでいくのに、である。「出世街道からはずれた」と揶揄する者もいるが、Q県警内の人事権も鏡が掌握しているという噂なので、本人も納得の上での異動なのだろう。
ゆえに、誰からともなく鏡のことをこう呼ぶようになった──「Q県警の番人」と。
一条は、警察官になっておよそ十年。これまで鏡と接したことはない。接した同僚もいない。だが、噂はいくつか耳にしている。その一つが、これだ。
──先輩には敬意を持って接するが、後輩には厳しく、罵声を浴びせることも珍しくない。
監察官がパワハラまがいの行為をするなど、まるでブラックジョークだ。しかし鏡は「組織の規律を保つには必要」と意に介していないという噂も聞いた。
あまり信じたくない噂だったが、どうやら真実だったようだ。
警察は、上意下達の組織だ。鏡の言い分には、一理あるのかもしれない。しかし先輩に媚びへつらっているようにも思え、一条はどうしたって反感を覚えてしまう。悪徳警察官は階級に関係なく処断したと聞くが、先輩には手心を加えたのではと疑いたくもなる。
──俺に『警察官に向いていない』と言った面接官は、あの鏡真人なんだよ。
かつて共に警察官を目指した親友、瀬尾隆信の言葉を思い出し、密かに歯噛みした。
「高野興一さんの件だ」
鏡は一条を睨みつけたまま切り出した。一条は唾を飲み込んでから「はい」と応じる。
「高野さんのスマホの発信履歴を確認したところ、一昨日、六月十三日午後十一時三十一分、読川署に電話をかけていたことがわかった。その時間帯、署にいた連中の日報を調べたよ。お前は高野さんから隣人トラブルの相談を受けたと記録している。間違いないな」
「間違いありません。ご報告するべきか迷っていたところで──」
「そのときのことを詳しく話せ」
一条を遮り、鏡は命じてきた。日報には、高野の名前と相談内容の概要、緊急性なしと判断したことしか書いていない。
「……高野さんの様子からは、そこまで危険が迫っているとは思えなかったのですが」
この一言を皮切りに、一条は電話の内容を説明した。
「騒音トラブルが起こってから、まだ一週間しか経っていなかったんです」
「誰もが、まずは管理会社に相談するべき案件だと思うはずです」
「あの段階でできる精一杯の対応をしました」
説明している間、そんな言葉が口から幾度もこぼれ落ちたが、言い訳だとは思わなかった。
あの電話だけで動く警察官はいない。名前を教えた上に日報にまで書いた自分は、むしろ親身に対応した方だ。ちゃんと説明すれば、誰にだってわかるはず──そうは思っても落ち着かず、貧乏揺すりしながら説明する一条とは対照的に、鏡は腕組みをしたまま、相槌一つ挟まなかった。そのせいで、話が進むにつれ一条の口調はしどろもどろになっていく。
「──以上です」
ようやく一通りの説明を終えたときには、全身が汗ばんでいた。
「あの電話だけで、事件を未然に防ぐことは不可能──」
「それを決めるのはお前じゃねえ」
鏡はようやく口を開いた。口調も言葉遣いも荒々しくなっている。独身寮時代の先輩と重なり、一条の胃に鈍痛が走った。
「警察の理屈で言えば、お前はなにも間違っていない。だが、世間がそう思うわけないだろうが。警察の冷たい対応が事件を招いただの、高野さんの命を救うことができたはずだの、無責任に批判してくることは目に見えている。特にマスコミは、恰好のネタだと飛びつくぞ。『信頼回復したと思われたQ県警は、なにも変わっていなかった』なんて、いかにも連中が喜びそうなストーリーじゃないか」
確かにそうだ。
不祥事が続発していたころのQ県警は、パトカーの中で会話を交わす姿すら「スクープ撮」と銘打たれ、緊迫感に欠けると批判された。普段はマスコミを「マスゴミ」呼ばわりする連中もそれに便乗した。今回の件がマスコミに知られたら、あの時代に逆戻りするということか。
その原因は、俺──身体が熱くなっていく。
「忘れろ」
「え?」
聞こえなかったわけではないが、聞き返してしまった。鏡は癖の強い髪に右手を突っ込むと、目を閉じた。痩躯が一度、ぶるりと震える。怒鳴られると思って身構えたが、目を開けた鏡は予想に反し、怒気を孕んではいるものの静かな声で言った。
「忘れろ、と言ったんだ。高野さんには親も兄弟もいない。周囲に聞き込みしたところ、警察に相談したと知っている者もいなかった。お前さえ黙っていれば、すべてなかったことになる」
「しかし、日報は……」
「こちらで預かる。万が一問い合わせがあったら報告しろ。適宜対処する」
それは、つまり……。
「高野さんから相談を受けていた事実を揉み消す、ということですか」
揉み消す。その言葉が自分の口から発せられたことが信じられなかった。
一条は、人並み以上の正義感を胸に警察官になったと自負している。とはいえ、人の数だけ正義があるから、本当の意味での「正義の味方」などこの世に存在しない。そんなことは警察官になる前、十代前半のころにはわかった気になっていた。
しかし、本当の意味でわかっていなかったことを思い知ったのは、警察官になって二年目。「同棲相手の男に殴られた」という女からの通報を受けて駆けつけた現場がきっかけだった。
女は、男から日常的に暴力を受けていると訴えてきた。男はそれを否定し、自分が稼いだ金を勝手に使われ続け、むしろ自分の方が被害者だと主張した。本人たちから話を聞いた結果、男は日常的に暴力を振るい、女は男の金を使い込む生活を送っていたことが判明した。男女どちらにも非がある、「しょうもない」としか言いようのない事案だった。一条がこの一件をニュースサイトで知ったなら、少しあきれるだけで数時間後には忘れていたことだろう。
しかし実際の現場では、二人は獣の如き咆哮を上げて罵り合い、自分こそが正しいと声高に強弁し続けた。別々に話を聞こうとしたら、「俺の方が先だ」「いいえ、私よ」と競うように叫んだ。「同時に話を聞くから、ひとまず交番までご同行願いたい」と言っても聞く耳を持たず、双方とも鬼気迫る表情で一条に詰め寄った。
一般人相手に情けなくはあるが、誇張でなく身の危険を感じた。余計なことを言ったら、どちらかの味方になったと決めつけられてもう片方になにかされる──そう思って、先輩巡査と一緒にひたすら二人を宥め続けた。
日本の片隅で起こった、こんな「しょうもない」事案の当事者ですら、これだけ己の正しさを訴えるのだ。もっと複雑な人間関係や国家間においては、どれだけの正義が振りかざされているのか。
安易に正義を選択することはできないし、するべきでもない。警察という公権力を持つ組織に属する身なのだから、なおさらだ。ならばせめて正しくないことをしないよう、職務に務めなくては。
「不正をしない」。後ろ向きにも矮小にも思えるが、それこそ自分が貫くべき正義──その決意を胸に、一条は警察官人生を歩んできた。杓子定規に生きてきたわけではない。必要悪と見なされるであろう、小さな不正をしたことがないとは言わない。
しかし、世間から後ろ指を差される行為に手を染めたことは一度もない。
そんな自分が、被害者から受けた相談を「揉み消す」?
一条の葛藤をよそに、鏡はあっさり頷いた。
「ほかに方法はねえだろう。ここでまたQ県警の信用が落ちてみろ。治安が悪化して、救える命も救えなくなるだろうが」
鏡が監察官に就任する前、Q県の治安は悪化の一途をたどっていた。「Q県警に捕まるはずがない」と舐められていたことが、犯罪者が増える一因になったと分析されている。不信感から、なにかあってもQ県警に相談しない県民も多かったようだ。
「しかし──」
「このことを世間に知られたら、批判を受けるのはお前だけじゃないんだ」
鏡が口にした「お前だけじゃない」とは、Q県警全般を指しているのだろう。しかし一条の脳裏に浮かんだのは妻と息子──優花と奏汰の笑顔だった。
自分の対応に問題はなかったと自信を持って言える。しかし世間は、そうは思うまい。悪徳警察官として、容赦なくバッシングしてくる。二人を悲しませることになる。万が一、懲戒免職でもされようものなら、養ってやることもできなくなる。そうなったら最悪だ。
──だったら……俺は悪くないのだから……独り身ならともかく、家族のことを思えば……。
「とにかく忘れろ」
鏡は荒々しい声で繰り返す。
「高野さんのことだけじゃない。ここで俺と話したことも含め、この件に関するすべてをだ。いいな?」
「……わかりました」
優花と奏汰のためだ、と自分に言い聞かせ、一条は声を絞り出した。
鏡に言われるまでもなく、この件は忘れるつもりだった。鏡とは二度と顔を合わせたくないとも思った。
しかし一週間後。一条は再び第二会議室に呼び出され、鏡と対面していた。
「『週刊パンドラ』の取材を受けろ」
鏡の第一声は、それだった。
「パンドラって……スクープを連発している、あの『週刊パンドラ』ですか」
「そうだ」
わかりきったことを訊くな、と言わんばかりの口振りだった。前回に続き独身寮時代の先輩の姿が思い浮かび、一条は慌てふためく。
「失礼しました。でも、どうして私が取材を? まさか、高野さんの件で?」
「向こうは理由を言っていないが、ほかに考えられないだろう」
「なぜ『パンドラ』は、私がかかわっていると気づいたのです?」
高野が相談のことを誰にも話していない以上、マスコミに一条の関与を知る術はないはずだ。
「わからん。だが先方は『読川署のイチジョウチョク』と、わざわざフルネームで指名してきた」
鏡は「イチジョウチョク」の一言を強調するように、わざわざ一音一音区切って口にした。
俺の名前まで知られているのか……。鼓動が加速していく。
「でも理由を言わないなら、取材を拒否することもできるのでは?」
「向こうの記者──藤峰という女だ──とは交換条件でいろいろ取り引きをしているから、そうもいかない」
「いろいろ取り引き、というのは?」
「知りたいか?」
目を眇めて問われては、「いいえ」としか答えられない。
鏡は、特殊な人事サイクルで監察官を続けているのだ。マスコミをコントロールするため、裏で飴と鞭を使い分けているのだろう。余計な詮索はしない方が身のためだ。
「わかりました、取材を受けます。広報課と日程を調整した上で──」
「いや」
鏡は、苦虫をかみつぶしたような顔で一条を制する。
「藤峰は広報課抜きで、お前とサシで話したいと言っている。それも、警察署の外でな」
警察官の取材に広報課が立ち合わないことは少ない。相手の目的がわからないことといい、異例尽くめだ。
「十中八九、藤峰は高野の話をしてくる。慎重に対応しろ。いざとなったら新たな取り引きを持ちかけて揉み消すが、お前があまりに醜態を曝しては手の打ちようがない。録音も録画も絶対にさせるな」
当惑する一条に、鏡は厳命してきた。言いたいことはいろいろあるが、逆らうことはできない。
鏡に教えられた番号にその場で電話をかけた一条は、六日後、藤峰の取材を受けることになったのだった。
*
発見器がなんの反応も示さないことを確認してから、一条は再び藤峰と向かい合って座った。
「お疲れさまでした、一条さん」
藤峰は唇を笑みの形にすると、テーブルに両肘をつき、胸の前で腕を交差させた。胸の膨らみが一際強調される。発見器を藤峰の身体に当てている間、この女のスタイルを意識しなかったと言えば噓になる。一条は先ほどに続き、思わず目を逸らしてしまった。それをごまかすためコーヒーに口をつけていると、藤峰が言った。
「高野さんからは、本当になんの相談もなかったんですね」
一条は、カップをソーサーに置いてから頷く。
「そうだと言ったでしょう。取材というのは、その件ですか」
「はい。実は、ちょっと気になることがありまして」
藤峰は胸の膨らみを強調したまま、テーブルに身を乗り出してきた。一条は、今度は藤峰を直視したまま目で先を促す。
なぜ取材相手に一条を指名したのか、気にはなる。しかし、高野が一条と電話で話したことは一部の捜査員しか知らず、全員に口止めしてあると鏡が言っていた。この女が知っているはずがないのだ。堂々としていればいい。
「高野さんが被害に遭う少し前、警察に電話で小久保のことを相談したという情報をつかんだんです」
3
「イチはすごいよ。子どものころからの夢を叶えて警察官になったんだから」
瀬尾隆信の称賛に噓はなかっただろう。しかし眉根を微かに寄せながら何度も頷く様を見れば、言葉の裏にあるものを察せずにはいられなかった。
瀬尾とは、幼稚園のときからの親友だ。家が近所だったこともあって、よく遊んだし、登下校も一緒だった。クラスが分かれることがあっても、関係は変わらなかった。
二人の共通の憧れは、悪の組織に敢然と立ち向かう特撮番組のヒーローだった。特に五歳のときに放送された『無敵剣士セイバースター』には、二人して夢中になった。ひ弱な主人公が、厳しくも温厚な老師に鍛えられ剣の達人となり世界征服を目論む組織と対決する……というありふれたストーリーだが、正義のために戦うセイバースターに魅せられた。
「大人になったら、ああいう正義の味方になろうぜ」という誓いは、小学校中学年になるころには「大人になったら警察官になろうぜ」という具体的なものへと変わっていった。もっとも、当時は警察官の仕事がどんなものなのか、よくわかっていなかったが。
一条は高校三年生のときQ県警の採用試験を受験し、合格を果たした。瀬尾の方は大学に進学し、四年生のときに同じくQ県警の採用試験を受験した。
結果は、不合格だった。
驚いたが、警察官採用試験は筆記試験のほかに身体検査や体力検査もある。いくら瀬尾が秀才でも、必ず合格できるわけではない。当然、就職浪人して受験し直すと思った。一条が瀬尾を居酒屋に連れていったのは、残念会兼激励会のつもりだった。
しかし瀬尾はジョッキで乾杯するなり「もう受験はしない」と宣言し、一条に言ったのだ。「イチはすごいよ。子どものころからの夢を叶えて警察官になったんだから」と。
「瀬尾っちだって、来年受けて夢を叶えればいいだろう」
戸惑いつつ笑う一条に、瀬尾はビールを一息で飲み干してから首を横に振った。
「俺には無理だよ。面接で『君は警察官に向いていない』と言われて、落とされたんだから」
「向いてないって……どういうところがだよ?」
「ショックすぎて訊けなかったけど、線が細いところじゃないか。実を言うと、俺も薄々そうじゃないかと思ってたんだよ。警察官になった後、どんどんたくましくなっていくイチを見ていたから。もっと早く気づくべきだったよな」
瀬尾は自嘲気味に言うと空になったジョッキを掲げ、店員に「生中をもう一つ」と声をかけた。
――こいつがこんな弱音を吐くなんて。
瀬尾は子どものころから学校の成績がよく、体力こそないものの運動神経がよかった。振り返れば一条は、ずっと瀬尾の背中を追いかけていた。「大人になったら、ああいう正義の味方になろうぜ」も「大人になったら警察官になろうぜ」も、最初に言い出したのは瀬尾だ。当然、警察官になった後も自分の前を歩んでくれるのだと思っていた。
ただ、瀬尾の体格が気になっていたことは事実だ。
警察官は肉体労働者。警察学校時代に嫌というほど走らされ、一条はそのことを思い知った。現場に出た後もそうだ。夏祭りの警備で炎天下に何時間も立たされる、徹夜明けで事故の処理に駆り出され三十時間以上一睡もできない……などなど、枚挙に暇がない。意識が飛ぶこともざらにある。もともと体格がよく、体力に自信がある一条でさえそうなのだ。小柄で、筋肉がつきにくい体質の瀬尾に務まる保証はない。とはいえ、
「俺の筋トレメニューを教えてやるよ。ある程度なら身体も大きく──」
「俺に『警察官に向いていない』と言った面接官は、あの鏡真人なんだよ」
瀬尾の言葉に息を呑んだ。
中学生になってしばらくしてから、二人そろって警察官になることに迷いが生じた時期がある。Q県警で不祥事が続発したからだ。中二のとき、当直の警察官が署内で性的関係を持ったことが明るみに出た際は、さすがに警察官を目指すことがばからしくなった。
それを変えたのは、瀬尾だった。
──今度Q県警の監察官になった鏡という人は、記者会見で『膿を出し切り、県民の信頼を取り戻す』と宣言した。目にも声にも力がある。なにかやってくれるはずだ。
監察官の着任挨拶という小さなニュースまで把握している瀬尾に感心する一方、期待しすぎだとも思った。しかし瀬尾の予言どおり、鏡は着任早々、悪徳警察官を階級に関係なく処断し、二年と経たずQ県警を立て直した。だから一条も瀬尾も、警察官への情熱が再燃したのだ。瀬尾がいなかったら、一条はQ県警の復活劇に興味を持たず、警察官にはならなかったかもしれない。
なのにその瀬尾が、夢をあきらめようとしている──よりにもよって、鏡真人によって。
いや、相手が鏡真人だからこそ、か。
「イチには俺の分まで、立派な警察官になってほしい。正義の味方になってくれ」
瀬尾はそう言って、運ばれてきたビールを再び一気に呷った。こんなに早いペースで飲む瀬尾を見るのは初めてだった。
翌年、瀬尾は、恋人の故郷である魚前町に転居し、そこの町役場に就職。さらに翌年、結婚した。その後も瀬尾との交流は断続的に続いたが、一条が読川警察署に配属されてからは魚前町と距離ができてしまったため会っていない。
しかし今年の三月末、朝のローカルニュースに出演する瀬尾を見た。気づいたのは、優花だった。
「瀬尾さんがテレビに出てるよ」
一条はネクタイを結ぶ手をとめ、テレビに映った親友を見つめる。
港に並ぶ小型漁船の前に立った瀬尾は、役場が魚前町の魅力発信事業を始めること、若い人に町に興味を持ってほしいこと、願わくば移住して漁業に就いてほしいことなどを語った。どうやら、町の施策を宣伝するために出演したらしい。
民間のPR会社と組んで始めたようだが、よくあんな田舎町の事業を請け負う業者を見つけたものだ。たいした予算もないだろうから、労力の割に実入りは少ないだろうに。
しかしレポーターの女性がいくら質問を重ねても、瀬尾は最後まで笑顔にならず、話が弾むこともなかった。新年度から魅力発信事業関連のイベントが続き、夏休み期間中には人気アイドルグループが来ることになっているらしいが、まるでアピールになっていない。
瀬尾は中学校では生徒会の役員を務め、人前で話すことが得意だった。だから笑顔にならない理由は、緊張しているからではない。
──引っ越しておいてなんだけど、魚前町はさびれてるよ。若い人が寄りつくような町じゃない。
いつだか飲んだとき、瀬尾はため息交じりにそう言っていた。それを踏まえると、魅力発信事業とやらに気乗りしていないからとしか思えない。
──仕事がつまらないんだな、瀬尾っち。
「パパ、なんでこわい顔をしているの?」
奏汰が怯えた声で言った。無意識のうちに唇を引き結び、双眸をつり上げていたようだ。
「パパの友だちがテレビに出ているから、すごいと思ったんだよ」
咄嗟に言い訳を口にすると、奏汰はくりくりした目を見開いた後、慰めるように言った。
「そうだね。テレビに出るなんてすごいね。でもパパだってすごいよ。正義の味方なんだからさ」
「そうよね。パパもすごいわよね」
優花が笑いながら奏汰に同調する。一条はと言えば、辛うじて笑みを浮かべるのが精一杯だった。
ニュース番組では、スポーツコーナーが始まっていた。日本人選手が大リーグでホームランを打ったという話題で、キャスターたちがつくり笑顔ではしゃいでいる。
「正義の味方なんだから」。奏汰が口にしたその一言に、「正義の味方になってくれ」という瀬尾の言葉が重なる。
──俺は『正義の味方』じゃないし、そんなものはこの世に存在しない。でも瀬尾っちの分まで、『不正をしない』という自分なりの正義を貫いてみせるよ。
瀬尾の痕跡が完全に消えたテレビに向かって、一条は目礼した。
この日のことを忘れたわけではない。とはいえ、明確に思い出すことは少なくなっていた。
しかし鏡に最初に呼び出されたあの日から、頻繁に脳裏に蘇っている。
*
「失礼。インクが切れていました」
その声で、一条は我に返った。いつの間にか藤峰が、ペンケースから予備のものと思しきボールペンを取り出していた。特に珍しくもない、どこにでも売っていそうなボールペンだ。
ボールペンを手にした藤峰は、無遠慮に一条の顔を眺めつつ、B5サイズのノートに書き込みを始めた。一条の表情をメモしているに違いない。
「インクが充分かどうか、取材前に確認しておかないんですね」
一条は顔をしかめて皮肉を口にすることで、表出した動揺をかき消した。その一方、頭の中で冷静に状況を分析する。
「高野さんが被害に遭う少し前、警察に電話で小久保のことを相談したという情報をつかんだんです」。藤峰のこの発言は真か偽か? 答えは、一秒もかからずに出た。
──偽だ。
そんな情報が出回っているなら、刑事課が把握していないはずがない。当然、鏡の耳にも入っている。しかし鏡は、一条にそんな話は一切しなかった。
大方、藤峰は事件の裏になにかあると踏み、一条の動揺を誘って口を割らせるつもりだったのだろう。稚拙な策だが、危うく嵌まるところだった。
なぜ裏があると思ったのか、策を弄する相手に一条を選んだのかは、わからないが。
「情報源は?」
一条が突っ慳貪に問うと、藤峰は芝居がかった様子で小首を傾げた。一条は重ねて問う。
「情報源ですよ、情報源。あなたによると、高野さんは小久保のことを事前に警察に相談していたのでしょう。そんなデマを流したのは、どこの誰です?」
「教えられるわけありませんよ。情報源は守らないといけないんですから」
「本当は情報源なんていないんじゃありませんか」
一条が眼光を鋭くすると、藤峰は大袈裟に肩をすくめた。そのまま沈黙する。やはり図星だったか。
事件の裏になにかあると踏んだ勘のよさは認めるが、相手にしていられない。早々に切り上げて──。
「情報源は明かせませんが、高野さんはお友だちに手紙を送っていたんです」
一条が言葉の意味を理解する前に、藤峰は口許に笑みを浮かべたまま、双眸をゆっくりと細くした。
俺の一挙手一投足を観察している目だ、と思ってから、藤峰がなにを言ったのか理解した。
「高野さんがお友だちに送った手紙には『昨日の夜、隣人との騒音トラブルを警察に相談した』と書かれていました。手紙の日付は六月十四日。事件が起こった当日ですね」
「で……でたらめを言わないでもらいたい」
言葉に詰まりながらも反論する。
「高野さんに手紙を送るような友だちがいたなんて話は聞いていない。いるならその友だちが、事件が起こった直後にマスコミに訴えているでしょう」
「そのお友だちは、海外に住んでいるんですよ」
声を上げそうになった。
海外なら、手紙が届くまで一週間近くかかる場合もある。日本国内で起きた殺人事件が報じられることもないだろうから、その友人が高野の死をすぐに知ることができなかったとしても不思議はない。つまり藤峰の話は、でたらめとは言い切れない? いや、しかし……。
「だとしても……今時、手紙なんて……メールもSNSもあるのに……」
「そのお友だちは、最近、出産したそうです。だから高野さんは、お祝いの品を贈りました。手紙は、それに同封されていた」
そういうことなら、手紙による近況報告も不自然ではない。
「お祝いを受け取ったお友だちは、すぐ高野さんにお礼のLINEを送りました。でも、いつまで経っても既読がつかない。心配になったけど、共通の知り合いもいない。だから高野さんの名前をネットで検索して、事件のことを知ったそうです。ただ、高野さんが事前に警察に相談していたという情報は見つからない。だから、うちに連絡してきたんですよ」
藤峰の話に矛盾はない。友人が海外在住なら、刑事課が見落とし、鏡の耳に入らなかった可能性は充分ある。『週刊パンドラ』には、リーク情報を持ち込む者が後を絶たないという噂とも合致する。
ゆっくりと、しかし着実に、一条の呼吸は乱れていった。気を鎮めるためコーヒーを口に入れようとしたが、右手が震えていることに気づきテーブルの下に隠す。
「ああ、そうだ。高野さんの手紙に関して、大切なことを忘れていました」
藤峰は胸の前で、ぱん、と両手を合わせた。わざとらしい仕草だった。一条を観察するような目つきのままなので、余計にそう思う。しかも話を振っておきながら、唇を笑みの形にしたまま黙っている。
「忘れていたって、なにをですか」
一条がこらえ切れず急かすと、藤峰は「実はですね」ともったいつけた前置きを挟んで言った。
「高野さんの手紙には、相談した警察官の名前も書いてあったんですよ。カタカナで『イチジョウ』です。勤務先は、読川警察署だとも書かれていました」
全身が粟立った。
「あなた以外に『イチジョウ』という名字の警察官は、読川署にいらっしゃいますか」
答えは「いない」だが、口にできるはずがなかった。室内に、再び沈黙が落ちる。室外から聞こえてくるほかの客の声が大きくなった気がした。
この情報を忘れていたなどありえない。切り出すタイミングを見計らっていたに違いない。
「どうして黙ってるんですかぁ?」
藤峰が、これまでよりさらに甘ったるい声で沈黙を破った。
「『イチジョウ』さんがほかにいるかどうか、簡単に答えられると思うんですけど?」
「……職務上の問題があるから答えられない」
言い終える前に、レベルが低い政治家よりひどい言い訳だと思った。案の定、藤峰は口許に右手を当ててくすくす笑う。一見したところ上品だが、せせら笑いだった。
直接の責任がないとはいえ、海外に住む高野の友人を見落としたことは鏡のミスだ。一条は、その巻き添えを喰らった形になる。
とはいえ、後輩に厳しく接する鏡が、己の非を認めるはずがない。このまま逃げ帰ったら逆ギレされ、処分を下される可能性だってある。
なんとかして藤峰に、この取材をやめさせなくては……。しかし、一体どうやって? 方策を考えようとすればするほど鏡の顔が、声が色濃く思い浮かび、胃がじくじく痛み出した。
──親身に対応して日報に書いた俺が、なんだってこんな目に……!
「ねえ、一条さん」
藤峰は腕組みをして、椅子の背に身体を預けた。目の高さはこちらが上なのに、高所から見下ろされているような心持ちになる。
「あなた、警察官なんですよね。それなら、国民を守ることが仕事なんでしょう。本当のことを話したらどうですか。ひょっとして、話したら大事になると思ってます? でも後からばれた方が、もっと大変なことになりますよ。私に言われるまでもなく、それくらいの判断力はあるでしょうけど。それとも、判断力はあっても警察官としての──いえ、人としての良心がないのかしら?」
最後の一言は、嘲笑とともに告げられた。一条の歯がかたかた鳴る。動揺と怒り、両方が理由だと思いながら、奥歯をきつく噛みしめた。その拍子に、三月末、ニュースで瀬尾を見たときの記憶が蘇る。
あのとき一条は、瀬尾の分まで「不正をしない」という自分なりの正義を貫く決意を新たにした。
だったら「揉み消せ」という鏡の命に背き、いまこの場で藤峰に洗いざらい話すべきではないか? それが警察官としてあるべき姿ではないか? 自分の中でなにか──藤峰に言わせれば「良心」か──が、声高に叫ぶ。それに従うことが、おそらくは正しいのだろう。
──落ち着け。俺だけの問題じゃないだろう。
今度は手の震えに構うことなくカップを握りしめ、コーヒーを一気に飲み干した。
奏汰の声が蘇る。
──でもパパだってすごいよ。正義の味方なんだからさ。
一条は「正義の味方」などでは断じてない。そういう子どもじみた夢はとっくの昔に捨てたし、そんなものが存在しないことも理解している。
それでも奏汰にとっては紛れもなく、一条は「正義の味方」なのだ。世間からバッシングされる姿を目の当たりにしたらどう思うか。
優花の声も蘇る。
──そうよね。パパもすごいわよね。
いまここで藤峰にすべてを話したら、奏汰だけでなく、優花も裏切ることになる。もちろん優花は、一条に非がないことを理解してくれるだろう。しかし、余計な心労をかけてしまうことは目に見えている。
それだけは、絶対に避けなくては。
──独り身だったら認めていたかもしれない。でも家族のためなんだ。なにがあっても、絶対に認めるわけにはいかないんだ。
カップをたたきつけるようにしてソーサーに戻した一条は、自分がなにを言いたいのか、言うべきなのかわからないまま、とにかく口を開いた。
「手紙が……そうだ、本当に高野さんの手紙が存在するなら、見せてもらいたい」
「お友だちからは、手紙を写真に撮って送ってもらいましたが、迷いますね。強引に押収された挙げ句、証拠を隠滅されてしまうかもしれませんから」
「写真だけなら見せられるでしょう」
破れかぶれで口にした割には、いい返しだと思った。手紙が存在しないなら、当然、写真も見せられない。偽造する手もあるが、ばれた場合のリスクを鑑みれば容易に取れる手ではない。
「それなら、お見せしましょう。ただし先に、あなた以外に『イチジョウ』という人物が読川署にいるかどうかを教えてください」
「それとこれとは話が別です」
「でしたら、お見せできませんわねえ」
わざとらしいお嬢さま言葉だった。読川署にほかの「イチジョウ」がいないことを確信して、一条をからかっている。
──なめやがって。
動揺と焦燥で一杯になった頭に、憤怒が加わった。
──そっちがそういう態度を取るなら、これはどうだ?
「仮に手紙が本当に存在して、そこに書いてあるとおり、高野さんが警察に事前に相談していたとします。だとしても、高野さんは緊急性があると伝わる言い方をしなかったのかもしれません。それなら警察は、動きようがなかったことになる。『週刊パンドラ』の今後を考えたら、記事にするかどうかは慎重に判断した方がよろしいのではありませんか」
記事にしたところで「高野の言い方に問題があった」「いや、なかった」の水掛け論になるからインパクトは薄くなる。警察を怒らせるだけでメリットはないぞ──言外にそのニュアンスを込めたが、藤峰は大袈裟に目を見開いた。
「なにを言ってるんです。高野さんの言い方にかかわらず、警察がそれを隠していることが問題なんじゃありませんか。それくらいの判断、誰でもつくと思うのですが」
頭の中が熱くなった。
あの電話だけでは動きようがなかったことを、知りもしないで……!
「ひょっとして一条さんは、高野さんから相談を受けながら、緊急性がないと判断したんですか。それなのに取り返しのつかないことになってしまったから必死に隠蔽しようとしているのですか。このことは鏡監察官も知っているんですか……って、あら、嫌だ。あなた以外にも一条さんがいるなら、隠蔽しようとしているのはその人かもしれないですよね。ごめんなさい」
こんなにも誠意がこもっていない謝罪は初めて受けた。明らかに、一条を挑発している。いまや動揺と焦燥、憤怒は渾然一体となり、自分がどんな感情を抱いているのか理解できなくなっていた。
「まあ、それはともかく」
藤峰は、一条の左手薬指に嵌められた指輪を一瞥して続ける。
「ご結婚なさっているようですが、いまの一条さんを見たら、ご家族はなんと言うでしょうね。被害者から相談があったことを隠蔽する卑怯者だと、がっかりするんじゃないですか。覚悟を決めて、いまこの場で真相を洗いざらい話したらどうですか。ご家族も世間からバッシングされるかもしれませんが、守って差し上げたらいいじゃないですか」
「家族は関係ないだろう」
「事件とは関係なくても、一条さんと無関係ではないでしょう。せっかくなら、お話をうかがいたい──」
「いい加減にしろ!」
怒鳴ったのが先か、立ち上がったのが先かはわからない。気がつけば座っていた椅子が後ろに倒れ、一条は藤峰を睨み下ろしていた。
体格のいい一条に怒鳴られたにもかかわらず、藤峰の顔に恐怖の色は微塵もない。満足そうな笑みを浮かべてすらいる。
──妙だ。
熱くなっていた頭の中が、急速に冷たくなっていった。
相手を挑発して怒らせ、おもしろおかしい記事を書く記者がいることは知っている。藤峰も、そういう類いの記者なのだとは思う。
しかしこの女の挑発の仕方には、現状では取るはずのない手段が含まれている。
なぜなら──。
「すごい迫力ですね、一条さん。そうやって犯罪者と対峙しているんですか。その迫力を高野さんのためにも使っていれば、事件は防げたかもしれませんね」
引き続きの挑発を無視した一条は、倒してしまった椅子を立てて座り直した。藤峰を見据えながら、この女と対峙してからいままでのできごとを逐一思い出す。
「一条さん? なんで急に黙るんですか? 私一人でしゃべるのはさみしいですよ?」
一条が声を荒らげたときですら余裕を見せていた藤峰の顔に、微かに困惑が滲んだ。無視して、引き続き思考を巡らせる。
よくよく考えれば、藤峰があれを取り出したことは不自然だ。だとしたら……確証は持てないが……ここは下手にさぐりを入れるより、強気に出た方が……。
奥歯を強く噛みしめてから、一条は口を開く。
「取材は中止です」
虚を衝かれた顔になった藤峰だが、すぐに笑って首を横に振った。
「耳に痛い話をされているからって、それはないでしょう。取材を終わらせたいなら、高野さんから相談があったことを認めて──」
「そうじゃない」
藤峰を遮って告げる。
「藤峰さんが約束を反故にしたからです」
4
「反故って、なんのことです?」
藤峰は笑いながら首を傾げたが、その直前、微かに視線が揺らいだ。
──いける。
「録音だ」
テーブルの下で拳を握りしめた一条は、敢えて敬語を排して言った。
「この取材を、私は録音も録画も許可しない約束で受けた。しかし、あんたはこっそり録音している。約束を反故にしたということだ。よって、取材は中止だ」
「録音なんてしてませんよ。最初に一条さんが、発見器で調べた──」
「だったら、胸ポケットに挿したそのペンを見せてみろ」
藤峰が顔を強張らせ、胸ポケットに挿したボールペンに目を向けた。すぐに一条に視線を戻し、再び笑みを浮かべたものの、先ほどまでより明らかにぎこちない。
どうやら、一条の考えは当たっていたようだ。
最初に引っかかったのは、藤峰が挑発に一条の家族を持ち出したことだった。いくら相手を挑発するためとはいえ、『週刊パンドラ』の記者がいまこの手を取るとは思えない。なにしろ先月、不倫した国会議員の家族を追い回しネットで大炎上したばかりなのだ。家族に関する話題はタブーのはず。
藤峰が無能な記者だというならわかるが、一人で東京からQ県まで取材に来ている上に、監察官である鏡に無茶な取材を呑ませているのだ。有能であることは疑いようがない。それなのに家族の話を持ち出したのは、取材は二の次で、一条を怒らせることを優先しているとしか思えない。
なんのためにタブーを犯した? 理由を考えるため藤峰の言動を振り返っているうちに、不可解な点に気づいた。
──失礼。インクが切れていました。
藤峰はそう言って、ペンケースから予備のものと思しきボールペンを取り出した。
なぜ、わざわざペンケースから取り出した? ジャケットの胸ポケットに挿してあるのに。
使っているボールペンのインクが切れたのなら、取材相手を待たせないようにするためにも、胸ポケットのボールペンを使う方が自然だ。しかし藤峰は、そうしなかった。不可解だが、ボールペンとしては使えない──ペン型のボイスレコーダーであるなら腑に落ちる。
ペン型のボイスレコーダーは、パワハラやモラハラの証拠を確保するためなど、堂々と録音できない局面で使われることが多い。取材相手に隠れて録音する場合にも用いられるようだ。
普通のボールペンとして使えるものもあるが、藤峰が用意したのはそのタイプではないのだろう。
この取材が始まる前、一条が使った棒状の発見器は、盗聴器や盗撮カメラが発する電磁波を検知する仕組みだ。あの時点で藤峰は、ボイスレコーダーのスイッチを入れていなかった。だから発見器は無反応だった。
その後、藤峰は胸の前で腕を交差させた。胸の膨らみを強調しているようで一条は目を逸らしてしまったが、その隙にボイスレコーダーのスイッチを入れたに違いない。
サイズの小さなブラウスとジャケットも、丈の短すぎるスカートも、「藤峰は胸の膨らみを強調するような女」と一条に印象づけるために選んだ服なのだろう。
藤峰は、ぎこちない笑みを浮かべたまま言った。
「どうして私が、ペンを見せないといけないんです?」
「そこにあるのはボイスレコーダーで間違いなさそうだな」
藤峰を無視して、一条は告げた。
「あんたは俺を怒らせるために、挑発を繰り返した。それを隠し録りして都合のいいように編集し、『週刊パンドラ』のサイトにアップするつもりだったんだ。Q県警が『録音も録画もしない約束で取材を受けた』と主張したところで、世間は『高野さんを救えなかったくせに逆ギレしている』とバッシングするのに夢中で、聞く耳を持たないことは目に見えているからな」
目論見どおりに行っていたらと思うと、ぞっとする。とはいえ、藤峰が約束を反故にしてまで一条の音声を隠し録りしたということは。
「あんたは、高野さんが事前にQ県警に相談したと決めつけているが、証拠はないんだろう。高野さんの海外の友だちも、手紙も存在しない。だから大衆を味方につけようとした。世間の批判が高まれば、Q県警は第三者委員会をつくって内部調査をしないわけにはいかなくなるからな。違うか?」
もちろん、冷静さを失した一条がこの場で隠蔽を認めることが、藤峰にとって最善だっただろうが。
藤峰は、ぎこちない笑みを浮かべたまま黙している。いまや形勢は、完全に逆転した。
「答えたくないなら構わない。しかし約束を破ったんだから、取材は終わりだ。その前に、ボイスレコーダーをこちらに渡してもらおう」
「これは……ただの、ペンです」
「だったら見せてみろ」
一条が右手を伸ばしても、藤峰は唇を噛みしめ動かない。顔つきが、先ほどまでより幼く見えた。一条と同世代だと思っていたが、まだ二十代前半かもしれない。
「渡さないなら、それでもいい。だがいまこの場で、鏡監察官に報告させてもらう。あの人といろいろ取り引きをしているようだが、それも今日までだな」
「ま……待ってください!」
スマホを手にした一条に、藤峰はすがりつくように言った。
「お願いします……それだけは……鏡監察官に話すのだけは……」
なんと言われようと、藤峰の取材がどうなったか鏡に伝えないわけにはいかない。しかし一条の脳裏に、一計が浮かんだ。
「そこまで言うなら、鏡監察官に話すかどうかは考えてもいい。ただし、あんたがボイスレコーダーを渡した上で、こちらの要求を呑むのであればだ」
「要求って……なんですか?」
「なぜ高野さんがQ県警に相談したと思い込んでいたのか? 取材相手に私を選んだのか? それを教えることだ」
これだけは答えを出せないでいた。とはいえ、落ち着いて考えれば察しがつく。
読川署内に、内通者がいるのだ。
その人物を洗い出すことができれば、鏡への手土産になる。
藤峰は目を伏せた。
「それを教えれば……本当に今日のことは、鏡監察官に内緒にしてもらえるんですか」
「約束する」
噓をついた。内通者を聞き出してボイスレコーダーを受け取ったら、鏡に連絡する。一条は、この女の茶番につき合わされたのだ。これくらいやっても罰は当たるまい。
藤峰は目を伏せたままでいる。迷っているようだが、選択の余地はないはずだ。一条が悠々と見つめていると、なんの前触れもなく貸し会議室のドアが開いた。反射的に目を向けた一条は、息を呑む。
「すばらしい、合格だ」
満面の笑みを浮かべ立っていたのは、鏡真人だった。
「鏡監察官が、なぜここに?」
一条は事態を理解できないまま言った。取材が今日であることは伝えたが、「いちいち俺の手を煩わせるな」と一喝されたので時間と場所は教えていない。
「驚かせてすまないね」
鏡の声音は、先日とは別人のように穏やかだった。口許にはあたたかな笑み。まだ五十歳前後のはずだが、「好々爺」という言葉がしっくり来る。
「私はもう失礼させてもらっていいですね」
藤峰が立ち上がりながら言った。こちらは先ほどまでの、余裕漂う顔つきに戻っている。年齢も再び、一条と同世代に見えた。いや、少し上か?
「構わないよ。お疲れさまだった」
「おそれ入ります──じゃあ、一条さん。鏡監察官とごゆっくり」
藤峰は一条に向かって軽く手を振り、退室した。
「あの記者とはいろいろ取り引きしていると聞きましたが……随分と、その……親しいようですね」
半ば呆然としてピントのずれた言葉を口にすると、鏡は言った。
「彼女は記者ではない、警察官だ」
「は?」
「以前は所轄の生活安全課にいて、いろいろなタイプの女性に化けて捜査をしていた。その技能を買って、いまは私の下で働いてもらっている。『藤峰』というのも偽名だ」
つまり、鏡の部下が『週刊パンドラ』の記者を装い、一条に〝取材〟していたというわけか。状況はわかったものの、却って混乱してしまう。
「順を追って説明しよう」
鏡は、藤峰が座っていた椅子に腰を下ろした。
「まず、君にこれまでの非礼を詫びよう。怒鳴りつけたり、威嚇するような言い方をしたりと、パワハラを繰り返してしまったね。意図的にやったこととはいえ、申し訳なかった」
鏡が頭を下げてきた。一条への態度にも裏があったのか。
「なぜ監察官は、そんなことを?」
「ストレスによって、君を追い込むためだ。君は独身寮に住んでいたとき、隣室の先輩に苦労させられたと聞いている。私の言動によって彼のことを思い出せば、よりストレスが大きくなると考えた」
独身寮時代の先輩は、確かに迷惑だったが上司に報告したわけではないので大事にはなっていない。知っている者は、一条の同期など親しい間柄の者にかぎられる。
それなのに、鏡は把握している。一体どんな情報網を持っているのか……背筋が冷たくなった。
「私は君にストレスをかけた上で、確かめたいことが二つあって今回のテストをしかけた」
鏡は穏やかな声音のまま、右手の人差し指と中指を立てた。
「一つは、頭の回転だ。万が一マスコミに高野さんの件を嗅ぎつけられたとき、適切に対処できるか見てみたかった。そのために、先ほどの彼女に記者のふりをさせたんだ。彼女と君のやり取りは、すべてチェックさせてもらったよ」
「チェックって……どうやって? ドアは店のカウンターから見える位置にあるし、隣り合っている部屋もない。盗聴器やカメラがしかけられていないことも確認済みです」
「この店には、店主しか知らない隠し部屋があるんだ。それを使わせてもらった」
鏡の視線が、壁に設置された大きな鏡に向けられた。あれはマジックミラーで、その先には隠し部屋があるということか。だからはずせないよう、壁にぴたりとつけられている。
伊達や酔狂でそんな部屋をつくる者などいない。おそらく店主は、鏡のS──即ち、スパイ。鏡はこれまでも、今回のようにこの店を使ったことがあるに違いない。
「私はたまたま、監察官にとって都合のいい店を選んでしまったというわけですか」
「そうだね。ただ、君がここを選んでくれることを望んでいた。この近辺には、ほかに立ち聞きされる心配をしないで済む部屋がある店はないからね。期待に応えてくれてうれしかったよ。ホテルを選んでくれてもよかったが、彼女に騒がれては面倒なことになるから避けるだろうと思った」
まるで自分の思考をたどられているようだった。一条がぞっとしている間に、鏡は続ける。
「多少危なっかしいところはあったが、彼女の取材攻勢に君はよく耐えた。高野さんから相談があったことは最後まで認めなかったし、ペン型ボイスレコーダーの存在を見抜いた点も評価できる」
この言い方からすると。
「彼女はわざとボールペンのインクが切れたと言って、ペンケースから代わりを取り出したのですか」
「そうだよ。君が水準以上の洞察力を持っていれば、胸に挿したボールペンを使わないことが不自然だと気づき、ペン型ボイスレコーダーであると見抜ける。それを口実に取材を打ち切ることができる……というルートを用意しておいた。ボールペンとしても使えるレコーダーを用意しなかったのは、君にヒントを与えるためだ。名前のルートも用意したのだが、こちらにはさすがに気づかなかったようだね」
「名前?」
「彼女は君の名刺を見て、『一条直』と読み間違えただろう。しかし私は君に、こう言ったはずだ。向こうが『読川署のイチジョウチョク』とわざわざフルネームで指名してきた、と」
鏡の言わんとしていることがわかった。
「気づいたようだね。そうだ。取材を申し込んだ時点で、『週刊パンドラ』側は君の名前を正しく認識していた。しかし、実際に記者に会ったら間違っている。矛盾しているだろう。彼女が名前を読み間違えたとき君がこのことを指摘すれば、その時点で私が部屋に入ってテストは終わりにするつもりだった」
鏡が「イチジョウチョク」の一言をわざわざ一音一音区切って口にしたのは、『週刊パンドラ』側が一条の名前を正しく認識していることを印象づけるためだったのだろう。これもまた、鏡のヒントだったわけか。
鏡は笑顔で拍手する。
「名前には気づかなかったが、君は充分よくやった。最後にはなぜ高野さんがQ県警に相談したと彼女が思い込んでいたのか、取材相手に自分を選んだのかと訊ねていたね。あそこまでしてくれるとは思わなかったよ。聞き出した後は、彼女との約束を破って私に取材の結果を報告するつもりだったんだろう」
すべて読まれている。本当に思考をたどられているようだ。
「これだけ頭の回転の速さを見せてくれたんだ。高野さんの件について、君は外部からなにか言われても簡単には口を割らないと確信できた。君が期待に応えてくれなかった場合は内勤に回すつもりだったのだが、手間が省けたよ」
──人を試すような真似をしやがって。
当然、その不満は大いにある。
しかし、悪い気がしていないことも事実だった。
なにしろ、相手は「Q県警の番人」だ。自尊心をくすぐられないはずがない。
一条を見つめる鏡の双眸は、木漏れ日を思わせた。おそらく鏡は、必要とあれば、これまでも部下にパワハラまがいの態度を取ることがあったのではないか。それが、後輩に厳しく、怒鳴りつけることも珍しくないという噂につながったのではないか。
しかし、噂はあくまで噂だった。
「テストで確かめたかったことは二つあるのですよね。もう一つはなんですか」
訊ねる一条の声は、わずかではあるが弾んでいた。二つ目も、耳に心地よいものに違いない。いい年をして恥ずかしいが、『無敵剣士セイバースター』に登場した、厳しくも温厚な老師と話している気がしていた。
「後ろめたさに押しつぶされない強さを持っているかどうか、だよ」
「強さ」という単語を耳にして、予想どおりほめられたと思いかけた。しかし、どこか違和感がある。その理由を解き明かす前に、鏡は言った。
「君は、自分の身が一番かわいいだろう」
刹那、呼吸がとまった。
鏡は、あたたかな笑みを浮かべたまま続ける。
「たとえ緊急性が認められなかったとしても、自分の対応次第で被害者を救えたかもしれないと思えば、後ろめたさが芽生えるものだ。君にその感情が、まったくないわけではないだろう。しかし、自分の身を守ることを優先している。だから半月前、私の命令に唯々諾々と従って、高野さんからの相談を隠蔽することに同意した」
「そう言われましても……上官の命令だから……あなたに、そんなことを言われる覚えは……」
狼狽のあまり、刃向かっていると断じられても仕方のない言葉を発してしまった。鏡は、気を悪くした風もなく頷く。
「もちろんだ。しかし、君は私に強くは抵抗しなかっただろう。それでいい。警察という組織に必要なのは、君のような人材だ。後ろめたさと正義感を履き違えて内部告発する輩がいては、組織が成り立たなくなる。延いてはそれが警察不信を招き、多くの国民を苦しめることになる」
〝それでいい〟
〝必要なのは、君のような人材〟
それらの言葉に少しも自己肯定感を抱けないまま、一条は半ば独り言のように言った。
「それは、つまり……私が保身に走る男である、と……?」
「そうとも言うね──ああ、誤解しないでくれ。君が職務をまじめに遂行していることはわかっている。だからこそ、許される保身だ。単に保身に走っているだけの警察官であれば、テストするまでもなく早々に左遷している」
保身? この俺が? 違う、そんなことはない……。
鏡は鏡なりに、一条を認めてくれているようだ。このまま黙っていれば、波風立てずにやりすごすことができる。それは承知の上でどうしてもこらえ切れず、一条は口を開いた。
「私は、自分なりの正義を貫いてきました」
鏡が眉根を寄せる。
「正義?」
「そうです。人の数だけ正義があるから、絶対的に正しいことなんてない。ですから私は、せめて『不正はしない』と思って警察官をやってきた。今回、隠蔽に加担するのはやむをえない例外であり──」
「誰かの正義に加担すれば自分が傷つくから、『不正はしない』という正義に逃げただけだろう。それこそ、まさに保身じゃないか」
鏡の声音は依然として穏やかなのに、胸に深々と突き刺さった。
警察官になって二年目。「同棲相手の男に殴られた」という女からの通報を受けて臨場した一条は、「自分こそが正しい」と訴える男女二人に鬼気迫る表情で詰め寄られ、身の危険を感じた。不正をしないよう職務に務めなくては、と思ったのはそれからだ。
鏡監察官の言うとおりなのか? 俺は自分が傷つくのがこわくて、逃げることにしただけなのか?
浮かんだ疑問に答えを出したくなくて、一条はとにかく口を動かした。
「保身が全然なかったとは言いませんが……少なくとも今回は違う……家族のためであって……だからこそ、監察官の命令に従うことに……」
「家族がいなくて天涯孤独の身であれば私の命令に従わずすべてを話していた、と?」
「もちろんです」
自分の立場を悪くするかもしれないことは承知で、即答した。
鏡もまた、即座に返してくる。
「君は今日、一度でも殺された高野さんに申し訳ないと思ったかね?」
あ──。
藤峰と名乗っていた、先ほどの女と対峙した記憶が蘇る。
あの間、高野のことを何度も思い出しはした。
しかし鏡に指摘された感情は抱いていない、一度たりとも。
鏡は唇をきつく噛みしめてから、声を絞り出すようにして言った。
「君は──いや、失礼、Q県警は、高野さんを救えなかった。救う術はなかったのだから、相談の電話があったことを公にする必要はない。しかし、救えなかったという事実が消えるわけではない」
目を閉じた鏡の痩躯が、一度ぶるりと震えた。初対面のときも、鏡は一条に「忘れろ」と告げた後、身体を震わせていた。怒鳴られると思って身構えた一条だったが、あのときの鏡は怒りに駆られていたわけではなく──。
目を開けた鏡は、穏やかな声音に戻って続ける。
「私に言わせれば、君は国民を守ることを旨とする、正義の警察官だ。ただしその正義は、自分が傷つかない範囲でのみ発揮される。否定したいようだが、そういう人間であることを受け入れなさい。それが、国民を守る組織に奉仕する者の義務だ」
鏡の声音は最後まで穏やかで、口許にはあたたかな笑みが浮かんでいた。
帰路の間ずっと、鏡から最後に言われた言葉が頭の中で残響していた。
あの人の言うとおりだ、と思う。
事件を知った直後、どうすれば高野を救えたのかと何度も自問した。しかし、「どうしようもなかった」という結論を下し、罪悪感はほとんど抱かなかった。その後は、厄介なことに巻き込まれたと自分を哀れんですらいた。挙げ句、家族を言い訳にして、鏡の命令に従うことを正当化した。
性質の悪いことに、それを自覚してもなお、高野への後ろめたさよりも、自分が相談の電話を受けた事実を世間に知られずに済むという安堵の方が大きい……。
夏を思わせる午後の陽射しが、首筋を容赦なく焼いてくる。そのせいで、全身が燃えるように熱くなっているのが太陽のせいなのか、自分が抱く感情のせいなのか判然としない。
自宅の警察官舎に到着した。一見、周囲の建物と大差ない、二階建てのマンションだ。二階の角部屋、締め切った窓の向こうには優花と奏汰がいる。二人の顔が浮かぶのと同時に、つまらなそうに仕事する瀬尾をニュースで見たときのことを思い出した。
あのとき一条は、「不正をしない」という自分なりの正義を貫くと誓った。
これから先は、この正義を貫き通す。鏡に話したとおり、今回は本当に例外だ。
──そうしないと、瀬尾っちに顔向けできない。
足を引きずるようにして階段を上がり、玄関のドアを開けた。
「ただいま」
「お帰りなさい」の一言とともに、優花が駆けてきた。普段おっとりしているだけに珍しい。
「瀬尾さんが、すごいことになってるわよ」
「なにかあったのか」
「これ」
ぼんやり訊ねる一条に、優花はスマホを差し出してきた。ディスプレイには、Q県のテレビ局が運営するニュースサイトの動画が表示されている。
そこに、瀬尾が映っていた。
スマホを受け取り、リビングに向かいながら動画を見る。瀬尾は会議室のような部屋で、マイクを複数突きつけられていた。
〈魅力発信事業に不正があったということでいいんですね〉
瀬尾にマイクを突きつける誰かが訊ねた。魅力発信事業……どこかで耳にした単語だ。少し考えて、瀬尾がニュースで語っていた、魚前町が始めた事業であることを思い出す。
〈そうです。事業を担当しているPR会社は、あの……町長の親戚が経営しておりまして……一応、企画競争入札をしたのですが……ええと……このPR会社以外は個人事務所が一社しか参加せず……まともに告知もしていなかったから、当然で……町長の親戚の会社と結果が決まっていた出来レースと言われても仕方がないかと……〉
たどたどしく答える瀬尾の額は、汗でてかっていた。この状況は……。
「瀬尾が不正を告発したのか?」
呆然と呟く一条に、優花は頷いた。
「そうみたい。しかも瀬尾さん自身も、かかわっていたんですって」
〈私自身にも……せき……責任があると、思っております〉
まるで優花の声が聞こえたかのようなタイミングで、瀬尾は言った。
〈私は、入札の担当もしておりまして……もっと告知して参加事業者を募るべきだと言ったのですが、上司に『必要ない』と言われたら、あの……あとは、見て見ぬふりを……町民のみなさんを裏切ってしまったことを……お詫び……お詫びするしか……〉
〈それはいつのことです?〉
〈一年ほど前、です。もっと早く告発するべきだと……でも、しようとする度に、こわくなって……ただ、夏休みには大きなイベントがありますから、その前にどうしても、と……〉
瀬尾が勤務する魚前町役場で、新規事業に絡んで町長とPR会社の間で談合が行われていた。瀬尾自身もそれに巻き込まれた、といったところか。
この前のニュースで瀬尾がつまらなそうにしていた理由は、これだったのか……。
愕然としているうちに、動画が終わった。生中継ではなく、録画だったようだ。
「瀬尾さんは、さっき記者会見したみたい。自分だって大変なことになるだろうに。かっこいいよね」
優花の感嘆の吐息が、一条の鼓膜を揺らした。
「かっこいい! 正義の味方!」
意味はわかっていないだろうが、奏汰が無邪気に優花に同調する。
微妙な案件だ、と思う。
無論、名目だけの入札などほめられたものではない。ただ、魚前町のような田舎町が大々的に告知したところで、手をあげるPR会社はなかったはずだ。その分の予算を事業に割いた方が効果的という考えもできる。それに個人事務所の参加を認めたのだから、最低限の審査はしたのだろう。瀬尾は「出来レース」と言うが、町長の親戚が経営しているというPR会社は夏休み中に人気アイドルグループを呼ぶくらいだから、よくやってもいる。個人事務所にここまでできたとは思えない。親戚だからこそ、阿吽の呼吸で動いてくれる気安さもあるに違いない。
しかし、それは行政の理屈だ。世間はそうは思うまい。不正であることは確かだし、アイドルグループが絡んでいるだけに注目も集まりやすい。この先、魚前町役場はマスコミやSNSでたたかれ、混乱に陥ることだろう。
──鏡監察官が瀬尾っちに『警察官に向いていない』と言った理由は、これなんじゃないか?
鏡の定義に当てはめれば、瀬尾は後ろめたさと正義感を履き違えて内部告発する輩となる。
しかしスマホの中で停止した瀬尾は、先日ニュースで見たときより、ずっと雄々しく見えた。汗だくな上に双眸が虚ろで、見た目はお世辞にもいいとは言えないのに。
瀬尾の分まで自分なりの正義を貫くと誓った。しかし、当の瀬尾が……。
優花に顔を向けた。いま目にした瀬尾の姿を思い浮かべながら、この半月ほどのできごとを話そうとする。
しかし、唇の上下が貼りついてしまったかのように動かない。
優花が心配そうに言った。
「どうしたの? なんで泣いてるの?」
「……なんでもない」
スマホを返した一条は目許を拭い、心中で瀬尾に呼びかけた。
──瀬尾っちの方こそ『正義の味方』だよ。