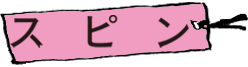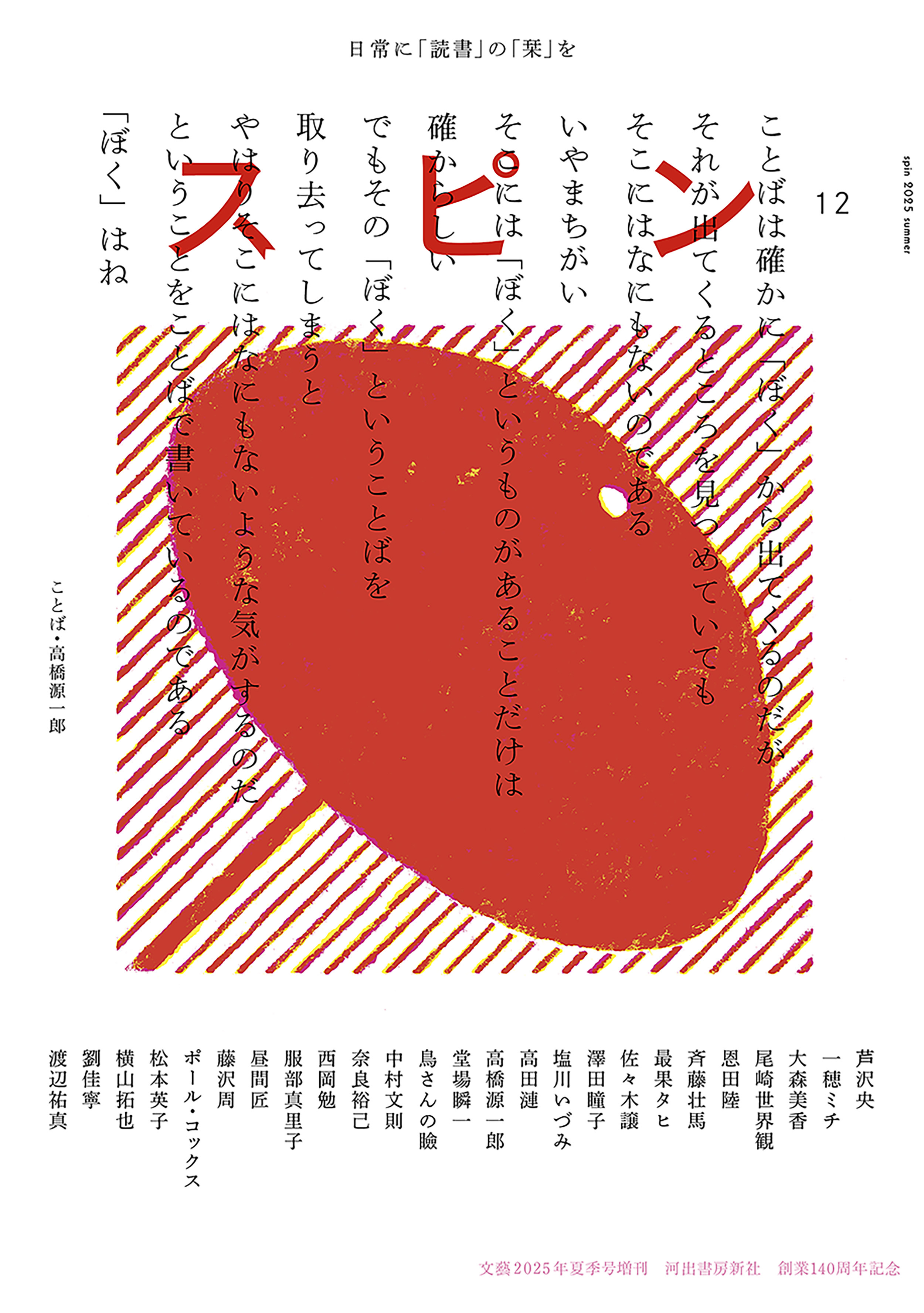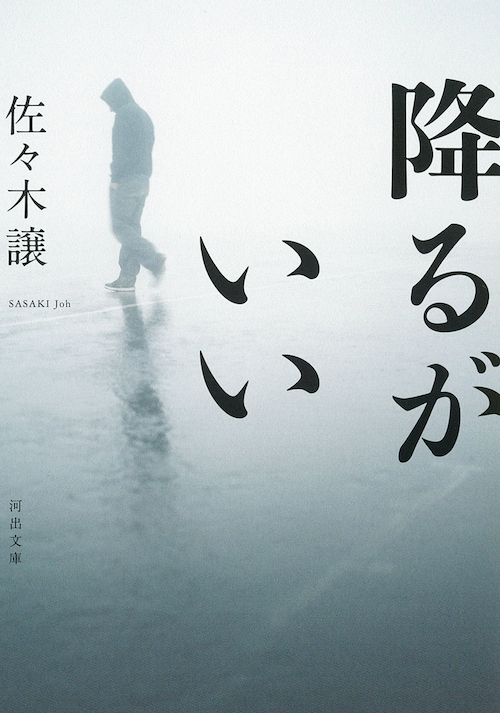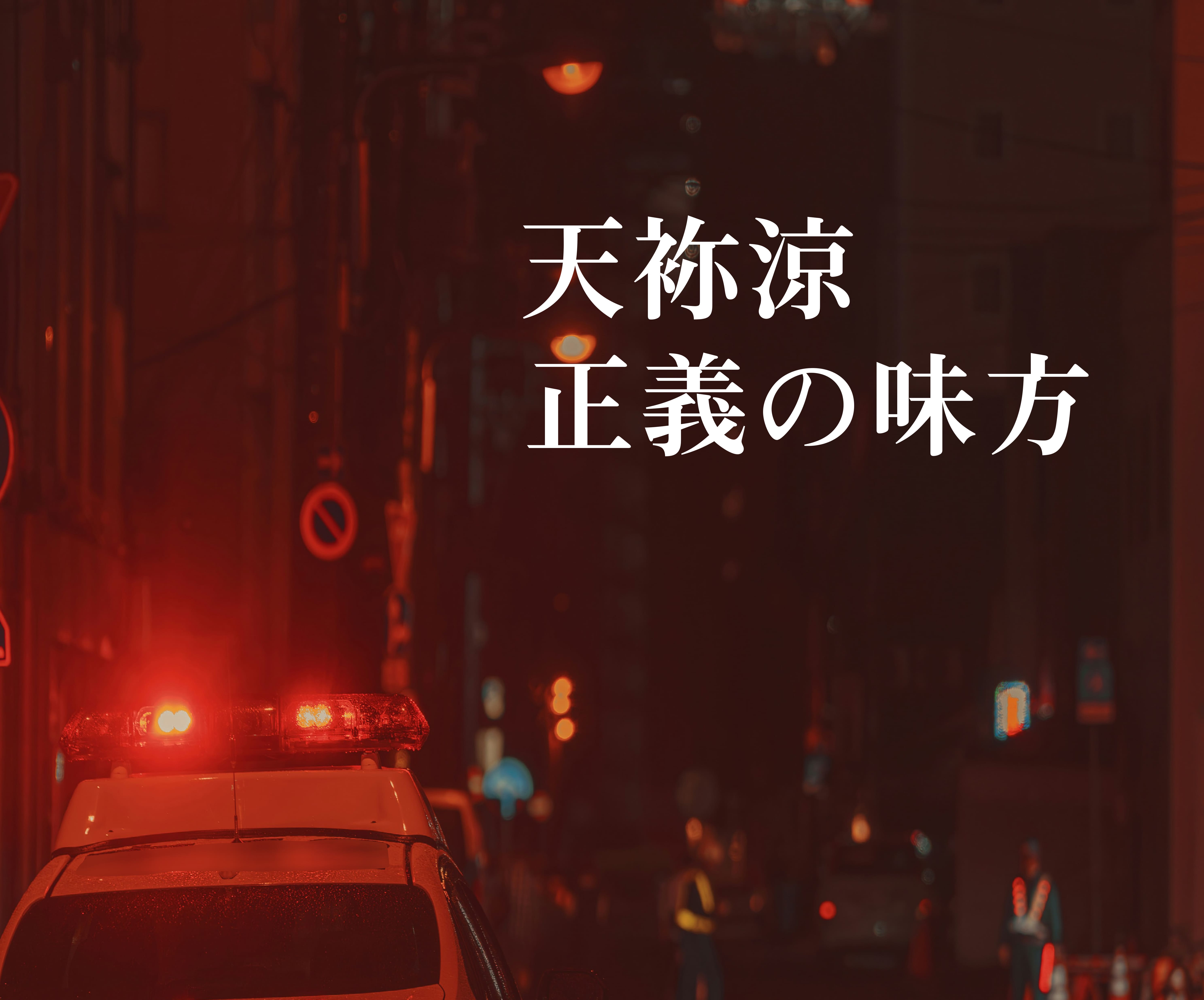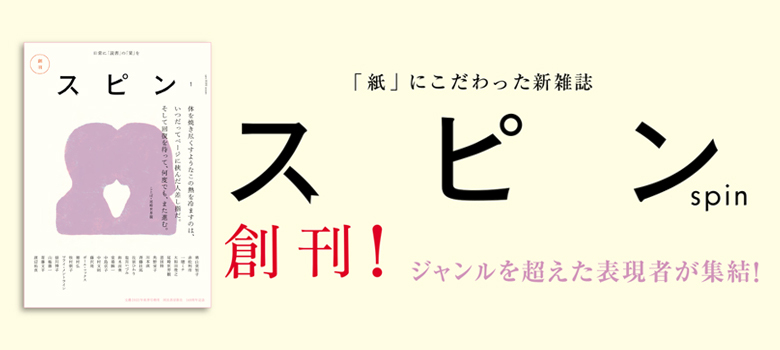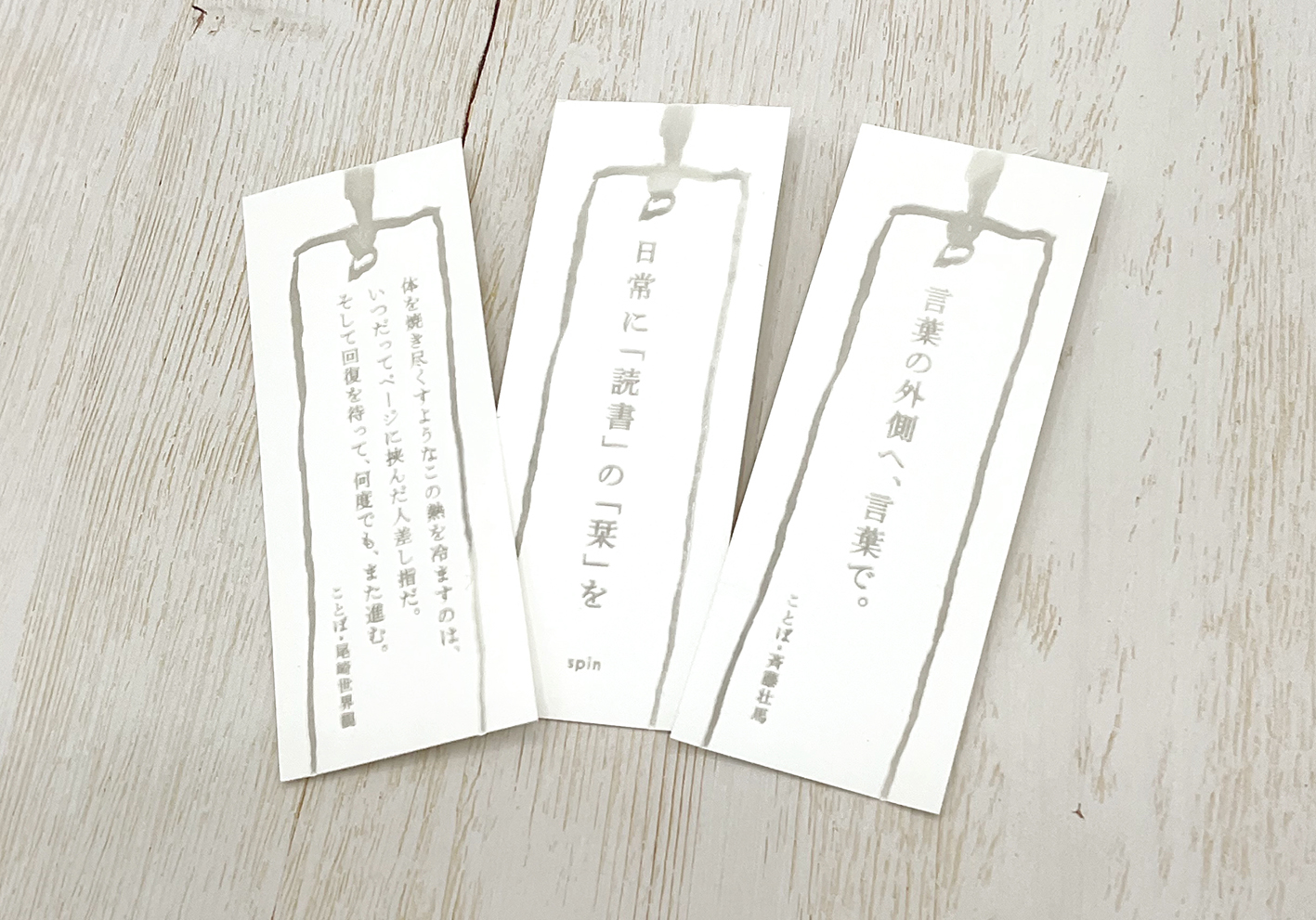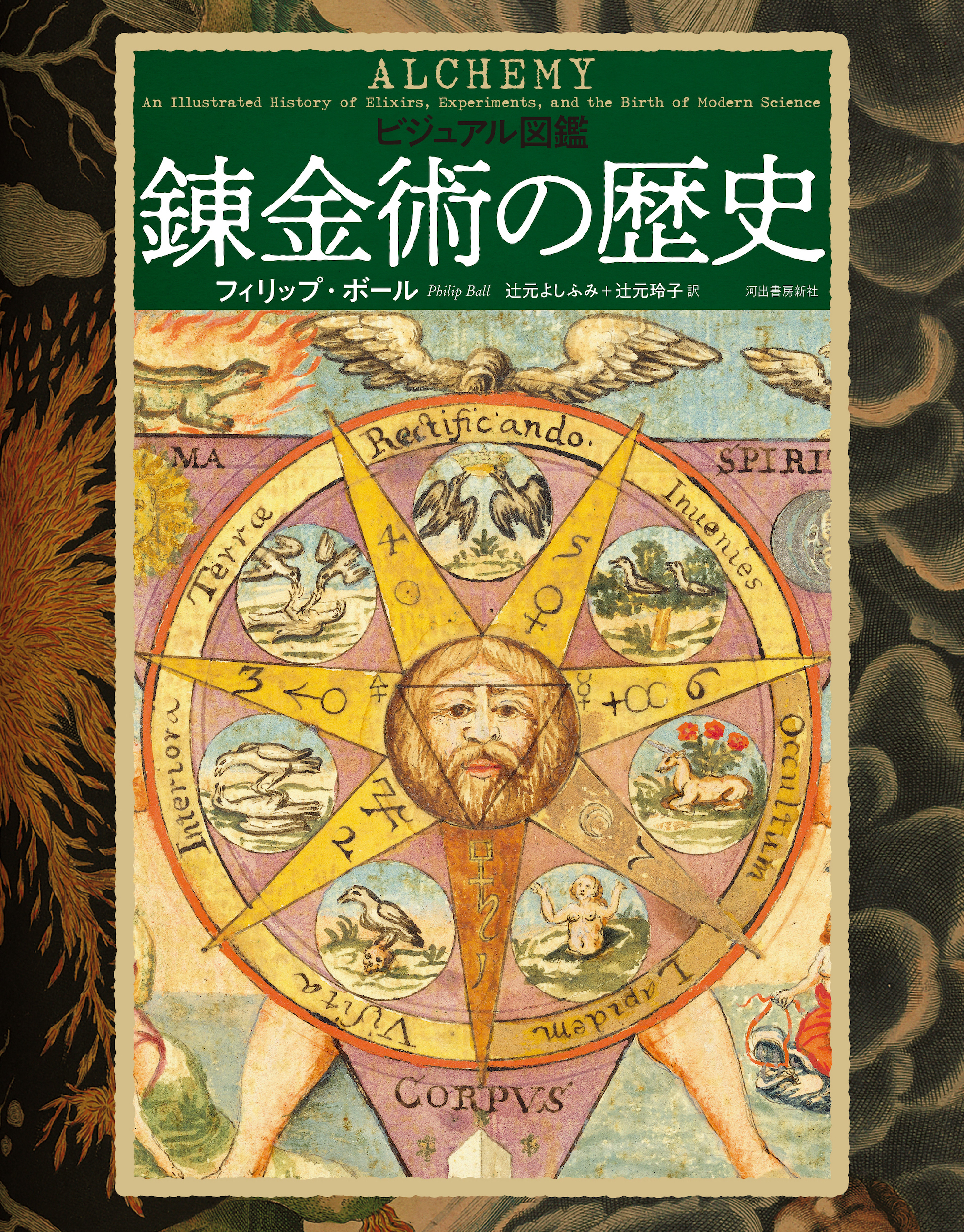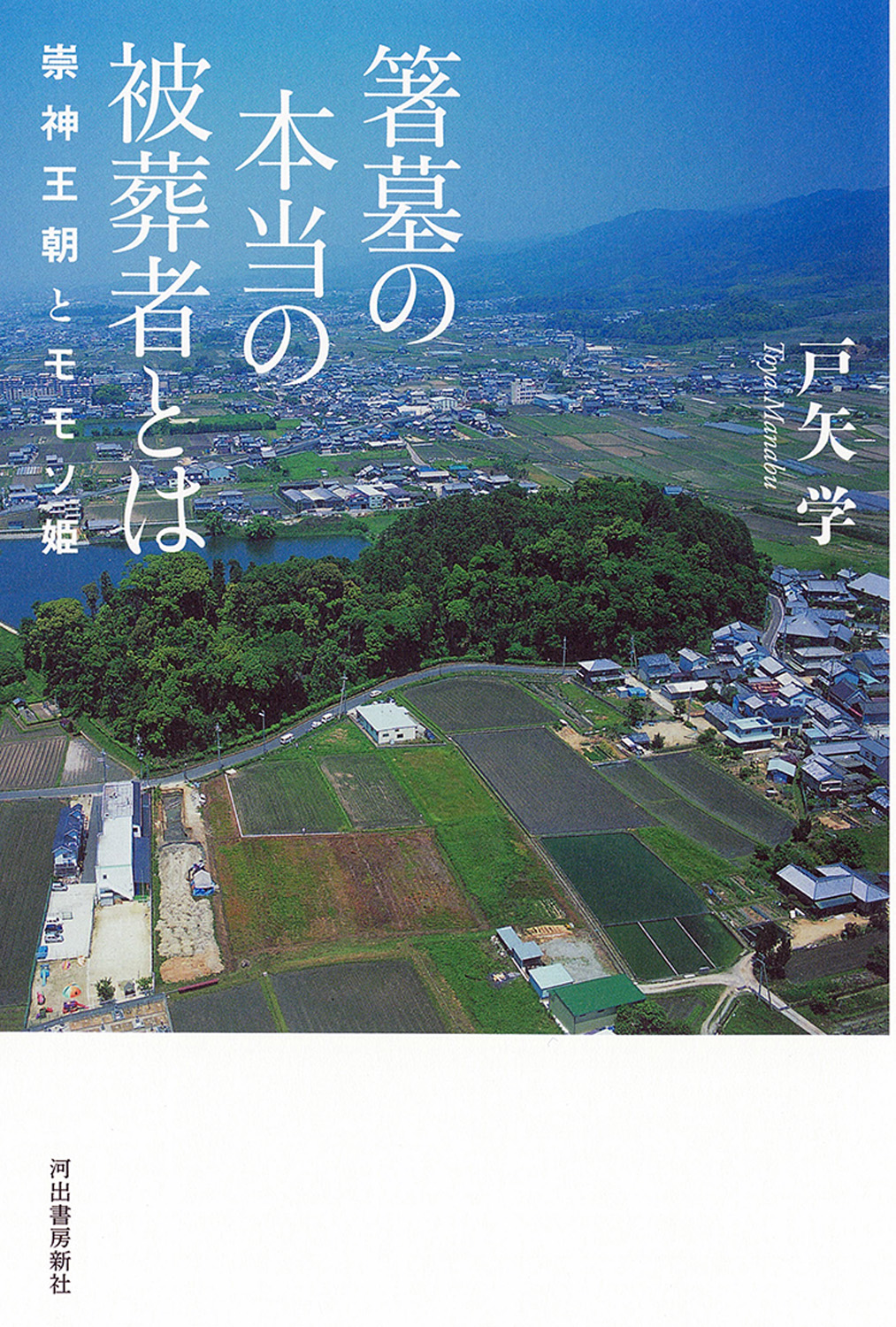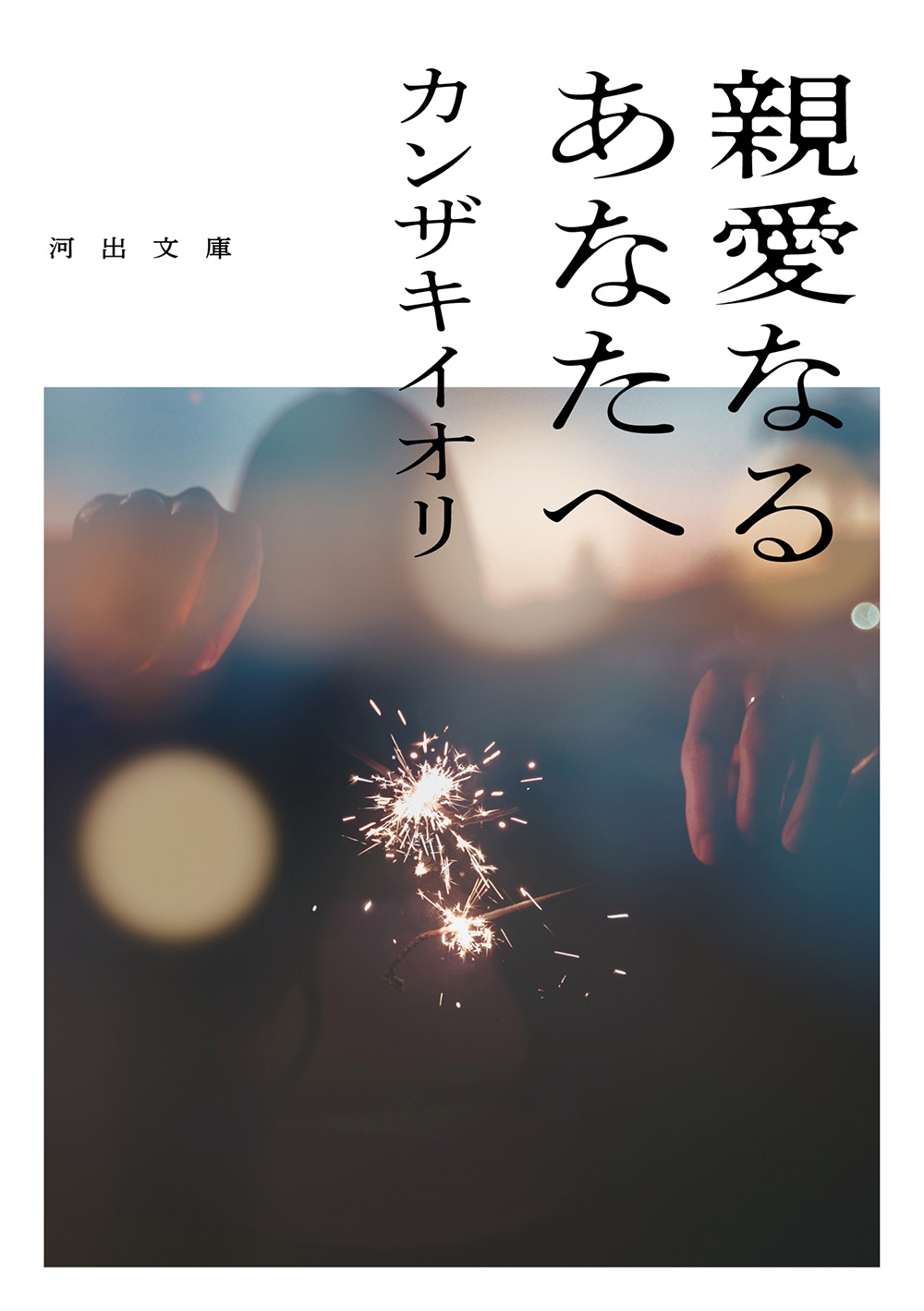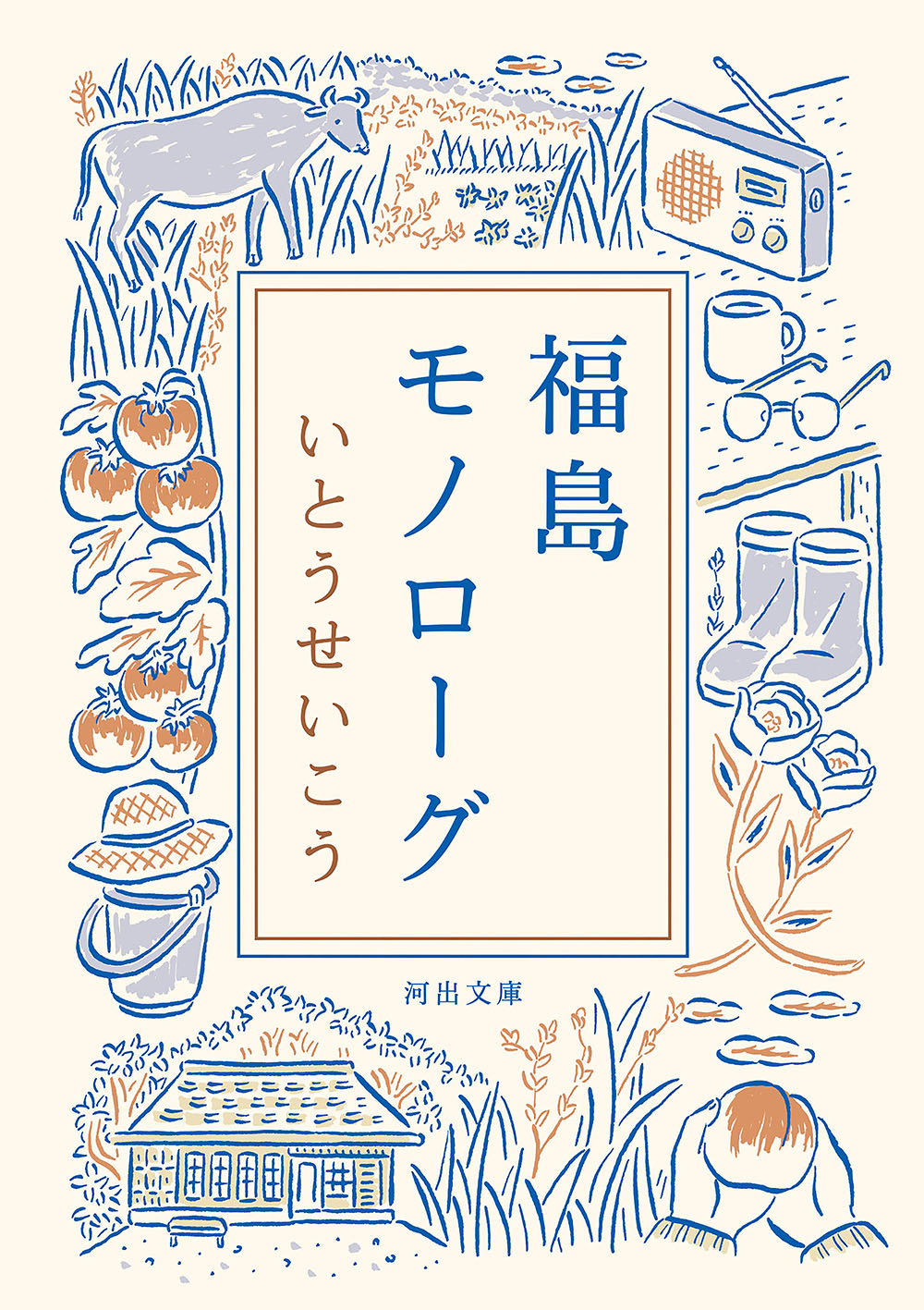読み物 - 読み物
路上の輝き 第2回
佐々木譲
2025.09.20

ふと気がつくと、はやぶさ十号は荒川を渡っていた。
東北新幹線は、盛岡から東京都内まで二時間余で移動するのだ。修平はいまだにこの速さに慣れていない。とうに新幹線の移動の数のほうが、在来線での移動の数を上回っているのにだ。
修平は棚から大きめの帆布のリュックサックを下ろして背負い、ショルダーバッグを肩にかけた。きょうはまず冬樹のアパートに行くことにしているので、東京駅ではなく上野駅で降りるのだ。
上野駅のプラットホームへ降りて、地上の新幹線改札口を出た。ここから先は、いまだに五十年前の面影のある上野駅だ。
修平は通路の隅に寄って電話をした。
「よ、修さん」と、冬樹の声は予想よりもずっと明るいものだった。「着いたの?」
「ああ」と修平は答えた。「上野駅。これから行っても大丈夫かい?」
「ああ。田端駅まで迎えに行ったほうがいいかな」
いま冬樹が住んでいる部屋を、修平は訪ねたことがなかった。たしか十数年前、冬樹は六十歳を過ぎたあたりで、田端が最寄り駅のそのアパートに移っているのだ。
「いいや」と修平は断った。「目印だけ教えてもらえれば、行けると思う」
冬樹が健常者のように歩けるのかどうか心配したのだ。アパートから田端駅までの距離もよくわからない。彼の身体の状態を考えると、その程度の運動さえきついのかもしれないと思う。知り合ったころから冬樹はひょろりと細身で、運動などは極度に苦手だろうと想像できる体格だった。胸は薄く、腕も腿も細かった。いまは、あのころよりももっと痩せていておかしくない。
「じゃあ、まず」と冬樹が教えてくれた。田端駅を降りて、駅前通りを南方向に進む。右手に墓地がある。三叉路まで来て、右手方向に折れる。お寺の山門がある。まずはそこまでが目印。
その山門の向かい側にある小路を進む。灰色の壁の、並びのアパートの中ではもっとも古く見える建物。外階段を上がって、三階の外廊下の手前から三つ目のドア。303。
「わからなくなったら、もう一回電話して」
「途中コンビニでもあれば、何か買ってゆこうか?」
「あ、頼めるかな。ペットボトルの水」
「ほかには何か?」
盛岡駅で名物の菓子のような土産物は、とくに買わなかったのだ。病状次第では、避けたほうがいいものもあるだろう。
「いや、それだけでいいよ」
山手線の田端駅で降りて、まずコンビニで二リットル入りの水のペットボトルを二本買った。それから教えられた目印を確認しつつ、その建物の前まで歩いた。冬樹が教えてくれたとおりの外観のアパートがあった。
階段はスチールではなく、建物の一部となっていて、外壁がある。その階段を三階まで上がり、外廊下の奥へと向かった。
ドアには表札は出ていないが、部屋番号は表示されている。303。
インターフォンを押したけれども、中でチャイムが鳴ったようではなかった。
修平はドアノブを回した。ロックされておらず、すっと手前に引くことができた。
開けながら、中に声をかけた。
「修平です」
すぐに声が返った。
「修さん、待ってたよ」
ほんのかすかに、そして冬樹には珍しく甘えも感じられる声だった。余命を告げられたひとりの暮らしでは、ひと恋しさがあっても当然だった。
玄関ドアの真正面にもドアがあって、開いている。その向こうで、ベッドの端に腰かけている冬樹が見えた。パジャマ姿だ。
「こんな格好だけど、上がってきてよ」
靴を脱ぎながら、修平は素早く観察した。
左手にシンクやらコンロがあり、その奥に冷蔵庫。通路をかねたキッチンだけれども、想像以上に片づいていた。料理をろくにしない男のキッチンだ。
通路の右側にドア。そこはユニットバスだろうか。典型的なワンルーム・マンションの造りだ。ただ、この建物はエレベーターのない三階建てだけれども。
通路を進み、部屋に入った。
「修さん」と、冬樹が目を細めて言った。「はるばるありがとう」
やはりもともと細身の身体が、さらに痩せているように見えた。
修平は、返事も待たずにドアを開けたことを弁解した。
「チャイムが鳴らなかったようなんで、開けてしまった」
冬樹が言った。
「電池が切れているみたいだ。たいして必要もないんで、そのままにしている」
ペットボトルの入ったレジ袋を提げたまま、自分がいるべき場所を探した。畳六枚分よりは多少広いかという程度の部屋だ。家具はろくにない。ベッドと、四角い食卓テーブルがひとつ。サイズはふたり用だろうか。それにふたつの椅子。食卓の上には、ノートパソコンが閉じて置かれている。封筒やチラシなどもまとめてあった。食卓は、ときには仕事机にもなっているのだろう。壁側に八十センチ幅の書棚が二架。スチール枠で布のカバーの衣類棚。
壁のフックには衣料品がかかり、二点、版画が掛けられていた。冬樹の著作の表紙に使われたものだとわかった。作者は別々だ。どちらも冬樹の友人の版画家の作品だ。
テレビはなく、レコード・プレーヤーもなかった。メリー・ホプキンのLPを探したが、目に見えるところには置かれていない。
部屋の様子は、ざっと見てそんなところだ。キッチンとは違って、この居室のほうは少し散らかっている。
少し遠慮なく、その部屋の中を観察してしまったかもしれない。
冬樹が言った。
「ま、そこの椅子に腰を下ろしてよ。部屋を観察されるのは、裸を見られているような気分になる」
「ごめん」と修平は苦笑して謝った。「ついこの部屋を俯瞰で描くとしたらと見てしまった」
「この部屋に越してきたときは、徹底的なミニマム・ライフを目指したんだ。だけど、やっぱりこの程度にはモノが増えてしまった。というか、なしでは暮らせなかった」
「人生はスーツケースふたつ」と、修平は冬樹がよく言っていた言葉を口にした。
冬樹がうなずいた。
「あんなことを言っていたときは、なんとなくずっと船の上での暮らしに憧れていたんだ。船室には、ビジネスホテルと同じ程度のモノは備えつけだし、自分の持ち物はスーツケースふたつで十分だろうと」
「じっさい冬樹さんは、そう生きたんだと思うけど」
「夢見ただけだよ」
「ニューヨークに行ったときは、ほんとうにスーツケースふたつだった」
冬樹が文化庁の何かの助成金を受けてニューヨークに派遣されることになったとき、奈津美と一緒に成田空港に送りに行くと、冬樹の荷物はほんとうにスーツケースふたつだけだった。正確に言えば、スーツケースが二個と、機内持ち込み用のショルダーバッグひとつ。少なくとも一年はいると聞いていたから、その荷物の少なさに修平は驚いたのだった。
冬樹はニューヨークから帰った後もいくつか住む都市を変えてきたが、そのときもたぶん荷物はじっさいにスーツケースふたつ程度だったのではないか。もっとも見送りに行ったのは冬樹がノースウエスト航空でニューヨークに向かったあのときだけだから、確実ではないかもしれないが。
修平は、レジ袋を食卓テーブルの下に置くと、椅子に腰をおろして冬樹に向かい合って訊いた。
「体調はどうなの?」
冬樹は微笑して答えた。
「このとおり、ステージ4とは見えないよね?」
「見えない」少しだけ嘘をついた。記憶よりも、頬が少しこけている。「ずっと寝ていた?」
「あ、いや、もうろくに外出する用事もないから、一日じゅうパジャマで過ごすことのほうが多いんだ」
「ほんとうに、広島までの旅行は大丈夫なのかい?」
「入院していないんだから、大丈夫だ。安静にしていろとは、言われていないわけだし。それから」冬樹はちらりと床の上の、ふくらんだ自分のショルダーバッグに目をやってから言った。「何もかもおんぶするわけにはいかないから、少し工面した」
旅費のことを言っているのだろう。それが可能な程度には、冬樹は困窮していないのだとわかった。少し安堵した。広島まで、冬樹につきあうつもりで来たが、自分も事実上の年金生活者であり、財布にはあまり余裕はないのだった。
「どっちみち」と修平は言った。「奈津美ちゃんから案内が届いて、行くつもりになっていた。ひとりで行っても、つまらないだろうし」
スマートフォンの着信音らしき音が鳴った。
小さなピープ音だ。自分のではない。
冬樹が身体の脇からスマートフォンを取り上げて画面を見てから言った。
「千春が来る。駅に着いた」
ときどきこの部屋に来て世話をしてくれている、と聞いた女性のことだ。近藤千春。彼女を紹介されたのもずいぶん以前だ。
「一回会っているひとだね」
冬樹は笑った。
「何を言っているんだい。何度も会ってる」
「お芝居に出ていたひとじゃなかったっけ?」
「そうだよ。千春」
冬樹が芝居の演出も手がけるようになったころ、どれかの公演のときに、その芝居の周囲の関係者の中に近藤千春がいて、紹介された。でも、何度も会っていたか?
「記憶が混乱しているな」
「違う女性と?」
「いや、そういうことじゃないけど。ぼくは、はずしたほうがいいかな」
「むしろいてもらったほうがいい。旅行のことを相談したくて、来てもらったんだ。千春は、広島に行くのは反対なんだ。修さんが付き添ってくれるにしても」
「身体の状態では、無理ということかな?」
「ぼくの自己申告が信用されていない。修さん、千春を安心させてやって」
「千春さんに世話をしてもらっているってことだけど、どのくらいのことを?」
「どのくらい、というのは?」
「その、支援とか介護のレベルで言うと、どのくらいのことをしてもらっているのかという意味だけど」
容態を、医学的に正確に知っておきたかった。
冬樹は声を出さずに笑った。
「ぼくは要支援でもないし、要介護でもない。千春は、介護士でもないしね。いま彼女は、いわば秘書」
「仕事をしていなかったっけ?」
「しているよ。芝居関連のNPO団体を手伝っている。昼間は少し時間がある。彼女が来たら、コーヒーを出してもらおう」
「ぼくが淹れよう」
「お客さんに、そこまではやらせられない」
「淹れるのは好きだよ。面倒じゃない」
冬樹はうなずいた。
「修さんに淹れてもらうなんて、何十年ぶりなんだろう。お願いしよう。その前にひとついいかな」
「なんでも」
「そのペットボトルの蓋を開けてくれないかな」
意外な頼みだったので、思わず修平は冬樹の顔を見た。
「ああ」と冬樹は言った。「ときどき、蓋を開ける力が入らなくなる」
買ってきた水のペットボトルの蓋を開けて、コップを探した。
冬樹がグラスを差し出してきた。修平はそのグラスに水を注いだ。
彼は見た目よりも、衰弱している? ペットボトルの蓋も開けられないほどに? 来月には入院するというのだから、そうであってもおかしくはないのか。彼はおそらく要支援直前なのか。
広島までの旅行に耐えられるのか?
修平は椅子から立ち、キッチン、というのか、キチネットか、シンクとコンロの並んだ台所設備の前に立って、コーヒーを淹れるための道具を探した。
スチールのシェルフの中に、ブリキのコーヒー缶がある。ドリッパーと、ふたり用のサイズのサーバーも。コンロの上には、注ぎ口の細いコーヒー用のケトル。炊飯器は見当たらないけれど、冬樹はコーヒーを淹れる習慣をずっと続けているのだろう。
コーヒー缶は、コーヒー豆販売会社のもので、スペシャル・ブレンドと中身の種類が書いてある。もう挽かれた粉なのか?
缶の表示を読んでいることに気づいたのだろう。冬樹が奥から言ってきた。
「缶の中の豆は別なんだ。修さんは好きだったかな。浅煎りのエチオピア」
冬樹のその好みは、知り合ったころのままだ。考えてみると、コーヒーに限らず冬樹はあのころすでに、その後五十年も守り続けることになる自分のライフスタイルや趣味嗜好を、ものにしていたということになる。自分は長いこと、それをものにするためにもがいてきたのに。
冬樹はコーヒー缶の蓋を開けてから言った。
「千春さんの分も作ろうか」
「ふたり分でいい。カップがないし。千春はたぶん自分の飲み物を用意してくる」
ならばとケトルをコンロにかけ、コーヒー豆をふたり分挽いた。
ドリッパーを用意しているあいだに、冬樹が訊いてきた。
「あのあと、ミミとは電話した?」
「うん」と修平は答えた。「一緒に行くと言ったら喜んでいた。メリー・ホプキンの話もしたけど、返してくれなくてもいいのにと言っていた」
「どういう意味なんだろう?」
「貸したつもりじゃないんじゃないの? くれたのとは違うのかい?」
「それとも、まだ持っているとは思っていなかったのかな。LPなんて、もともとそんなに持っていなかったけど、あれが最後の一枚になったんだ」
「最後の?」
「京都に行ったときに、友達なんかに全部やったんだ。メリー・ホプキンだけは残した」
冬樹は四十代のころに、京都にも住んでいた時期がある。そのあとさらに福岡にも住んだ。修平が冬樹といちばん疎遠になっていたのは、彼が福岡に行っていた時期だ。四十代も後半になって、冬樹が東京に戻ってくるまでは、まったく会っていなかった。
「それは、奈津美ちゃんは知っていた?」
「知らないと思う。ずっと持っていたとも思っていなかったかもしれない」
冬樹が、ベッドの奥のほうに身をかがめて、LPレコードのジャケットを取り出した。すぐにあのレコードだとわかった。
メリー・ホプキンの最初のLP。
POST CARD
ポール・マッカートニーがプロデュースした、アップル・レコードの最初のリリースLPでもある。
知り合ったとき、奈津美は東芝のいわゆる赤盤というLPを持っていた。当時東芝は、レコードを赤い着色料を入れた素材でプレスしていたので、東芝のレコードはそう呼ばれていたのだ。奈津美が修平や冬樹に教えてくれた。
イギリス版のこのタイトルのLPには、シングル盤がヒットした『悲しき天使』は収められていないのだとか。イギリスのレコード業界の慣習では、シングル盤が出た曲は、LPには収録しないからだ、と奈津美が言っていた。
でも、アメリカでリリースされた『POST CARD』には、この曲が収録されている。つまりUK盤とUS盤では、同じタイトルのLPなのに、収録曲が違っている。東芝の盤は、US盤にならった収録曲なのだと。
冬樹がジャケットを修平に見せて言った。
「ミミが貸してくれたのは、このUS盤。当時の貴重品だよ。アメリカ旅行をした友達が、土産に買ってきてくれた、と言っていた」
その友達が誰か、修平には見当がついた。奈津美が二十七、八歳のころのボーイフレンドだろう。奈津美と同じ服飾業界にいた男で、修平は会ったことはないが、話は聞いていた。奈津美よりも数歳年長で、ときどき仕事でアメリカやヨーロッパに行っていたはずだ。
修平は言った。
「奈津美ちゃんは、東芝の赤盤を持っていたから、それを冬樹さんにくれたんじゃないのかな」
「不要だからって? そういうことかな。赤盤をもっていたのは知っていたけど、芝居で使いたいんで貸してくれないかと頼んだら、これを貸してくれたんだ。友達のロサンゼルス土産だって自慢しながら。その友達が、中古レコードの店で見つけてくれたんだ、と言っていた」
「同じ話を聞いてる。そのお芝居って、どれだろう。『悲しき天使』が、使われていたものって?」
「いいや。書く前はあの曲がモチーフになるかと思ったんだけど、けっきょく使わなかった。『あの日会わなければ』」
「現在から、一幕ごとに時間が過去にさかのぼっていくやつ?」
「そう。そのまま返しそびれていた。どこに行ったかわからなかった時期もあったし」
「奈津美ちゃんが何も言っていないんなら、借りたままでよかったんだ」
「小さなことだけど、ひっかかっていて」
再会したとき、奈津美があの曲を歌ってくれたことを思い出した。「月蝕洞」にはアップライト・ピアノがあって、小学生のときにオルガンを習っていたという奈津美は、芸能誌付録の歌本の楽譜を頼りに弾きながら、最初は日本語で歌ったのだった。森山良子の歌で修平も覚えていた、恋愛の歌として解釈した、官能性も強調した歌詞。
店の主人は、奈津美がギターを弾かないことを不思議がった。
ギターは弾けないんです、と奈津美が言うと、主人は、うちの客にはギターが得意なのが何人かいるから、次は伴奏を頼むといいと言った。それから彼はあわてて付け加えた。いまの歌も素敵だったけど。
奈津美はつぎは英語の歌詞で歌った。途中からは無伴奏だった。
奈津美が歌い終えると、冬樹が拍手してから言った。
「これは断然、英語版がいい」
修平は英語の歌詞の細かなところはわからなかったけれども、冬樹の感想に同意した。奈津美のいまの歌は、たぶん森山良子とはまた違う声の質と雰囲気で歌われたからよかったのだろう。
コーヒーを淹れて、揃っていない陶器のマグカップふたつに注ぎ、食卓へと持っていった。冬樹は白い大手コーヒーチェーンのマグカップを手元に引き寄せた。冬樹がひとくち飲んで、少し大げさな調子で味を誉めてくれた。
修平は言った。
「ひとりの時間が長いと、コーヒーを淹れることにも上達する」
冬樹が訊いた。
「その後は?」
「その後って?」
「田舎に戻って、お父さんを看取った後のこと」
「変わりはないよ。ほんとうにずっと」
「思い切ったな、と、あの決断については感嘆しているんだ。そういうひとじゃないと思っていた」
「そういうひとって?」
「最後には、いちばん穏当で保守的な結論を出すひとだ、と思っていた」
冬樹が言っているのは、修平が東京での生活を止めて、生家に帰った事情だ。修平は当時広告代理店を定年退職し嘱託になったばかり、それまで副業であったイラストレーションを描くことを主な仕事としていた。さいわいに、発注してくれる人脈は作っていた。若いころに一度は諦めた絵を描きたいという夢が、ささやかに実現していた。
そんなときに、離農してひとり暮らしだった父親が倒れた。子供は巣立っていたとはいえ、東京の集合住宅に父親を引き取ることは難しかった。修平は妻に、盛岡の生家で暮らさないかと提案した。イラストレーターとしての仕事は、たぶん生家に帰っても続けられるだろう。
妻に提案すると、返事は簡単に、無理、というものだった。修平はそれ以上は話し合うこともせず、協議離婚し、東京の住まいを妻に渡して生家に帰った。
あれから十五年が経つのだ。父親が亡くなったのは、修平が生家に戻って三年後だった。
「あの場合は」と、修平は冬樹に訊いた。「どういう結論が、ぼくらしかったんだろう」
「離婚はしない。会社には残る。お父さんは施設に入ってもらう。東京での生活を続ける」
「ぼくは、あんまり詳しく言ったことはないけれども、これでけっこう大胆で過激な結論を出してきた」
「途中の転職のことを言っている?」
「いいや。あれなんかはむしろ、いちばん保守的な結論だった。結論を出さなかったと傍からは見えていたときが、じつはいちばん思い切った決断だったかもしれない」
「離婚して盛岡に戻ったと手紙をもらったとき、誰かが盛岡にいるのだと思った。それで帰ったんだろうと」
「あのときは還暦だよ。何がある?」
「ぼくの還暦のときは」
ドアがノックされ、すぐに開いた。
知っている顔だった。一回紹介されただけの女性ではない。
「ごぶさたです」と千春が言った。「近藤です」
短めのジャケットにニット帽子。働く女性の通勤着と見える服装だった。見つめているうちに、何度か会ってきたときの記憶とその顔立ちが重なった。
「お久しぶりです。及川です」
この女性が近藤千春なら、最後に会ったのはいつだったろう。もう奈津美は広島に帰ってしまってからだ。もしかすると、二十年ぶりぐらいになるのか。大塚の喫茶店で、冬樹が自作の朗読会を開いた夜だ。冬樹が五十代だった当時、彼はその店で何度か自作の詩と戯曲の掌編の朗読会を開いており、修平も三度、行ったことがある。朗読会では、千春はたしかに秘書のような役割で冬樹のそばにいて、会の受付役もしていた。
千春は、途中スーパーマーケットで買い物をしたのか、大きめのレジ袋をキッチンに置いてから、部屋の中に入ってきた。お茶のペットボトルを手にしている。
冬樹が言った。
「ごめん。ここにさすがに三人は狭い」
千春が言った。
「小さくしていますから」
千春はもうひとつの椅子を引き出して腰掛け、ポーチから手帳を取り出した。
千春があらためて修平に顔を向けて言った。
「旅行に連れていってくれるなんて、さすがに及川さんだって話していたんです」
修平は言った。
「共通の友達のところだし、そのひとがお店を閉めるというときだから、いい機会なんです。一緒に行ってもらえるなら、わたしも楽しい」
「でも」千春は、ほんとうにそれでいいのかと確かめてくるような目となった。「冬樹さんが病気のことは、聞いたんですよね」
「ええ。でも広島を往復するぐらいの体力はあるってことだし。自転車で行くわけじゃないから」
冬樹が千春に言った。
「逆に、こういう旅行をするとしたら、この瞬間しかないんだ。いまはまだ終活する体力も頭もある」
千春が言った。
「終活だなんて、自分から」
「自分をごまかしても仕方がない。この旅行は終活だよ。それに」冬樹は食卓の上にまとめられているチラシとか封筒に目をやった。「広島まで行くんだという気持ちになったら、気力が湧いてきた。もういくつかついでに終活をしたいという気持ちになっている」
千春が言った。
「終活は、わたしにまかせてると言ったじゃないですか」
「そっちじゃなくて」
「なんです?」
「フェアウェル・ジャーニー」
「お別れの旅、ですか?」
「もっと直接的な言葉もあるな。エンド・オブ・ライフ・ジャーニー」
「縁起でもない」
「この広島行きをそういうものだと納得するなら、全体にポジティブなものになる。ぼくは、じっさいそういう気分になってる」
千春が黙ったので、修平は訊いた。
「広島以外にも、訪ねたいところがある?」
「ああ、ぼくは日本のあちこちで生きてきた。二度と行きたくない街もあるけれど、あらためて訪ねてみたい場所もある」
「たとえば?」
千春が言った。
「ニューヨークは絶対に無理」
「除外する」と冬樹。
修平は訊いた。
「では、名古屋、京都、それに福岡になるのかな?」
冬樹が頻繁に通ったり、何年か暮らした都市だ。彼は知り合って以降何度か引っ越しては、生きる土地を変えてきた。いったん東京に戻ってきたときもあったけれど、京都から福岡に移ったときは、東京には戻らずに直接行ってしまったのだった。
福岡に行くときは、新設される芸術系専門学校の副校長に引っ張られたのだと聞いた。その学校にいたのは、二年か三年だったろう。学校を辞めた後も、彼はしばらく東京には戻ってこなかった。事情の詳細は知らない。
冬樹が答えた。
「広島に向かいながら、途中下車で。福岡は広島の先だからはずす。東京にも、行きたいところはある。浜松にも途中下車したい」
修平は訊いた。
「浜松にも住んでいたことがあったっけ?」
「ないけど、寄れるなら寄りたい」
千春が訊いた。
「それは、街を訪ねたいってこと? それとも、その街のピンポイントのどこか?」
「ピンポイント」冬樹が食卓の上のチラシや封筒の山に目をやった。「ちょうどこのタイミングで、東京ではぼくの戯曲がひとつ、何十年かぶりに再演される。それを観たい。下北沢だ」
修平も訊いた。
「東京のお芝居は、きょうから?」
「明日から」
「東京出発を、明後日にはしないほうがいいと思う」
「きょうがゲネだ」と冬樹は芝居関係者の業界用語を口にした。ゲネプロ、ドイツ語で通しのリハーサルを意味するゲネラルプローベの略だ。冬樹の芝居に少しつきあっている時期に、修平も覚えた。「きょう、演出家に見学させてくれと頼めば、見せてくれるだろう」
「ゲネに、関係者でもないのに行けるのかい?」
自分も同行するつもりだから、そう訊いたのだ。
冬樹が答えた。
「ぼくは脚本を書いているんだし。演出家は古い知り合いだ」
「奈津美ちゃんの店の閉店は今週だよ」
「明日出発でも、ミミのライブハウスの閉店までには間に合う。ライブは三日続くんだから」
千春が少し不安そうに言った。
「移動が毎日続くんですよ」
冬樹が、心配ないと言うように首を横に振った。
「新幹線に乗っている時間自体は、たいしたものじゃない。浜松なら一時間十五分で行ける」
修平は確かめた。
「ひとつの街に一日かけるんだよね」
千春が冬樹に代わって答えた。
「それがいいと思う。ゆったり目の旅程を組んで、毎晩ホテルで休んでください。出発は次の日」
「毎晩、ビジネス・ホテルを取りますよ」
千春がまた冬樹に訊いた。
「そのセンチメンタル・ジャーニーには、甲府は入れなくていいの?」
冬樹の出身地だが、いま彼はその名を出さなかったのだ。行かなくてもいいのだろう。
冬樹が答えた。
「いま、この旅行では行きたいわけじゃない。これまでも頻繁に帰っていたし」
「では、きょうはそのお芝居のゲネを観て、明日出発?」
冬樹が修平を見た。
「そういうことで、いいのかな」
「いいよ。ゲネプロを観たあと、今晩はホテルに泊まって、明日また迎えに来る。明日から四日目に広島に着くことになる。明日、浜松には何時ころに着いているのがいい?」
「二時前後には」
「新幹線のチケットをきょうのうちに買ってしまう。お芝居のほう、劇場は下北のどこなんだろう」
冬樹がチラシを渡してくれた。
A4サイズの、いわば演劇公演の定番規格のチラシだった。表がカラーで、ひと目を惹くビジュアルと惹句。主要なスタッフ、出演者、それに劇場の名。
劇場は、修平がたぶん行ったことはないところだ。最近、というか、この二十年くらいのあいだにできたものではないのだろうか。下北沢にある、おそらく観客席が百以下の小劇場のようだ。
チラシの裏はモノクロで、出演者たちひとりずつの顔写真と上演の日程。劇場の地図とアクセス案内。
芝居のタイトルは、『夜更けの水位』だ。修平も観ていた。池袋の小劇場での初演を初日に、奈津美と一緒に観に行ったのだ。三人がつきあうようになって五年目ぐらいだったろう。
冬樹の脚本は、たぶん彼の学生生活に直接題材を取ったものだ。登場人物は三人だけ。国文学の大学教授と、その弟子筋の若い研究者、研究者の恋人の女子学生。三角関係の物語の一幕ものだ。
演出したのは別の人物で、その演出家が主宰している小劇団の公演だった。そのころ冬樹は、知り合いの演出家から頼まれて芝居の脚本を書くようになっていた。戯曲の翻訳をしているうちに、自分も書き出したのだ。冬樹に言わせるなら「面白がってくれる演出家もいて」、修士課程を出たころには完全に自分の表現活動として書いていたのではなかったろうか。
冬樹が自分の劇団を立ち上げて自作を演出するようになるのは、一九八一年だ。
現代イギリス戯曲の翻訳からの出発だったから、冬樹の作品はいわゆるアングラやその後の小劇場の芝居とは少し違った傾向のものだった。バラエティ・ショーっぽい芝居も苦手としていた。また、やはり冬樹に言わせるなら、スタインベックの影響も大きい、とのことだった。じっさい彼は後に、自分の翻訳で『二十日鼠と人間』も上演している。
冬樹がそのチラシを引き取ると、スマートフォンを手に取った。
彼は電話の相手に言い始めた。
「堂内です。いま、もうゲネが始まってるかな。あ、そう。もし迷惑でなければ、ちょっと覗かせてもらっていいかな。もうひとり、初演を観ていた友達と一緒に行きたいんだ」
「何も、口出ししたりしないよ。観るだけ。ほんとうは明日行きたいんだけど、ちょっと用事があるんで、きょうのゲネを観られたらと思って。懐かしいし、クニちゃんはどう演出するのか、すごく楽しみで」
「五時くらいから? 大丈夫。その前に行ける」
「場所はわかる。うん。じゃあ、後で」
冬樹は通話を終えると、修平たちに言った。
「歓迎してくれるってさ。五時に下北沢。ここを四時に出ればいいかな」
修平は腕時計を見た。いま一時十分。自分はいったん宿を決めて、チェックインしてきたほうがいいだろう。
「失礼」と冬樹が立ち上がった。トイレに行くようだ。
トイレのドアが閉じられてから、千春が言った。
「冬樹さんは、見た目以上に衰弱してるんです。迷惑をかけるかもしれません」
修平は訊いた。
「何か特別に注意することとかは?」
「薬を確実に服んでもらってください。駅前あたりまで歩くのも、ほんとうはつらそうなんですけど」
「痛みがあるんでしたね?」
「ええ。楽なのは、横になってじっとしていることのようなんです」
「無理はさせません。一日に一回移動して、思い出の場所を訪ねるくらいなら、そんなに身体に負担にはならないでしょう。でも、診断は急だったんですね」
「病院嫌いなんで、痛みを放っておいたら進行していたんだそうです」
「千春さんは、ずっと冬樹さんをそばで見てきたんですか?」
「ずっとってわけじゃないけど、放っておけないし。わたし、冬樹さんと一緒に暮らしてもいいと思うようにもなっていて」
修平は千春を見つめた。それは具体的にはいつごろからのことなのだろう。冬樹の病気がわかってからか? もっと前からか?
修平の表情で、千春は修平の疑問を察したようだった。
「冬樹さんがいい歳になってきてから。だけど、冬樹さんはああいうひとで」
「ああいうひと、というと?」
「他人と一緒に暮らすのが苦手なんです。人生に同伴者が要らないひとなんです。そうでしょう?」
「どうだろう。友達と一緒に旅行をするのは、たぶんそんなにいやではないひとですよ」
「それは修平さんとか」小さく間を開けてから、千春は続けた。「奈津美さんとかと一緒の場合です。わたしは、冬樹さんとは旅行をしたこともない」
それは意外だった。
「そうなんですか?」
「ええ。冬樹さんは、一緒に誰かと暮らすこととか、誰かと一緒に旅行することを、自分の美学とは合わないと感じているのかもしれません。修平さんたちは別だけど、違いますか?」
「たしかにそういうところはありますね」
「修平さんたちは、何度も一緒に旅行していますよね」
「ええ。そもそも旅行中に知り合った仲ですから。ぼくらが何度も旅行できたのは、そのせいもあるのかな」
「そういう話を聞いて、いつもうらやましく思っていました」
「一緒に暮らそうと、話をしたことはなかったんですか?」
「ありますよ。でも、それを口にするたびに、笑って逃げられた。まったく会うこともなかった期間も、ずいぶんあります」
トイレのドアが開く音がした。修平たちは会話をそこでやめた。
冬樹が出てきて言った。
「ぼくが何から逃げたって話をしていた?」
千春が言った。
「わたしから」
冬樹はとくに戸惑いも見せなかった。
「それは、愛ゆえに、のことだって」
「逃げ回ったのは、認めるんですね」
「千春のしあわせが一番だから」
修平は割って入った。
「その話はふたりだけで。ぼくはホテルを決めて、荷物を置いてくる。四時前にまた来る」
冬樹が修平に言った。
「シャワーを浴びて、髭を剃っておくよ」
千春が冬樹に訊いた。
「わたしは料理を作っておこうと思ったけれども、要らなくなった?」
冬樹が答えた。
「今晩と、明日の朝までの分だけでいい」
修平は自分の荷物を持ち上げて、ふたりに言った。
「それじゃあ、あとでまた」
千春が言った。
「わたしはたぶん、それまでに帰っています」
修平はふたりに会釈して、玄関口へと向かった。
奈津美に、予定が少し変わったことを伝えなければならなかった。アパートのある小路から十分に離れたところまで来て、修平は立ち止まった。
メールにするのがいいのか、肉声の電話がいいのか、少しだけ迷った。先日の電話も、久しぶりだった。SNSで再会してからは、あまり直接の電話はしないようになっていたのだ。自分は少しフォノフォビアの気があると自覚もしているし、電話ではどうしてもぎこちなくなる。
でも、この連絡は電話のほうがいいだろう。
「はい」と、奈津美がすぐに出た。期待の感じられる声。「いま、どこ?」
「まだ東京。冬樹さんのアパートに来ていた」
「これから出発ですか?」
「その件なんだけど、東京を明日出発にしたい。土曜日に広島に着く」
「車で来るわけじゃないですよね」
「新幹線だけど、一気に広島に向かうのはやめようということになった。やっぱり冬樹さんの体力が心配で」それが一番の理由ではないが、この程度の嘘は許されるだろう。「冬樹さんは、だったら思い出のある街で新幹線を途中下車して、四日目に広島に着く予定にしようということになって」
「ふうん」と、奈津美は不思議そうな声になった。「思い出の街って、京都とか?」
「名古屋も。浜松にも行きたいところがあるって」
「浜松、名古屋、京都か。三人でも行っていますね。どういう思い出なのか、言っていました?」
「いいや。でも、京都には住んでいたんだし、ぼくの知らないようなこともいろいろあるんだろう」
「ひとに会いたいってことなのかな」
「そういう話ではなかった。ピンポイントで訪ねたいところがあるとか」それはたしかに、人に会いに行きたいという意味なのかもしれないが。「きょうは、夕方から下北に行くことにした。冬樹さんの書いたお芝居が上演されるんだ」
「どのお芝居だろう?」
「『夜更けの水位』」
「あ、観ましたね。教授の助手は冬樹さんがモデルでしょうと言ったら、ぼくは自分のことは書かない、と言われたけど」
「ずいぶん久しぶりの再演で、冬樹さんにも思い出深い作品みたいだ」
「土曜日が、特別ライブの最終日で、お店の最後の日。待ってます」
「途中、どこまで来ているか、毎日報告しようか」
「いいですね。毎日近づいてくるのを意識して、店の最後の日を迎えるなんて」
「じゃあ、土曜日に」
通話を切ろうとすると、奈津美があわてて言った。
「あ、もうひとつ」
「ん?」
「広島に来るのは、修さんと冬樹さんですよね?」
「うん、ふたり」
「いいな。わたしも入って、三人での旅行って、もうないのか」
同じことを、自分も一昨日冬樹と電話で話したときに思った。自分たちは若いころ、二十代から三十代にかけて、何度も一緒に旅行した。奈津美がまず提案し、修平と冬樹がそのプランに乗るというかたちの旅行が大半だった。
ニューヨークにいる冬樹に会いに行く旅行は、修平と奈津美のふたり旅だったが。
修平と冬樹は、奈津美が広島で開いたライブハウスを訪ねるために、一緒に旅行したこともあった。
でも、冬樹がステージ4の膵臓ガンとなれば、自分たち三人が一緒に旅行することはもう確実にない。冬樹が冷静に意識しているように、この旅行は彼のエンド・オブ・ライフ・ジャーニーであり、自分にとってはそれを見届ける旅となる。
奈津美が言った。
「あ、でも、ふたりして来てもらえるだけでもうれしい。楽しみにしています」
下北沢の駅は、大きく改装されていて、修平は戸惑った。
盛岡に帰ってからこの間、もちろん東京には何度も来ているけれども、下北沢には来たことがなかったのだ。南口の改札口を出た先の風景も、ずいぶん違って見える。ビルの林立はないけれども、記憶にあった高架の鉄道は消えていた。あれは何線だったか、地下に潜ってしまったのか。
冬樹の付き添いのつもりでここに来たけれども、しばらくは冬樹に道案内をしてもらう必要がありそうだった。
ところが冬樹も、南口を出たところで周囲を珍しげに見渡して言う。
「変わってしまったな」
修平は訊いた。
「冬樹さんも、そんなに来ていなかったのか?」
「芝居から離れて久しいから。だけど、劇場はわかる」
彼が、こっち、と修平の先を歩き出した。衰弱などは感じさせない歩き方であり、姿勢だった。服装は、黒のロングコート。その下にはやはり黒づくめの上下と黒いシャツだった。最初に会ったとき以来、冬樹の服装はほとんどずっとこの印象のままだ。
雑踏の中を歩いたのは、ほんの百メートル、いや、それ以下だったかもしれない。改札口から遠からぬところにその劇場はあった。ビルの一階に案内が出ている。劇場自体は地下にあるようだ。席数が百前後というから、ごく小さな部類の劇場なのだろう。
作業ズボンをはいた中年の男が、芝居の案内看板の前に立っている。演劇関係者の雰囲気があった。
冬樹がその男に近づいて話しかけた。その男はすぐに階段を示した。
冬樹について階段を降り、劇場ロビーにあたる空間に行くと、そこにも芝居の関係者らしき男女が数人いた。
冬樹が若い女性に近づいて名乗った。
「堂内というんだけど、井上さんは中ですか?」
チラシで、井上邦彦という男が演出家だと覚えてきた。冬樹が電話で、クニさん、と呼びかけていた男が、その井上なのだろう。
女性が客席に通じるドアを開けた。暗幕がかかっている。女性は中に入ると、すぐに戻ってきた。
「どうぞ」
冬樹について、修平もその劇場の客席へと入った。中はまだ、開演前の「客電」と呼ばれる照明の状態だった。
変わったかたちの劇場だった。正面にステージがあるが、ステージの右手側にも客席があるのだ。ステージの側から言うと、九十度角度をつけて、二方向に正面がある。ステージには幕は降りておらず、照明は作業用、準備用の「前明かり」となっていた。
ステージの上では、舞台監督らしき中年男性と、スタッフらしき若い男たちが数人、ステージの方々を指さしながら話している。ステージには、テーブルと椅子が三脚置かれていた。あとは何もない。シンプルな、黒っぽい舞台だった。
客席には、五、六人の関係者がいて、ステージを見つめている。客席最後尾の列には、照明とか音響の係の機材が置かれ、担当の者が椅子に着いていた。
ステージすぐ前の席から男がひとり立ち上がって、脇の通路を修平たちのほうへと歩いてきた。背の高い、初老の男だった。短髪で、口髭を生やしている。井上邦彦だろう。
「堂内さん」と、その男が言った。「光栄です。来てもらえるなんて」
「ぼくも光栄だ」と冬樹が言った。「このホンが、まだ生きていたんだから」
「全然古くなっていない作品ですよ。テーマはいまでも通用します」
冬樹は修平をその男に紹介してくれた。
「ぼくの芝居の、古くからの観客。及川さん。ぼくの芝居のチラシのデザインもよくやってもらった」
「ああ」と男は言った。「筋金入りの堂内冬樹ファンなんですね。演出の井上です」
冬樹が言った。
「井上さんは、ぼくの芝居にも、役者として何本か出てくれている。『あの日会わなければ』にも」
修平は言った。
「初演を観ています。どの役でしたっけ」
「ウエイターでした」
「ああ」覚えてはいなかったが。
井上はまた冬樹に顔を向けた。
「最近あまり書いていませんよね?」
「そうだね」と冬樹が苦笑して答えた。「芝居仲間がどんどんリタイアしていってるから」
「堂内さんのホンなら、やりたいところはいくらだってあるでしょうに」
「もうないよ」
「このとおり、ぼくはやりますよ」
「冒険だ。そう誰かに言われてないかい?」
「全然。だってそもそも」
井上の言葉が途切れた。不自然な切れ方だった。修平はその後に続く言葉を想像した。
「そもそも」と井上は言い直した。「ぼくは他人の評判を気にしないほうですから」
冬樹が、井上から視線をそらしてうなずいた。
井上は腕時計を見てから言った。
「あと十分くらいで、始まります。堂内さんに観てもらうなんて、緊張しますけど」
「どうして?」
「手厳しい批評がきそうで」
「何も言わないよ。舞台は、演出家のものだ。いったん手を離れたら、作者は楽しむだけだ」
「堂内さんの厳しさは、評判でしたから」
「ほんとうに?」
「冗談です」
否定したようには聞こえない口調だった。
ステージの上から、舞台監督らしき男が井上を呼んだ。
「じゃあ」と井上は言った。「後ほど、少し遠慮ぎみの助言などを」
「言わないって」
井上は通路をステージのほうへと向かっていった。
冬樹が後ろ寄りの列の椅子に腰をかけた。修平はその右隣りだ。
冬樹が訊いた。
「盛岡では、芝居は観ているの?」
妙に唐突な質問だった。
「いいや」と修平は答えた。「完全に無縁になってしまった。商業演劇のツアーはときどきあるようだけど、小劇場のお芝居なんて、あるんだろうか。よくわからない」
「修さんは、知り合ったときも、ほとんど芝居を観たことがなかったものね」
「宮澤賢治だけだった。『セロ弾きのゴーシュ』とか『注文の多い料理店』。子供向けのものだけど」
「ミミも同じようなことを言っていたな。『セロ弾きのゴーシュ』を観たって。子供のころには、あと『森は生きている』とか」
「演劇は、ぼくにとっては、東京で初めて出会った都会の文化だった」
「おおげさな。賢治を出した土地のひとが」
「ぼくが育ったのは、盛岡市内ではなかったから」
ステージの上から声があった。
「それじゃあ、そろそろいきます」
井上が応えた。
「はい、始めて」
客席部分もステージの上も暗くなった。
知り合った時期、冬樹はお芝居に関係していたわけではなかった。観客としての演劇青年でもなかったろう。ただ、大学院の担当教授の指示で、現代イギリス戯曲の下訳をしていた。
だから会うときはたいがい、冬樹はわりあい大きめの英英辞書とノートと、翻訳中の戯曲のプリントとか本を持っていた。三人がよく会うようになった酒場の月蝕洞でも、あまり広くはない店の隅のテーブルで、翻訳作業をしていることが多かった。修平や奈津美が店に到着したところで、やっとその作業をやめるのだった。
最初のころ、奈津美が冬樹のその翻訳の仕事について、興味津々という様子で訊いたことがあった。
「お芝居の台本を翻訳してるんですね?」
冬樹が、万年筆を持った手を止めて答えた。
「下訳だけどね。翻訳者として名前が出るわけじゃない」
「冬樹さんは、前からそういうお芝居の翻訳をしたくて、英文科に入ったんですか?」
「いいや。大学に入って初めて戯曲を読むってことを覚えた。先生の影響」
「いま訳してる戯曲は、まだ日本語には翻訳されていないんですね?」
「たぶんね。最近の作品だから。でも、もう訳しているひとがいるのかもしれない。ひょっとしたら、もう上演されているかな」
「いま訳しているのは、なんていう劇作家さんの作品なんですか?」
冬樹は、A4サイズほどの軽装版のその本の表紙を奈津美に見せた。
「ハロルド・ピンターって劇作家。『オールド・タイムズ』」
「どんなストーリーなんですか?」
「ある夫婦が田舎に住んでいて、そこに奥さんの友達が訪ねてくる。三人の思い出話がそれぞれに違っていて、観客は昔何があったのかがよくわからなくなる。奥さんとその友達はレズ同士だったみたいでもあり、亭主はその友達とも関係があったようにも思える」
「おお、緊張する話ですね」
「舞台の上に爆弾が転がっているみたいな芝居だな」
「種明かしでは?」
「これが、はっきりとはわからないんだ。でも、たぶん観客が感じたことはじっさいそうだったんだ」
「教えてくれ、って言いたくなりません?」
「というか、訳していると、その答は台詞の中ではっきり言われているような気がして、何度も訳が正しいのか確かめることになる。えらく厄介な戯曲だな、ぼくには」
「答が見つからない作品は、観ても難しそう」
「この劇作家には、そんなに難しくもない作品もあるよ。映画になった『召使』とか」
「面白いんですね?」
冬樹は苦笑した。
「『召使』は面白かった。だけど、このひとの芝居はこういうものなんだと心構えがないと、終わったあとに、ぽかんとしてしまうかもしれない」
「アングラも、わたしはほとんど観ていない」
「アングラにも、ぽかんとしてしまうものはあるけど」
修平は思い出した。奈津美が『セロ弾きのゴーシュ』や『森は生きている』といった作品の名を挙げたのはあのときだ。
知り合ってやはりまだほんの二、三カ月しか経っていないころ、修平が月蝕洞に行くと、冬樹がそれまで観たことのない青年と同じテーブルに向かい合っていた。あいだに本を一冊置いている。
修平はカウンターの席に着いて、ふたりの様子をしばらく横目で見ていた。見知らぬ青年が冬樹に何か訴え、説得しようとしている様子だった。冬樹は最初はあまり気乗りしない表情だったが、最後には微笑してうなずき、本を手元に引き寄せて、その上に自分の辞書を置いた。
やがてその青年が店を出て行き、冬樹が修平の隣りにやってきた。
修平は訊いた。
「何かの打ち合わせ?」
冬樹が答えた。
「アルバイト。やることにした」
「翻訳の仕事なんですね?」
「戯曲。短いやつを一本。ギャラをもらえる」
「いまのひと、知り合いだったんですか」
「いいや。ピンターの下訳をやっていることを耳にしたらしくて、伝(つて)をたどってこの店にやってきた。芝居をやっている男」
「またピンターを?」
「べつのイギリスの劇作家のもの」そうして冬樹は、修平にごちそうさせてくれと言って、マスターに白ワインを注文したのだった。
「こういう日のために、英語を勉強してきたんだ」
「こういう日というのは?」
「自分の英語力にカネが支払われる日」
また少し思い出した。奈津美が、専門学校を卒業しても東京でまだしばらくは暮らすと言ってきたのが同じ夜だった。白ワインで乾杯した記憶があるから、間違いはないだろう。
修平が、滅多に飲むこともない白ワインを、なめるように飲んでいるときに、店に奈津美が現れた。うれしそうな顔だった。
奈津美は、服飾の専門学校を卒業したら広島に帰らねばならないと言っていたけれど、ほんとうはそのまま東京で暮らしたいのだった。ただ、親は、帰ってくるから、という約束で専門学校への進学を許したのだ。その約束を違えて東京で働きたいとは言い出せないと嘆いていた。
冬樹がアドバイスしていた。親も反対できないような服飾関連の会社に就職してしまえ、と。そこで働くことは、広島ので家業の洋品店で働くときに絶対に役に立つから、もう三年だけ許して欲しいと言えと。三年後にも何か同じような理由で、延ばしていけばいい。そのうち親も折れる……
その夜、カウンターの修平と冬樹とのあいだに入った奈津美に、修平は言った。
「就職、いいところに決まったんだね」
「わかります?」と奈津美が言った。
「おでこに書いてある」
「就職が決まって、昨日親に電話して、もう三年間くらい、東京にいてもいいことになった。うちの店で働くための修行期間延長です」
冬樹が訊いた。
「どこで、どんな仕事に就くの?」
奈津美は、中堅どころのアパレル企業の名を出した。主に女性用衣料品の製造・販売の会社。もともとは繊維メーカーが母体ではなかったろうか。
「そこを受けていたんですけど、昨日採用の通知が来て」
冬樹が言った。
「最初一年間は直営店勤務とかって約束で、けっきょくずっと店員のまま、本社勤務にはさせないところじゃないの」
「残念ながら違います。本社企画部です。テキスタイル・デザインの部署に決まったんです。店舗での研修は三カ月だけ」
「それでも、専門的な訓練を受けた子を、三カ月も無駄に遣うんだな」
「我慢できる期間です。親はむしろ、そっちの研修のほうを喜んでいた」
「まだまだこの店で会えるのか」
「いやじゃないですよね」
「歓迎しているんだよ」
「ちょっと乾杯の気分じゃないですか。だから今夜はきたんです」
冬樹が、カウンターの中の店の主人に言った。
「こちらのミミちゃんにも、一杯ワインをご馳走したい」
主人がうなずいた。
奈津美が冬樹に訊いた。
「冬樹さんたちは、何かいいことがあったんですか?」
冬樹が答えた。
「ぼくの新しいアルバイトがいま決まった。もしかしたら、独立への一歩になる」
「よくわからないけど、ごちそうになっていいんですか?」
「お祝いしよう」
全員がそれぞれワイングラスを持って乾杯した。自分には、ここでは祝い酒を飲む理由がないなと、ひと口飲んでから修平は思ったのだった。
ステージの上が明るくなった。出演者三人が、井上のほうに向かって深々とお辞儀した。
舞台監督がステージの横に出てきて、腕時計を確認した。
井上が立ち上がって、ステージに上った。出演者と舞台監督が、井上を囲んだ。演出家による講評とか、いわゆるダメ出しとかがあるのかもしれない。
修平も観たことのある芝居だけれども、途中からストーリーを覚えていなかった。だから、退屈することなく観ることができた。冬樹の書いたオリジナルのままでの上演なのか、それとも演出家が多少手を入れているのかわからなかった。
客席の明かりもついたから、修平は冬樹の横顔を観た。
彼も視線に気づいて修平に顔を向けてくる。目がうるんでいるように見える。
「どうだった?」と冬樹が訊いた。
「面白かった。たしかに全然古くなっていないね」
「ほんとうにそう思うかい?」
「嘘は言わない」
井上がステージを下りて、冬樹のほうへと歩いてきた。
「どうでした?」と井上が訊いた。出来ばえには自信がある、と言っている顔と見えた。
冬樹が言った。
「よかった」冬樹の声にも、嘘はないとわかった。「もっと翻案しているのかと思った。大胆に変えてもよかったのに」
「ケータイがなくても通じる話なんですよね。だから翻案の必要はなかった。ただ、台詞は微調整させてもらっています」
「気にならなかった」
「このあともまた少し作業があるんで、一杯ってわけにはいかないんですが」
「うん、ぼくらもだ」
冬樹が腰を上げたので、修平も立ち上がった。
冬樹は、田端駅に着くまでほとんど無言だった。不機嫌ではないし、落ち込んでいるけでもない。むしろずっと、自分が書いた芝居を観たその余韻に、しみじみとひたっているかのような表情だった。
田端駅から冬樹のアパートに向かって歩き、アパートの前に立ったとき、冬樹が修平を見つめて訊いてきた。
「ぼくって、そんなに悪い仕事をしてはいなかったのかな」
修平は言った。
「いい仕事を続けてきたよ」
「無理に言わせたかい」
「正直に答えた」
「連れていってもらって、よかった。ここでいい。明日からも、よろしく」
「十一時半に迎えに来る」
「ありがとう」
冬樹は手を振って階段のほうへと歩いていった。
(つづく)